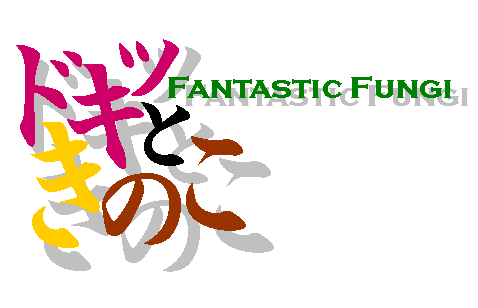 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
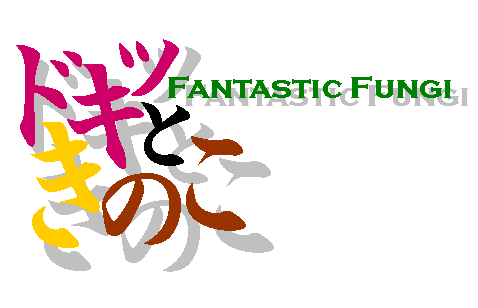 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
| 2018年 6月24日(日) 矢田山子どもの森 奈良県大和郡山市 |
昨日は梅雨寒の一日だったが、今日は朝から晴れて一気に気温が上昇している。気温差が10度もあると、なかなか体が付いていけない。 歩き始めるとすぐに、シロイボカサタケが目に留まった。他の場所でもいくつも見かけた。 太い木の根元に特徴のないイグチが出ていた。この特徴のない姿はおそらくアワタケに違いない。管孔が大きく膨らんで、柄が見えないほどだった。 薄暗い森の中で、神秘的な色のカサを見つけた。これがアオエノモミウラタケではないかと思ったが、どうも決め手に乏しくイッポンシメジ属としておく。 そのすぐ傍には、枯れ木に生える極小菌があった。クヌギタケ属だろうと思うが、ここでは未同定種としておく。 今度は2本だけ立っているキイボカサタケを見つけた。やや老菌で、アングルを変えようとしたら1本折れてしまった。 濃い黄褐色のアンズタケ属菌があった。ここでは以前にも見つけている。サイズは小さいが、なかなか個性的なスタイルが絵になる。 最後は、白、黄色に続いてアカイボカサタケを見つけた。この森では秋にもこの3色を見た記録がある。 まだウグイスとホトトギスが競い合うようにさえずっている。もうこの時期は、求愛より縄張りの意味が強いのかもしれない。 |
|
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2018年 6月23日(土) 「ドキッと塾」撮影会 京都府精華町 「けいはんな記念公園」 |
今年3回目の「ドキッと塾」撮影会は、雨予報が出ていたので参加者は少なかった。いまにも降り出しそうな雲行きだったが、何とか歩くことはできた。 駐車場を離れてすぐに、群生する小型菌を見つけた。これは「コツブ」の付かないヒメヒガサヒトヨタケだろうと思う。 そのすぐ先には、チチアワタケの群生もあった。その後の園内でもたくさん見ることができた。 小型のウラグロニガイグチを見つけた。これは頭に「コ」が付く方ではないかと切ってみたが、どうやら違うようだ。 散策路に沿って広い範囲で、クロアシボソノボリリュウタケを見ることができた。形のいいものを選んで撮った。 ようやく夏のきのこが出始めた。コテングタケモドキなどのテングタケの仲間だが、まだ数は少なかった。 苔の斜面にキチャハツが出ていた。本種には失礼だが、こんなきれいなキチャハツは初めて見た。 垂直の斜面からフモトニガイグチが生えていた。前はクリイロニガイグチと分けていたが、同種らしいので、より情緒のある名前の方で扱っている。 コースの最後で気になる種類が見つかった。ノボリリュウタケなのだが、サイズが小さくて真っ白だ。リンクサイト「きのこワールド」(川口さん)に時どき登場する、シロノボリリュウタケによく似ている。おそらく同種なのだろう。 昼からは本降りの雨になってしまったので、昼食を後回しにしてコースを急いだ。大型菌はまだまだ少ないが、ずいぶん種類が多くなってきた。これからが楽しみだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2018年 6月17日(日) むろいけ園地 大阪府四条畷市 |
今日も晴れてすがすがしい風が吹いている。昨日より条件がいいはずなのに、今日はきのこが少なかった。 最初は、カサが反り返って良く分からないきのこで、採取してみてやっとヒロハウスズミチチタケだと分かった。2本がくっついていた。 枯葉が堆積したふかふかの斜面に、ニセクサハツが数本生えていた。近くには幼菌もあった。 前回(5月4日)と同じ場所に、まだツチヒラタケが出ていた。今回は小さな1個だけだった。 朽ちた太い広葉樹の材に、小型の白いカサを見つけた。ヌメリツバタケだろうと覗き込むとツバがない。ウラベニガサの仲間らしいので、調べるとハナヨメタケらしいことが分かった。 最後は昨日に続いてイボカサタケだが、今回は黄色だ。色鮮やかなキイボカサタケだった。 少しずつ顔ぶれが変化してきているが、野山が賑やかになるのはもう少し先のようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2018年 6月16日(土) 上野森林公園 三重県伊賀市 |
昨日の午前中まで、近畿では梅雨らしいシトシト雨が降った。地中深くまで水分が浸み込むような、こういう雨にきのこは反応する。 歩き始めてすぐに小型のきのこが目に留まった。アセタケ属だろうと思ったが、ヒダには真っ黒の胞子ができていた。どうやらナヨタケ属のようだが、種名までは分からない。 しばらく進むと、きつね色のきのこが2本立っていた。まさしく見たままのオオキツネタケだ。 針葉樹の材からミドリスギタケが出ていたが、日光が当たって撮りにくかった。そばには幼菌も出ていた。 ベンチで休憩して周囲を見回すと、ダイダイイボカサタケが数本立っていた。一番大きなペアを撮った。 ヤマドリタケモドキが1本だけ出ていた。ここの本種もかなりせっかちなようで、ずいぶん早い発生だ。 終盤は疲れて足を引きずって歩いていたが、視界の端にきれいな姿のきのこが見えた。とてもいい状態のガンタケだった。 最後のビジターセンター付近では、日の当たる斜面に白っぽいイグチが出ていた。初めて見るアオネノヤマイグチだ。 弱い風があって汗は出なかったが、陽射しが痛いほど強い。すっかりバテて車に戻った。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2018年 6月10日(日) 大和民俗公園 奈良県大和郡山市 |
台風5号の影響で雨模様の予報だったが、一向に降る気配がない。曇天で気温が低めなので、探索には好都合だ。 いつも通り入り口前の桜並木を歩くと、小さな黄色いきのこがあった。アカヤマタケ属のようだが、老菌は色が抜けて白くなっていた。 その近くでは、少々カサを開き過ぎのムジナイッポンシメジが出ていた。ここではよく見かける種類だ。 園内ではまず、やや大型のベニタケ属を見つけた。色や味もはっきりせず、名前は分からない。 次も大きなベニタケ属だが、これはすぐに名前が分かった。クロハツモドキだ。 小型ながらきれいなイグチを見つけた。コケの上に出ているアケボノアワタケだ。柄に広がる赤い粒点の網目がひときわ美しい。 その先で大きなきのこが2個、目に飛び込んできた。アカカバイロタケだ。大きい方はカサの直径15センチを超えていた。 次に見つけたきのこも、写欲を掻き立てる種類だ。2本のコツブヒメヒガサヒトヨタケが、ひどく傷んだクサハツの横に立っていた。 小型のチチタケ属を見つけたが、しっくり同定することができない。乳液の色は透明だった。 最後は、まばらに数本出ていたアカシミヒメチチタケだ。本種は徐々に発生数が増えてきているように思う。 午前の2時間ほどでたくさんの種類を撮ることができた。撮影が楽しくなるきのこも、少しずつ増えてきたようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2018年 6月 9日(土) 矢田山子どもの森 奈良県大和郡山市 |
晴れれば「真夏日」、降れば「土砂降り」。今年の梅雨もまた、かなり乱暴者になりそうだ。 歩き始めていきなり、名前の分からないきのこに出会った。小型で褐色という、一番タチの悪いヤツだ。コガサタケ属かと思ったが、ヒダの幅が広くて違うようだ。未同定菌にしておく。 次はさらに小さいが、これは分かりやすい。久しぶりに見たハナオチバタケだ。 生きたコナラの大木に出る小型菌が、今年も出ていた。イヌセンボンタケに似ているが、おそらくクヌギタケ属だろうと思う。 次も小型の白いきのこ。一旦はパスして行きかけたが、こんな時のためにマクロレンズを持っているのだからと、撮ることにした。たぶんヒノキオチバタケなのだろう。 ナガエノチャワンタケがたくさん出ていた。小型のものが多かったが、表情が面白い。 ウスムラサキフウセンタケが出ていたが、あまり紫色が出てなくて残念だった。 最後はムササビタケの群生。朽ちた倒木にビッシリ並んでいた。コケの上に出た幼菌は面白いシーンだ。 雨の直後なので、晴れて風が止まると地面から湯気が立ち上るような蒸し暑さが襲ってくる。汗が噴き出す季節が近づいてきたようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2018年 6月 3日(日) くろんど園地観察会 大阪府交野市 |
今日も晴れて暑くなりそうだが、午前中は25度前後の予報なので汗が噴き出すほどではなさそうだ。 集合場所の公園には、あちこちにオオヒメノカサが菌輪を描くように生えていた。 園に入るとまず、きれいなイタチタケが出迎えてくれた。ちょうどカサを開いたいいタイミングだった。 先月に続いて今回も、朽ちた材にアカエノベニヒダタケが出ていた。ヒダがきれいなピンク色だった。 黒く朽ちた材に極小の白い粒が付いていて、ルーペで見るとパイプタケのように見えた。見たいと思っていた種類だと喜んだが、詳しく観察するとパイプタケそのものではなさそうとのことで、ここでは未同定種としておく。 まだ腐朽の進んでないコナラの間伐材に、たくさんのゴムタケが出ていた。縁の部分に焦げ茶色が残る、まだ新しい群生だった。 次も気になるきのこだ。一見してベニタケ属だと分かるのだが、なんと、スギ(ヒノキ?)の材から生えている。少し離れた材からも生えていた。 炎天下でカサがテカテカに光ったきのこがあった。どうやらクサウラベニタケのようだ。 次もまた、強い日差しを浴びて立っているムジナタケが見つかった。 もうすぐ梅雨に入るらしい。この調子なら去年のような大凶作にはならないだろう。・・・ならないで欲しい。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2018年 6月 2日(土) 太陽が丘公園 京都府宇治市 |
梅雨入りが秒読み段階に入ったようだが、今日はカラッと晴れて気持ちがいい。久しぶりに宇治の公園を歩いたが、きのこは少なかった。 最初はオオホウライタケだが、小型のものが多くてきれいな群生には出会わなかった。 地面に球形のきのこがたくさん出ていた。1個を切ってみると中は真っ白で、外皮の断面が3層になっていた。ツチグリだ。この後一斉に開くのだろうか? 芝生広場の日の当たる所に、今年もテングツルタケが出ていた。直射日光をまったく気にしないきのこだ。 植え込みの下に、1本だけ黄色っぽい小型菌が出ていた。名前が分かりそうなのに分からない。未同定菌だ。 最後はカサの反り返った大きなテングタケ。本種はなかなかいい瞬間に出会えないきのこだ。 ベンチに腰掛けると、涼しい風が通って気持ちがいい。しかし、きのこはそんな爽やかさが嫌いのようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||