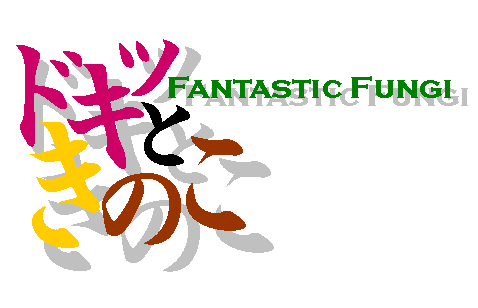 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2004年 4月 |
| 2004 | 2003年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2005年へ |
| 2004年 4月29日(木・祝) 寺家ふるさと村 神奈川県横浜市 |
いよいよゴールデンウィークが始まった。初日の今日は2日前に雨も降って、気温も高くなり朝から雲ひとつ無い行楽日和。かなり面白いものがきっと見つかると期待して、きのこ仲間4人で探索。 ウメの樹下のハルシメジ、ヤマグワの樹下のキツネノワンやキツネノヤリタケはともに空振りで、大の大人4人がかりでやっと見つけたのは1ミリほどしかない子嚢菌。オレンジ色の子嚢盤に細い柄が伸びて何かの実に付いている。付近に落ちている実や頭上の木を観察すると、どうやらヤマザクラの種子から生えているようだ。初めて見るもので図鑑にも見当たらない。 道沿いの倒木に柄の黄色いきのこが生えていた。カサと柄の表面はビロード状に毛が生えていて、ヒダが黄色い。一見エノキタケのような姿だが、これはビロードエノキタケだ。 谷戸の奥の竹やぶにアミガサタケが生えていた。高さは13センチほどで頭部は黄色く、網目が縦に比べて横脈がはっきりしないので、オオトガリアミガサタケと言われていたタイプのようだが、最近は分類が判然としなくなったので、ひとまずはアミガサタケということにしておく。 この時季にしては例年よりきのこの種類が少なく、小さなきのこすらなかなか見つけられない。どうも寂しいスタートだが、どこかで好転してくれるのだろうか。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 4月25日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県大磯町 |
神奈川県南部では昨日の夕方からまとまった雨が降ったらしく、夜には止んでいたがあちこちに水溜りができていた。そして今朝は風もなく快晴で、気温はやや低いものの、きのこ探しには大いに期待できるものがあった。 ところが湘南平からスタートして、行けども行けどもまったくきのこが見つからず、今日も空振りに終わるのかと思い始めたとき、ようやく倒木から生える1本のきのこを発見。ウラベニガサ科だとすぐに分かったが、種名がはっきりしない。カサの表面に見える暗褐色のカスリ模様が特徴的で、これがフチドリベニヒダタケではないかと思う。疑問が残るので細かく標本撮影しておいた。 山道の真ん中、段差になったところにムジナタケの幼菌を見つけた。いつも思うが成菌に比べて幼菌の姿がきれいで、ついカメラを向けたくなる。ムジナタケはなぜか人に踏まれそうな場所を選んで生えているような気がする。 午後になって少し冷たい風が吹き始めた。地獄沢へ向かう途中、裸地の斜面にカサの反り返った中型のきのこを見つけた。見たところヌメリガサ科のきのこらしいのだが、触ってみても黒変しないのでアカヤマタケではない。カサにヌメリがはっきりあり、カサの中央が尖っているわけでもないので、ヒイロガサに近いと思うが柄が白過ぎるのが気になる。もう少し前ならもっとはっきり分かっただろう。 地獄沢では大きな倒木に立派なアミヒラタケが生えていた。とても肉厚で柔軟ないい状態のものだった。 前半は惨たんの内容だったが、終わってみれば何とか絵になるものも撮れたマズマズの一日だった。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 4月24日(土) 芝公園 東京都港区 |
日が長くなってきたので土曜出勤日の今日、久しぶりに芝公園を覗いてみた。ところが昼ごろまでの好天が午後になって曇り始め、夕方はかなり暗くなってしまった。仕方なく、ウッドチップを敷き詰めた所だけを大急ぎで探した。 すぐにやや乾燥気味の小さなきのこを見つけた。色や形からツバナシフミヅキタケであることは分かったが、以前ここで見たものとはずいぶん大きさが違う。水不足のせいなのか、付近を探しても5センチにもならない貧弱なものしか生えてなかった。 遊歩道を隔てたもう一方の広場を探すと、一転して大きなツバナシフミヅキタケの群生が転々と散らばって生えている。残念ながら少し古くなっていて被写体には向かないものが多かったが、ある1本のクスノキの周囲だけ、とても瑞々しい元気な群生が環を描いて生えていた。 全体に明るい褐色で目立った模様や鱗片などもなく、なんとも捉えようのない特徴の乏しいきのこだが、逆にそれが本種の特徴と言えるかも知れない。 昨日までの真夏のような暑さから、一気に冬へ逆戻りになってしまった。 |
 |
 |
||
| 2004年 4月18日(日) 伊豆稲取→高麗山 静岡県・神奈川県 |
「国家公務員共済組合連合会(KKR)」という長い名前の会が、全国に48の一般客も利用できる宿泊施設を運営しているが、その会できのこに関連したイベントが企画され、資料と演出を兼ねて写真を提供することになった。今日その案内会場となる「KKR稲取」へ写真を届けて掲示コーナーに展示した。 ついでに伊豆高原のあたりを探索してみたが、気温が高く乾燥している状態だったので、気になっていることを確認するため高麗山へ戻った。 10日(土)に見つけたチャワンタケをアネモネタマチャワンタケとして掲載したが、他のいくつかのHPを見るとこの時季キツネノワンというのが方々で出ている。図鑑を見ても名前が出てこないきのこだが、クワの樹下に菌核を作って生えるらしいので、高麗山のものがどっちなのか気になっていた。結論から言えばキツネノワンの方だったようだ。すぐ横にクワの木があり大きく枝を伸ばしたその真下に群生していたわけだ。今日はすでに少なくなっていた。外見的に違いが見られないが、何か明確な同定ポイントがあるのだろうか?もし、クワの樹下にアネモネやニリンソウがあれば・・・?などと、考えてしまった。 帰路、1本のウメの大木を見つけて、菌友から今朝「もう出ている」と情報をもらっていたのでチェックしてみると、形のいいハルシメジがたくさん生えていた。本種としては中型だが、均整の取れたきれいなものだった。いよいよシーズン到来だ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 4月17日(土) 伊豆・一碧湖 静岡県伊東市 |
湖畔のサクラ目当ての観光客ももういなくなっただろうと思い、伊豆半島の一碧湖へ行ってみた。朝から気温がぐんぐん上がり、7月中旬並みの「夏日」となったらしい。箱根や周辺の山々はモヤがかかって霞んでいた。 そこそこ大きなきのこが出ていそうな気候になってきたので、目を「きのこモード」に切り替えてくまなく探し始めた。・・・ところが、まったくきのこが見つからない。湿った土の斜面に小さなものくらいは生えていそうなものだが、どんなに目を凝らしても見つからない。 やっとカメラを向ける気になったものは、きのこではなく、ウラシマソウの花で日向ぼっこ中のニホンアマガエル。 今日はもうこれだけしか撮影できないかも知れないと、半ば諦めかけていたとき、ようやく小さなアミガサタケを発見。付近にはもう少し大き目の1個がタチツボスミレと並んで生えていた。 俄然、きのこ目は「アミガサタケモード」になって、さらに大きな1本を発見。ところがよく見ると網の窪んだ所より稜線部分の方が色が黒い。これはトガリアミガサタケのようだ。 完璧な空振りに終わるかと思ったが、何とか季節のきのこを撮ることができた。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 4月11日(日) 八菅山・中津川 神奈川県愛川町 |
今日は「きのこ探して・・・」ではなく、友人たちと川原でデイキャンプの日だったのだが、食べられる野草などを探し歩いていると、ついきのこはないかと思ってしまう。 で、今日の写真は同行者が見つけてくれた、形のいいアミヒラタケの1種のみ。鱗片がカサに密着しているので本種でよさそうだ。木に生えたタマチョレイタケがたいへんよく似ているが、タマチョレイタケは鱗片があまり黒っぽくならないことや、カサの中央付近では鱗片がささくれ立つことで見分けられる。 新緑ののどかな田園風景を眺めながら、野趣味豊かな料理を満喫する。時おり、強風に悩まされたこともあったが、大満足の一日だった。 |
 |
| 2004年 4月10日(土) 地獄沢(高麗山) 神奈川県大磯町 |
この時期は何かと野暮用が多いもので、何とか予定を1日に集中させたりするものだから、今日は午後の2時間だけ高麗山の地獄沢を探索することができた。 やはり最も気になるのが入り口の斜面に出るヒメコンイロイッポンシメジ近縁種だ。わずかに1箇所だけ、5本ほど束生していた。斜面の上に1本だけスギがあってその付近にだけ生えるようだ。 エゴノキだと思われる倒木から1本だけエノキタケが生えていた。なぜか高麗山ではあまりエノキタケを見かけない。もっと群生してくれると、撮影と採取ともに楽しめるのだが、1本では味噌汁の具にもならない。 散策路に沿って小さなチャワンタケが群生しているのを見つけた。近くにツバキはないので、どうやら ※前項4/4の新治での「ヒトヨタケ科」について、HP「きのこ屋」の高橋さんから「オオカバイロヒトヨタケ」ではないかとメールをいただいた。W女史による検鏡結果も楕円形の厚膜胞子などで、それを裏付けるものだった。高橋さん、ありがとうございました。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 4月 4日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
昨日「汗ばむ」と書いたばかりだと言うのに、いったい今日の寒さは何だったのだろう。風が強い訳でもないのに体の芯まで痛くなるような寒さで、完全に冬へ逆戻りになってしまった。 いつも通り駐車場の付近を探すと、小さなヒトヨタケ科のきのこが出ていた。一つはカサを開いていて、見た感じではコツブヒメヒガサヒトヨタケのように思えた。コツブ・・・を付けるべきかどうかは検鏡しなければ分からないが、高さが5センチくらいで単生していたことからそう思った。 ところがそのすぐ近くにカサを開いてないヒトヨタケ科のきのこがあり、同種か別種かが分からない。カサの肉に厚みがあるので別種にも見えるが、ヒトヨタケ科のこのタイプは幼菌と成菌でずいぶん印象が変わるので何とも言えない。W女史に検鏡してもらうことになったので、結果が楽しみだ。 去年あんなに見たフクロシトネタケを今年はほとんど見なくなった。去年が大発生だったのだろう。去年と同じ場所に1個だけ生えていた。中心部の凹凸や外縁の褐色の粒点など、特徴は顕著だった。 草むらにたった1本だけカサを広げているきのこを見つけた。近くでよく観察するとこれもまたヒトヨタケの仲間だ。カサの表面に細かな鱗片が付いていいるのでどうやらキララタケでよさそうだ。 せっかくサクラが満開になってちょうど見ごろだと言うのに、午後からはミゾレ混じりの冷たい雨が降ってきた。この頃の激しすぎる寒暖の差は、きのこの発生にどう影響するのだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 4月 3日(土) 愛名緑地 神奈川県厚木市 |
気象用語というのだろうか天気予報でよく使われる、季節を表す常套句のような言葉がある。それで言えば今日の天気は「春めいて」を通り過ぎて「汗ばむ初夏の陽気」というところだろう。 このところの雨に気の早いきのこが出ているのでは・・・と、初めての緑地を歩いてみた。ところがハラタケ目はもちろん、堅いきのこでも新鮮なものは見つからなかった。 落ち枝に並んで生えていたのはヌルデタケで、撮影中に通りかかった初老のご夫妻が興味深く話しかけてくれた。「団子鼻にそっくり」と、ひとしきり笑う。 立ち枯れた木の根元に、ずいぶんバランスよく生えたサルノコシカケを見つけた。もうかなり乾燥してひび割れているが、きれいな生え方のコフキサルノコシカケだ。 その後はいくら歩いても、目に付くのは春の草花ばかりで、やはり新鮮なものはなんでも美しい・・・と、カメラを向けてしまう。「きのこ不作」だったここ数年より寂しい内容で、この先が思いやられるが梅雨までは仕方がないのだろうか。 |
 |
 |
||
 |
