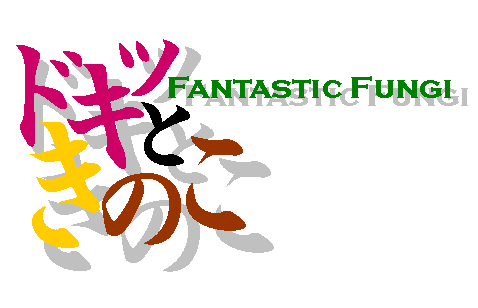 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2004年 5月 |
| 2004 | 2003年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2005年へ |
| 2004年 5月30日(日) 湘南平 神奈川県大磯町 |
今日は「神奈川キノコの会」の平成16年度総会が平塚市博物館で行われるので、開始前のわずかな時間だけ先日の湘南平へ再度行ってみた。 前回でイロガワリの幼菌をいくつか見つけていたので、成菌に出会えるものと確信していたが、なぜか1本も見つけることができなかった。 相変わらずイヌシデの樹下にヒロハシデチチタケが生えていて、先日も種名が分からなかったベニタケ属とツーショットというシーンもあった。このベニタケ属はカサの色に変化があって別種なのかも知れないが、成菌のヒダがクリーム色になる特徴が共通しているので同種ではないかと思う。カサに強い粘性があること、味が温和であること、カサの表皮が剥がれやすいことなど、いくつも特徴が分かっても図鑑の絵合わせだけでは同定し切れない。 今年初めてのイグチを見つけた。カサの表面が細かくひび割れて管孔面が黄色い。管孔を触るとゆっくり青くなる。ここまでの特徴ではコウジタケとキッコウアワタケが考えられたが、コウジタケの名前の由来である特有の甘いにおいが全くない。従ってキッコウアワタケでいいのだろうと思う。 もう、撮影中に汗が流れて目に入るような季節になってきた。撮影はハードになるがきのこの種類が増えてくるのは楽しいものだ。今年は期待して良さそうな予感がするのだが・・・。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 5月29日(土) 芝公園 東京都港区 |
この公園も、月1回の土曜出勤の日に訪れるようになって、まるで定点観察の場所のようになった。しかし、園内はクスノキの大木が多いため、いつも行くウッドチップの一帯以外はほとんどきのこが見られない。 ウッドチップには雨の後にはたくさんのきのこが出るが、少し乾くとパッタリと沈黙してしまう。今日もほとんど干からびて朽ちたきのこばかりで、ようやく見つけたのはかなり乾燥気味のツバナシフミヅキタケの1本だけだった。 切り株の周囲に何か白い硬質菌が密生していた。どことなく不気味さを感じて「見なかったことに・・・」と思ったが、よく見るとまだ新鮮な状態だったのでひとまず撮影。採取すると少ししなる程度の強靭なカサで、表面に特徴的なシワがある。管孔面を見るときれいに揃った細かな管孔になっている。これは紛れもないクジラタケだ。管孔面も撮影しておいた。 さらに探索すると、どうやらカラスの縄張りに踏み込んでしまったらしく、低い枝の上からしきりに威嚇の叫びを発している。ついには頭をかすめるように飛んで来るようになったので、一人で多勢を敵に回したくなかったので退散してきた。 |
 |
 |
||
| 2004年 5月23日(日) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
また少し気温が下がってしまったとは言え、2ヶ月ぶりのこの公園にはかなり違う種類が出ているに違いない。雨の量から考えても尾根筋や斜面でも期待が持てそうだった。 ヤマザクラの倒木がいくつにも折れて、それぞれの端から明褐色のヒラタケ型きのこが生えていた。大きさがまちまちで大きくても幅数センチまで。ヒダが鋸歯状になっているのが確認できたのでイタチナミハタケのようだ。どれも新鮮な状態だったのでヒダの様子なども撮影しておいた。 今日、最も目に付いたきのこはダイダイガサだった。遠くからでも目に飛び込んでくる鮮やかなオレンジ色だが、いくつかは別種かと思うほど白いものもある。よく見てみると雨でカサの鱗片が落ちてしまっている。もう何枚も撮ったから・・・と思ってもついレンズを向けたくなるいい被写体だ。 地面に淡い褐色の中型菌が株状になって生えていた。しっかりした柄やカサ中央の色からナラタケだということはすぐに分かった。どうやら地中の浅いところの木の根から生えているらしい。付近の木の根周りを探してみたが見つからず、これではまるで地面から生えるきのこに思えてしまう。 黄色っぽい色の普通のイタチタケを数箇所で見かけたが、明るいグレーのハイイロイタチタケも観察できた。いつも均整の取れたスタイルで、曲がった柄などに表情があって絵になる写真が撮れる。幼菌の姿もなかなか面白く、構図を変えてなんカットも撮ってしまう。 他にも名前の分からない小型菌が何種類もあって、撮影はするものの図鑑との絵合わせができずに、全く不明のままというのもある。特徴のハッキリしない小さなきのこはいつも苦労させられる。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 5月22日(土) 湘南平 神奈川県大磯町 |
台風2号の接近で昨日が雨で今日は好天という予報だったが、台風の速度がかなり速くなって昨日は午前中から晴れて、今日が雲の多い天気になってしまった。今にも雨が降りそうな空模様だったので、最も近いフィールド、高麗山・湘南平を歩くことにした。 フィールドアスレチックのある斜面にはイヌシデの木が多く、昨年同様ヒロハシデチチタケがたくさん生えていた。黒っぽい灰褐色のカサは今日のような曇天下ではたいへん見つけづらい。少し目が慣れてきてやっと、あちこちにたくさん生えていることが分かる。傷つけると白い乳液を出し、変色はしない。味はきわめて辛い。 生垣(ツツジ?)の根元に小さなきのこを発見。クヌギタケ属のきのこだと思うが地面から生えているようなので、クヌギタケそのものではなさそうだ。 もう1種、あちこちに生えていたきのこも、名前がよく分からない。ベニタケ属なのだがドクベニタケやチシオタケと違って肉がまったく辛くない。成菌の柄にはわずかに淡い色がある。ニシキタケとも色合いが違うようで、この色のベニタケ属にはいつも悩まされる。 とうとう雨が降りだして、短時間の探索だったが仕方なく切り上げた。そして自宅近くの駐車場まで帰ってきて車を入れようとしたら、なんと車を置いていたその場所にきのこが生えている。舗装された隙間から数本出ていたので降りて確認してみると、コンクリート下の木材から生えているアミスギタケだった。思わず車が背景に入るように撮影。物足りない内容にオマケをもらった感じだ。 踏まないように注意して車を停めて、本日の探索が終わった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 5月16日(日) びわの森 神奈川県平塚市 |
朝から天気が不安定で、時おり横殴りの大粒の雨が降る。わずかに止んでいる間を狙って、先日2年前の写真ファイルから再発見した新種「コガネハナガサ」の撮影ポイントへ、2匹目のどじょうを探しに行ってみた。 現地に着いてみると2年前の記憶はかなりあやふやで、ピンポイントに場所を特定することはできなかった。仕方なくやや広範囲に探ってみた。 超小型のホウライタケ属のきのこがあちこちにたくさん出ている。少し掘ってみるとすべてアオキの枝や葉から生えている。アオキオチバタケだ。ここまで小さいと薄暗い中ではほとんどピント合わせができない。しかも今日は風が強く長時間露光もできない。何とか妥協しながら撮った。 切り株の上にササクレ模様のカサが目立っていた。アミスギタケはサルノコシカケ科の仲間とは思えない、ごく普通のきのこの生え方をする。 斜面に褐色の端正な姿のきのこが生えていた。見た瞬間はイタチタケかと思ったが、ヒダを見ると真っ白でナヨタケ属ではない。ヒダが柄の上部に向かって深く窪むような形はクヌギタケの仲間に多い。埋もれ木などから生えたクヌギタケだろうと思ったが、よく見るとカサに条線が全くない。どうやらこれはコザラミノシメジのようだ。カサの色やスタイルに変異が多く、おまけにハッキリ目立つような特徴がないので、いつも消去法の同定で行き着くきのこだ。 もう1種、スギ林のはずれにホウライタケ属のきのこ、スジオチバタケが生えていた。カサの紫色の溝線がよく整ったきれいな状態だったが、これも風があっては撮影困難なきのこだ。途中で諦めてカサのクローズアップを標本撮影しておいた。幼菌は柄の色も紫を帯びていてきれいだ。 結局「コガネハナガサ」は発見できなかったが、6月に撮っているので来月もチェックしてみよう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 5月15日(土) 富士山南麓西臼塚 静岡県富士宮市 |
富士山をメインのフィールドにしているHP「遊々きのこ」によれば、南麓の西臼塚でそろそろきのこが出始めた様子なので探索に行ってみた。 まずは南側の広い駐車場からウラジロモミ(?)の続く散策路を歩くと、すぐにきれいな生え方をしている一群を見つけた。カサの独特の深い赤紫色と周縁へ向けて薄くなる色合いは、毒きのこのサクラタケだ。ありふれたきのこでも生え方が一味違うところが富士山ならではで、つい撮影枚数が増えてしまう。 同じ駐車場の草むらにはアミガサタケが1本だけ出ていた。黄色タイプで高さは6〜7センチ。富士山は今がちょうど春なのだろう、八重桜が見ごろだった。 道路北側の散策公園で倒れかかったブナの木に、真っ白いきのこが生えていた。ヌメリのあるカサの表面と特有の形のツバとで、ヌメリツバタケモドキだと分かった。同じ形でヌメリツバタケもあるが、富士山ではほとんど前者の場合が多く、ヒダを確認するとあまり顕著ではないが縮れているのが見えた。 2002年の6月末にここで初めてコガネヌメリタケを見つけて、その美しさに驚いたのだが、その後、何度か見る機会はあってもその時ほどのきれいなものには出会えなかった。「遊々きのこ」にはたくさん出ているように書かれていたので期待が膨らんだ。確かにいたるところに生えていて、かなり美しいものもあったのでたくさんの写真を撮ることができた。霧が出て空気が湿っていればきっと、もっときれいなシーンを撮ることができた筈でちょっと残念。 今日、ブナの倒木上にいくつも生えていた黒いカサのきのこが、どうにも名前が分からない。クロゲナラタケかと思ったが柄が細すぎる。カサの表面に短毛が密生して、ツバはなくヒダはカサとほぼ同色。図鑑で見つけられなかった。 日差しが強く汗ばむほどだが、さすがに空気が冷たく清々しい気分で探索ができた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 5月10日(月) 新種発見! 2002年6月のファイルから |
昨夜、何気なくいろんな「きのこ関連HP」を眺めていて、高橋春樹さんの「八重山諸島のきのこ」の新種が紹介されているページに行き当たった。興味深く見ていて「コガネハナガサ」という美しいきのこを見た瞬間、以前撮影して不明のままにしているものにそっくりだと思った。 時期がうろ覚えだったので1年分くらいを探してみると、あった!2002年6月16日に地元平塚市の「びわ青少年の家」で撮影した中で、「不明」と名づけてそのまま調べていないきのこだった。 キツネノハナガサにちょっと似ているが、黄色ではなくオレンジ色の微粉をつけているような感じで、根元にはまるでゴマ粒のような幼菌が密生している。 キシメジ科クヌギタケ属でありながら、成菌は一夜で萎れるらしい。再度見つけてぜひ標本を手に入れたいきのこだ。 |
 |
 |
||
| 2004年 5月 9日(日) 七沢自然保護センター 神奈川県厚木市 |
雨の予報だったのであまり広大ではない探索場所としてここを選んだが、駐車場に着いた頃から怪しい雲行きになってきた。手早く見つけて撮影だけを優先しようと探索開始。 せせらぎにかかった苔むした木橋に赤紫のきのこが束生していた。今度こそチシオタケだろうと少し傷つけて確認すると、赤い液がにじんできた。真冬の雪の中でも見られる通年生えるきのこだ。 撮影中にもう雨が降り出してしまった。うかつにも傘を積んで来なかったので、一旦車へ避難。しばらくして空が明るくなり、雨が止んだので探索再開。 地面から小型のきのこが生えていた。明るい褐色でカサが開いたものは周縁が裂けている。ツバはなくてヒダが暗灰褐色をしている。やや小型過ぎる気もするがこれはツバナシフミヅキタケではないかと思う。これと言った決め手に欠けるきのこなので同定が難しい。 そして再び撮影中に雨。しかも、とうとう本降りになってしまい、ついに探索を断念した。しかし、気温のあまり下がらない雨はきっといい結果を生むだろう。 |
 |
 |
||
| 2004年 5月 8日(土) 高麗山 神奈川県大磯町 |
まとまった雨が降った後にどうしても気になる場所は、やはりマイフィールドにしている高麗山だ。昨年の5月に高麗山でナラタケの群生を見ているので、今日も高来(タカク)神社から入って女坂を登った。 ところが今年はまったくナラタケが見つからない。わずかに倒れたタブノキの老木からそれらしき極小の幼菌が出ていたので、まだこれからなのかも知れない。一方、昨年同じ日に見たオオゴムタケはあちこちで見ることができたので、こちらは順調なスタートをしているようだ。 急な斜面の途中に不朽の進んだ倒木が横たわり、それに赤いきのこがたくさん生えていた。これも今日あちこちで見かけたヒイロベニヒダタケだ。どれも鮮やかな色で、こんな多数の群生は初めて見た。 山の北東部にある「けやきの広場」には名前の通り大きなケヤキがたくさんあるが、その大木の根元のウロにナヨタケ属と思われる数本が生えていた。イタチタケの仲間で、2001年5月に真鶴半島で見つけて検鏡していただいた結果タカネイタチタケと同定されたものにそっくりだ。名前は「高嶺」だが平地にも生えるきのこだと聞いた記憶がある。 同じ広場でこれもあまり見かけないきのこを見つけた。カサに黒褐色の繊維紋があり光沢がある。目立つ特徴は際立って白い、幅の狭いヒダだ。どうやらコザラミノシメジのようだ。胞子や細胞に分かりやすい特徴があるらしいが、顕微鏡を覗かないので分からない。柄の強靭さなどのいくつかの特徴も当てはまるのでこれでいいのだろう。 斜面に生えた薄紫色の小さなきのこを見つけて、たぶんチシオタケではないだろうかと思ったが、採取してよく見るとこれはなんとフウセンタケ科のきのこだ。カサも柄も薄紫色をしていて、くもの巣状のツバがはっきり見える。手持ちの図鑑にはどうやら当てはまるものはないようだ。少し大きめの1本はカサが褐色になっていたので、成長すればかなり印象が変わるのかも知れない。 一通り歩いて車に戻る途中、やや乾いた斜面にイッポンシメジ科のきのこが生えていた。見た瞬間ハルシメジだと思ったが周囲にウメもサクラもなく、よく分からないがバラ科の樹木はなさそうだ。撮影後に採取してみるとどれも柄が中空で弱々しく、どうやらクサウラベニタケだと思われる。まだ、ハルシメジも出ている時期だから混同しないように注意が必要だ。 ようやく地上に生えるきのこがいくつか出始めて、撮影も面白くなってきた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 5月 5日(水・祝) 八菅山(ハスゲヤマ) 神奈川県愛川町 |
ここは神奈川キノコの会でもよく勉強会を行う樹種の豊かな自然公園だが、ここにある八菅神社にもスダジイの巨木がたくさんある。カンゾウタケが生えると聞いたことがあったので行ってみた。 あいにく朝から雨が降り続き、空は明るいもののなかなか止んでくれない。駐車場でしばらく様子を覗うと、昼近くになってようやく傘が不要な程度になった。 スダジイを中心に探索を開始すると、さすがにこのきのこは遠くからでも見つけやすく、すぐにいくつも見つけることができた。ところがまだ時季が早すぎたようで、どれも数センチしかない小さなものばかり。それでも色の華やかさは魅力でついカメラを向けてしまう。 神社のはずれに種々の間伐材を積み上げたところがあって、マツの材から大きなマツオウジが1本生えていた。大きくカサを広げた柄の太いもので、カサの黄色が鮮やかだった。全く傷みのないしっかりしたものだったので味わってみることにした。かすかなマツタケ臭に松ヤニが混じったようなにおいだった。 すぐ近くの別の材からは小型の明褐色のきのこが3本生えていた。一見してナヨタケ属のように見えたのでキツネタケかムササビタケくらいに思って撮影しておいた。後で確認のつもりでヒダを見ると、なんと肉色をしていた。となるとこれはウラベニガサ科になる。カサの中央にしわがあってヒダの下縁が独特の弧を描いた丸みがある。どうやらヒメベニヒダタケのようだ。 今日でGWが終わったが、昨日今日の雨はこの次の週末に期待を持たせてくれそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 5月 3日(月・祝) 鷹取神社 神奈川県平塚市 |
神奈川県で「鷹取山」と言えば、厨子と横須賀の市境にある山だと思う人が多いかも知れないが、実は平塚市の西のはずれにも鷹取山がある。その昔、鷹匠が鷹を取ったという名前だから、神奈川に限らず全国各地にあるのだろう。 山頂に古刹「鷹取神社」がある。山上にある神社となれば当然、シイやタブなどの古木がたくさんあるはず。・・・と考えて、短時間だけ「きのこ探索」をしてみた。 狙い通り、タブの巨木が切り倒されて朽ちている。そしてその空洞になった内側などに、マユハキタケがたくさん生えていた。どれも数ミリから1センチまでの小さなものが多いが、その数はまるでゴマ粒を降りかけたようなおびただしいものだった。 そして、これも狙い通り大きなスダジイが何本も立っている。当然この時季はスダジイを見つけると、その根回りを一周して真っ赤なきのこカンゾウタケを探す。まだ少し早いようで、見つけたのは直径5〜6センチの幼菌と、さらに小さな赤い点だった。 明日にかけてまとまった雨が降るような予報だったので、この連休は最終日に期待できるかも知れない。 |
 |
 |
||
| 2004年 5月 2日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
昨日とは打って変わって肌寒い一日になり、この春の激しい気候変動に体調維持が難しい。本日の定点観察会は8人の参加者で、16個のきのこ目による探索に大いに期待が持てた。 道沿いの斜面にフジイロチャワンタケモドキが生えていて、今日は離れた場所でもいくつか見つかったので、ちょうど今が発生のいい時季なのだろう。少し大きくなると子嚢面の色が薄くなってしまうが、枯れ葉に埋もれた幼菌は鮮やかな紫色をしていた。 参加者の内2人は最近キツネノワンとキツネノヤリタケを何度も見つけているので、今日はキツネノヤリタケが撮影できると期待していた。ここにはヤマグワがたくさんあるので確率は高い。一人がキツネノワンを見つけたのでその付近を数人がかりで念入りに捜索。そしてついに念願のキツネノヤリタケが見つかった。なるほど聞いていた通り、バックから浮き立たせてくっきり撮影するのが難しいきのこだ。生えている場所が薄暗い草むらなので、三脚もセッティングしにくい。むしろカメラを地面に置いて撮る方がいいアングルになった。 この森の湿地にはミズベノニセズキンタケに近縁のミズタマタケ(仮称)が生えるところがあるが、今日は別の流水地でたくさん発生しているのが見つかった。落ち枝に生えることが多いが、ここではササの茎に生えているものがいくつもあった。ササにはきのこが生えにくいらしく、珍しい事例とのことだった。 例年いま頃はあちこちでアミスギタケの群生が見られるはずなのだが、今年は発生が遅いのか少ないのか、いつもより数が少ない。それでもやはりこのきのこを見ると、絵になる生え方をしているのでいい被写体になる。 この所の激しい気候の変動は、はたしてきのこの発生にどう影響するのだろう。例年見られないような興味深いものが多く出てくれることに期待したい。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 5月 1日(土) 富士山東麓・南麓 山梨県・静岡県 |
春に生えるきのこシャグマアミガサタケをまだ見たことがないので、もうそろそろ出ている頃かと富士山まで探しに行った。須走口から入る「ふじあざみライン」のふもとに広がる針葉樹林の中を、かなりじっくりと探索したが見つからなかった。・・・というより、他のきのこもまったく出ていない状態だった。 倒木や立ち枯れた木にツリガネタケがいっぱい生えていた。独特の姿とまばらな生え方でとても分かりやすいきのこだ。 雪解け水を期待して標高の高いところへも行ってみたが、4合目のカラマツ林へ行ってもカラカラに乾いている。急きょ南麓の方が良さそうな気がして、午後は西臼塚付近へ行ってみた。ところがここでもきのこはほとんど見つからなかった。 倒木に変な形の白っぽいきのこを見つけて、ヒダを見ると著しい縮れ方をしている。ヌメリツバタケモドキのようだ。よく見るとヒダに白線の模様が見える。 やっと新鮮なきのこを発見。もうぼろぼろに崩れた倒木から数本のウラベニガサが生えていた。珍しい訳ではないが、なぜか今日はこれの撮影に力が入った。 帰路の混雑を避けたい理由もあるが、これ以上探しても時間の無駄に思えて、さっさと引き上げてきた。 |
 |
 |
||
 |