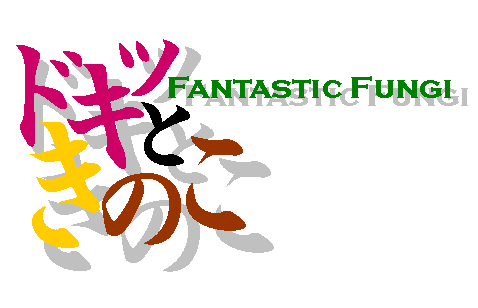 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2004年 6月 |
| 2004 | 2003年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2005年へ |
| 2004年 6月27日(日) 日光 栃木県日光市 |
HP「きのこ雑記」(浅井さん)や「きのこ屋」(高橋さん)で毎年のように美しいタモギタケやホシアンズタケの写真が紹介され、南関東では見ることができないきのこなのでぜひ一度撮影したいと思っていた。場所と観察時期のアドバイスをいただくことができたので行ってきた。 日光の2箇所を探索したが、最初のポイントではいきなりきれいなマスタケを見つけることができた。広葉樹に生える黄色いタイプをアイカワタケとして区別しているようだが、これは樹種は不明だったが鮮やかなサーモンピンクでマスタケということになる。 苔むした地面から見慣れないイグチが1本だけ生えていた。柄を見ると白っぽい地に黒い粒点が一面に付いている。ヤマイグチかと思ったがよく見るとカサ表面の全面に鱗片が付いている。すぐに図鑑を確認したがヤマイグチ属ではその特徴のものがなかったので種名は分からない。 もう1種きれいな状態を撮ることができたのはクサハツ。有毒で特有の不快臭があるのでこの名前だが、このように新鮮なものはあまり強いにおいはしないようだ。 もう1箇所のポイントへ移動してすぐに探索を開始。まず最初に見つけたのは明るいオレンジ色のベニタケ科のきのこ。カサにややヌメリがありカラマツ林に出ていたので、カラマツチチタケだろうと思いヒダに傷をつけてみた。ところが乳液が白ではなく透明で変色しない。少し甘い果物のにおいはしたが種名は分からなくなってしまった。 すっかり樹皮が剥げてしまって樹種が分からない倒木に、小さなオレンジ色の球を見つけた。今日よく見かけた変形菌のタマホコリかと思ったが、それにしては大きすぎて形もいびつだ。近づいてよく見ると下側にかすかなシワ状の筋があり、柄には濃いオレンジ色の水滴が付いている。初めて見るホシアンズタケだ。 ハルニレやヤチダモが多い林に差し掛かると、遠目からもはっきり分かる鮮やかなレモンイエローの塊りがいくつも並んでいる。今回の第一目標きのこ、タモギタケだ。大きくカサを広げたものから米粒大の幼菌まで、とても新鮮で色の鮮やかなものばかり。思わず夢中になって構図を変え絞りを変え、一気に30カットほど撮影。肉眼で見る独特の黄色がなかなかデジカメで出てくれない。補正や日の光のさえぎり方を工夫してみて、何とか表現することができた。その場で確認できるデジカメならではの良さを本当にありがたいと思った。 助言いただいた両氏にも心から感謝したいと思った。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 6月26日(土) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
長かった「梅雨の中休み」がやっと終って、昨日は久しぶりにまとまった雨が降った。長雨と蒸し暑さがきのこ発生の好材料だから、朝から「泉の森公園」を歩いてきた。 反り返ったイグチがいくつもあって管孔の柔らかさからアワタケだろうと思い、付近を探してみると新鮮な一群が見つかった。カサにひび割れが見られないのでやはりアワタケでよさそうだ。管孔はゆっくり青変する。 マテバシイの林の中で葉っぱに埋もれたきのこを発見。慎重に葉やごみを取り除いていくと、褐色のきれいなきのこの群れが姿を現した。アセタケの仲間らしいことはすぐに分かったが、種名が浮かんでこない。撮影後に採取してみると根元にはっきり膨らみがある。カブラアセタケだと思うがどことなく様子が違うので自信はない。 もう1種、やや大きめのアセタケを見つけた。カサの中央が極端に突出している。カサの表面をよく見ると繊維状の表皮が放射状に裂けている。柄が細すぎるのが気になるが、これはオオキヌハダトマヤタケでいいのだろう。 気温が上がると一気に種類が多くなるのがテングタケの仲間で、まさに「夏のきのこ」の代表と言えるだろう。最初に高さが10センチくらいの白いテングタケ科を見つけた。カサは薄いながらも灰色が見え、周囲にははっきり条線がある。ツルタケだろうと思ったら、柄のやや上のほうにツバがついている。となるとこれはツルタケダマシだ。ヒダにピンク色が見えないのでタマゴテングタケモドキではない。 もっとカサの色が黒っぽい幼菌を見つけたが、この状態を一見しただけでは数種類の可能性があるので、撮影後は必ず細かな部分をチェックしておかないと後で写真を見ても分からなくなってしまう。・・・で、これはツバが全くなくヒダが真っ白だったのでツルタケそのものということになる。 最後はもう少し大型で柄にも灰色の段だら模様が見える。これもツバが全くないのでこちらはオオツルタケだろう。図鑑にはヒダに縁取りが見られるという記述があるが、これには確認できなかった。「しばしば」という表現なので無い場合もあるのだろう。 暖かい雨が降ると里山は一気に賑やかになる。明日は遠方へ出かける予定なのでHPの更新はたぶん28日(月)の夜以降になるだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 6月20日(日) 高麗山 神奈川県大磯町 |
まったく雨が降ってないのだから、遠くまで出かけても時間を無駄にするだけだろうと考えた。そこでマイフィールドにしている高麗山を歩くことにした。 1ヶ月前にイロガワリの幼菌を見つけた斜面で少し大きくなったものを見つけた。やや乾燥気味で変色のスピードもなんとなくのろいが、どの部分を触っても濃い紺色に変色するので分かりやすいきのこだ。 自称「テングタケ通り」へ行くと、去年(2003.6.14)と同じ場所に淡い紫色のベニタケが1本だけ生えていた。ウスムラサキハツではないかと思ったきのこだが、図鑑で再度特徴を照らし合わせてみると、違う種類である可能性が大きいことが分かった。ヒダが極めて密でカサの周縁は溝線ではなく、粒点状にひび割れている。私の持つ図鑑では符合するものは発見できなかった。 ここは2,3日前に雨が降ったらしく、地面が湿っている。そしてようやく「テングタケ通り」にテングタケ科が出始めた。カサの中央やツバに淡いピンク色のあるドクツルタケの仲間、アケボノドクツルタケだ。中心だけがわずかに薄いピンクのものや、遠目でもはっきりピンク色の環紋を持つものなどさまざまある。 この通りが賑やかになると撮影が楽しく、そして忙しくなる。今年こそ数種類のテングタケ科が同時に生える状態になって欲しいと思う。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2004年 6月19日(土) 芝公園 東京都港区 |
恒例の芝公園定点観察・・・と言っても時間は日没までの30分ほどしかなく、おまけに今週はただの一滴も雨が降らなかった。「梅雨の中休み」だそうだが、普段より湿度が低いという過ごしやすい梅雨だ。 当然のことに、いつものウッドチップは乾燥してふかふか状態。それでも諦めずに目を凝らして探すと、かろうじて撮影に耐える小型のヒトヨタケ属を見付けた。位置から推測して毎年ここ生えるクズヒトヨタケかと思ったが、色や肉質が違うようだ。付近に成菌が見当たらないのでよく分からない。やっと老菌を見付けたがこれでもよく分からない。 他には何もないだろうと歩いていたら、黄色い塊りが見えた。これは変形菌の仲間でススホコリという種類だろう。時間をかけて観察するとどんどん形や色を変えて行くので変形菌と呼ばれるが、分類学的にはあまりきのこに近くないらしい。 中休みもほどほどにしてもらって、そろそろ本格的な「きのこシーズン」到来と願いたいものだ。 |
 |
 |
||
| 2004年 6月13日(日) 木もれびの森 神奈川県相模原市 (神奈川キノコの会) |
今年第1回目の「神奈川キノコの会・野外勉強会」が開催された。この森ではもう何度も開催されているが、広大な面積であることとまったくの平坦地であるために、方向や現在地が不明になることがしばしば。方向音痴の私はあまり広範囲に歩けない。 到着後すぐに見つかったのは切り株に密生しているイヌセンボンタケだ。極小のカサがおびただしい数で生えている。幼菌は真っ白だが成長すると灰色になり一夜で真っ黒になって朽ちてしまう。クローズアップで見るとなかなかきれいなきのこだが、やはりこの生え方を不気味と感じる人は多いようだ。 今日はかなり多くのベニタケ科が見つかったが、中でもあちこちで大きなカサを広げていたのはクロハツだった。ヒダが粗く傷をつけるとすぐに赤く変色して、その後ゆっくり黒く変わっていく。これは無毒で可食だが、黒くならないままだと猛毒のニセクロハツだから注意が必要だ。 いくつもの落ち枝に白から灰色のカサの小型のきのこが出ていた。数本ずつ束生するような生え方で、柄にはっきりとジェル状のヌメリが見える。雨が降ったせいてカサも粘性があるように見えたのでハイイロナメアシタケとも思えたが、乾いたカサを観察すると粘性がないのでヌナワタケということになる。ヌナワとはジュンサイの別名でうまいネーミングだと思う。 アカマツが並ぶ付近を探索していると、盛り上がった松葉のすき間にわずかな白いカサが見えた。様子が面白いのでまずはそのまま撮影。松葉を除いてから再度撮っていると、ヒダの色が真っ白ではなくわずかに青緑色を帯びていることが分かった。デジカメでは色が分かりにくいのか、撮影の腕が悪いのか、写真ではその微妙な色合いが表現できないが、肉眼ではこのアイバシロハツのヒダの色が分かる。 ずいぶん多くの種類が出る季節になって来たが、最近特に鑑定の段階で種名を断定されないことが多くなり、肉眼的な見分け方に頼っている者としては困った状況になりつつある。新種が公式に発表されるのは興味深いことだが、その前段階の仮称だらけにはちょっと辟易するものを感じる。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 6月12日(土) 富士山北麓 山梨県富士吉田市 |
今週は梅雨らしく雨がよく降り、週の後半には台風4号までやって来てたっぷりの雨をもたらしてくれた。気温も高くなって蒸し暑い日が続いたので、そろそろテングタケ科の顔も見たいものだと、富士山まで遠征してみた。 富士五湖道路の富士吉田IC料金所にウッドチップを敷き詰めた一角があって、昨年テングタケやサケツバタケなど数種類が生えていたのでチェックしてみた。まだ少し時期が早いのかテングタケはなかったが、大きなサケツバタケが生えていた。カサが大きく開いたものはすでに雨に打たれて見る影もないが、これから開くしっかりしたものが数本あった。名前の通りカギ爪状の裂けたようなツバがあるのでとても分かりやすいきのこだ。 カラマツの多い林の中ではいくつものヒロヒダタケを見ることができた。カサが反り返って真っ白いヒダが目立つので見つけやすいが、反り返る前はカサの表面が黒いカスリ模様なので、逆にとても見つけづらい。アメリカで中毒例があるらしく毒きのこという扱いになっているが、以前は食用にされていたようだ。 溶岩樹海の中ではずいぶんたくさんのベニヤマタケを見ることができた。血のような赤い色から明るいオレンジ色まで変化に富んでいるが、幼菌のころの深い紅色はとても印象的だ。これが目に付きだすとあまりの派手さに他のきのこが見えなくなってしまう。 散策路わきに地味な色のきのこが並んでいた。1本採取してヒダを見ると深い紫色をしている。これはウラムラサキに違いないが、普段見かけるのはもっと小さいものが多い。富士山では多くの種類が大型になると聞いたことがあるが、カサの直径が4センチ以上もあるウラムラサキは初めて見た。 モリノカレバタケが群生していたのでそれを撮影していると、すぐ近くに小型の赤いきのこが生えている。2002年11月に飯山観音で撮ったコウバイタケ近縁種としたものによく似ているが、ピンク色が強かったのに対して今回のものはオレンジ色が強い。カサだけを見るとベニカノアシタケに近いのだが、柄にまったく色がないので、よりコウバイタケに近いように思う。超小型のクヌギタケ属には本当にきれいな種類が多い。 夕方からは雲行きが怪しくなってきたので早めに切り上げた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 6月 6日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
昨日とは打って変わって朝から雨。いよいよ梅雨に入ったような降り方で一日中降り続いた。しかし、こんな天候でも「定点観察会」は何事もないかのように敢行され、みんなレインギアや傘を持ってのきのこ探しが始まる。 散策路の階段下に束生しているきのこを発見。どことなくナラタケモドキのような雰囲気があるが、カサが平滑で条線がある。ヒダがカサと同じ色で、ルーペで見ると黒褐色の胞子が出ているようだ。フウセンタケ科ケコガサタケ属になりそうだが種名は分からない。 今年初めてのテングタケ科はタマゴテングタケモドキだった。乾燥のせいか柄に強いササクレがあるが、ヒダを見ると日に透けてはっきりピンク色が見える。通称で呼ばれる「アカハテングタケ」の方が分かりやすいので、つい標準和名を忘れてしまう。 腐朽の進んだ倒木からきれいな黄色いきのこが生えていた。カサにハッキリ条線が見えるのでウラベニガサ科のベニヒダタケだろう。横に幼菌が2個並んでいたがずいぶん色が違うし、カサに条線が見られない。幼菌だけで同定をするのはむずかしいと思った。 麻のズタ袋を積み上げた所から、柄がわずかに黄色い幼菌が生えていた。カサを良く見るとヌメリが強くてシワ状のくぼみが並んでいる。今まで芝公園のウッドチップでしか見たことのないキオキナタケだ。こういう環境から生えるきのこなので里山などではほとんど見ることのないきのこだ。この森でも観察開始以来初めての記録となった。 夜になってようやく雨が止み、星空が見え隠れした。次の週末はきっと多種多様なきのこの発生が見られるだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2004年 6月 5日(土) びわの森・地獄沢 神奈川県平塚市・大磯町 |
朝出発してひたすら「道志みち」へ向かった。ところが30分も走ったところでもう車が多くなり始め、カーナビ嬢による到着予想は昼を過ぎることになった。一気に気力が萎えてUターン。付近の森を探索すことにした。 雨が少ない時でも何らかの興味深いものが見つかることが多い2カ所を歩いてみた。まずは平塚市の「びわ青少年の家」。探索できる範囲は広いほうではないが、きのこが好む地質や環境でもあるのか発生の多い所だ。 すぐに見つけたのは黄色っぽいカサと太い柄が特徴のキショウゲンジ。柄の上部が白く、しっかりしたツバには条線がはっきり見える。幼菌もいくつかあったのでしばらく見ることができそうだ。 昨年、ここで見つけて名前が分からず、城川先生に教えていただいたシュイロコナチャワンタケ(仮称)が今年も出ていた。まだ幼菌でどれも1センチまでの小さなものだが、その鮮やかなオレンジ色は目を引く。 もう1カ所は高麗山の「地獄沢」。いくつもの沢沿いに倒木が積み重なっているので、こまめに探せばいい状態のきのこが見つかる確率の高いところだ。 案の定、沢に落ちた枝に小型ながら形のいいきのこが出ていた。横から見るとヒダが下へ膨らんだように丸く見える。これはヒメベニヒダタケだろう。このヒダの特徴は成長過程でははっきりしない場合もあるようで、付近で同じようなカサのきのこをいくつか見つけたが、ヒダの下縁が直線状になったものもあった。 同じく沢近くの倒木から、とてもスタイルのいいきのこが生えていた。ナヨタケ属のようだが、カサ一面の白い鱗片が美しいので同定は後回しにして撮影優先。背景に初夏の濃い緑が見えていい雰囲気の写真になった。カサの褐色が周囲の部分で薄くなっていることや柄に強いササクレがあることから、アシナガイタチタケだろうと判断した。図鑑で「幼菌のカサには繊維状の白色鱗片がある」ことを確認、間違いなさそうだ。 階段脇にやや太い倒木があっていつも何か生えているのだが、今日はカサの中央に乳首状の突起がある小型菌がいくつも出ていた。ケコガサタケ属の感じだが、これも図鑑で「乳首状突起」が確認できたのでヒメアジロガサモドキのようだ。たいへん分かりやすい特徴だが、ない場合のほうが多いようなので決め手になる特徴ではないようだ。 暑い一日だったのでかなり体力を消耗した。きのこ探しに限ってだけで言えば早く梅雨に入って、多種類の発生と新鮮な状態に期待したい。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |