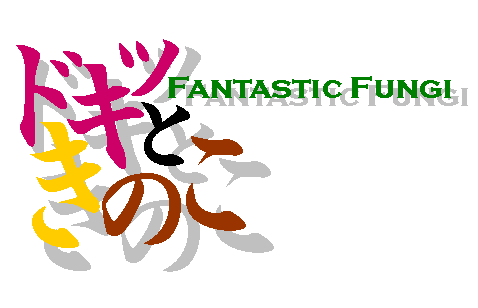 |
きのこ探して 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 3月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 3月31日(日) 大磯城山(ジョウヤマ)公園 神奈川県大磯町 |
今まで城跡でもあるのかと思っていたが、ジョウヤマと読む里山公園だった。金曜日にまるで集中豪雨のような雨が降り、昨日は快晴。気温も上がりいい条件が整った。・・・ハズだったが、狙いを間違えたのか、きのこが少ない。 やっと見つけたのは、また苦手な褐色の小さなきのこ。アセタケ属なのかナヨタケ属なのか、1本だけでよく分からない。カサの表面からはアシナガイタチタケのように思える。 苔の生えた湿った低地にヒトヨタケが出ていた。カサに厚みのあるシッカリしたタイプだ。まだ食べたことがなかったので、試すことにした。酒は飲まないので中毒の心配はないだろう。 樹種は分からないが広葉樹の枝に、鮮やかな橙色のきのこが生えていた。今まで見たことがないきのこで、図鑑でも見た記憶がない。表面をルーペで見るとミカンの皮のような粒点がある。裏面に管孔が見えないので子嚢菌のように思えるが、分からないので検鏡してもらうことにする。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 3月24日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県大磯町 |
2月から続いていた地獄沢入口の道路工事がようやく終わり、久しぶりに高麗山へ行ってみた。久しぶりといっても2月11日以来だが。 当HPのタイトル横に使っているキララタケの倒木は、高麗山訪問の際に必ずチェックしているが、今日、ようやくコキララタケを見ることができた。幼菌から成菌までそろって、ちょうどいい状態を撮影できた。*Galleryにも1点追加。 すぐ近くでアセタケ属のようなきのこを見つけたが、図鑑での判断でキヌハダニセトマヤタケが最も近い。アセタケの仲間は似たものが多く、外見でも顕微鏡でも同定が難しいと聞いたことがある。付近を探したが1本だけだった。 マユハキタケがいかに成長が遅いか、比較のために同じ子実体を撮ってみた。前回(2月11日)から約40日経過してこの状態。時間が止まっているようだ。 |
 |
 |
||
| 2002年 3月23日(土) 富士南麓・西臼塚 静岡県富士見市 |
5月並の陽気と言われては、平地だけでなく少し高い所でも何かが出ていそうな気がして、今年最初の富士山へ行くことにした。富士五湖付近は花見客が押し寄せるだろうと、静岡側の西臼塚へ向かった。 今日は少し気温が下がって、日が曇ると寒く感じたが、木々や草花の芽吹きはもう始まっていた。今日最も多く見られたのは、鮮やかなレンガ色の、その名もレンガタケ。カサの周囲の白い部分と管孔面の薄いクリーム色が特徴。コケの緑に良く映える色だ。 もう1種、落ち枝が青緑色になってしまう、ロクショウグサレキンをたくさん見かけたが、なかなか子実体を作っているのは見つからなかった。1本だけたくさんの子嚢盤をつけているのを見つけて撮影。最大で直径7ミリほどで、このきのことしては大きい方だった。 道路沿いにはまだ残雪も見られ、きのこを探すには少し早すぎたようだ。 |
 |
 |
||
| 2002年 3月21日(木・祝) 四季の森公園 神奈川県横浜市 |
サクラの開花が異常に早い今年、きっとアミガサタケも例年より早く出るのではないかと、6人のメンバーで四季の森公園を調べてみた。公園の方に尋ねると園内にはイチョウが無いとのことなので、前回のタイプのトガリアミガサタケは見つからないかと思った。 まず、サクラらしき落ち枝にヌルデタケをみつけた。少し乾燥しているが、シャワーヘッドのような形が面白い。管孔面を見てもシャワーヘッドそっくりだ。 しばらく探し歩くと、N氏が1本のトガリアミガサタケを見つけた。そしてその付近一帯にたくさん出ているのが、次々に見つかった。周囲の樹を見るとイチョウは無い。どうやらウワミズザクラを取り囲むように散生している。N氏によるとカツラやツバキの樹下でも見られたらしいので、イチョウだけではないことが分かった。 網の特徴や色、柄の表面のザラツキをよく見ると、どうやらトガリアミガサタケにほぼ間違いなさそうだ。他のアミガサタケ科のきのこは、やはりもう少し後なのだろう。 |
 |
 |
||
| 2002年 3月16日(土) こども自然公園 神奈川県横浜市 |
昨年4月にここでトガリアミガサタケの干からびたのがあったが、それをチェックに行ったN氏から「もう出ている」との情報をいただいた。金曜日の雨、気温の上昇は好材料だろうと、撮影に出かけてみた。 イチョウの樹の周辺を探すと、すぐに数本見つかった。トガリアミガサタケなのだろうが、頭部の色がオリーブ色で、あまりとがった形態でもないのでやや疑問がある。アミガサタケ属の分類は、まだまだ研究の余地があると聞いたことがある。こまめな撮影と採取が必要だろう。 別のイチョウのそばでは、頭部の色がより褐色のタイプのトガリアミガサタケを見つけた。前種とはどこか雰囲気が違うので、切断面も記録しておいた。頭部と柄の境目に段差が無く、スムーズにつながっている。 これから各地で見られるから、外見的な比較をしてみたい。 |
 |
 |
||
| 2002年 3月10日(日) 相模原市一帯 神奈川県相模原市 |
きのこの写真を撮るようになってから、毎年のようにアミガサタケのいい写真が撮りたいと思うのだが、どうもうまくめぐり会えない。先日、HP『きのこ雑記』でもうアミガサタケが出ていると知り、相模原市の森林公園を渡り歩いてみた。イチョウの樹下に良く出るようなので、目を皿にしてくまなく探したが見つからなかった。 サクラの古木になにやら堅いきのこがあった。良く見ると古いマンネンタケのようだ。コフキサルノコシカケと合体してしまっている。 いいきのこにはめぐり会えなかったが、相模原北公園ではもうカタクリが咲いていた。他にもセツブンソウやフクジュソウが美しく、何枚も写真を撮った。 HPのタイトルが『ドキッとはなこ』になってしまいそうだ。 |
 |
 |
||
| 2002年 3月3日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
昨日までに比べるとずい分気温が下がった。しかし、それでも平年以上ということらしいが、心理的にはより寒く感じてしまう。昨年から定点観察地として計画を進めてきた新治(ニイハル)市民の森へ、今回は人数も増えて総勢6人での観察となった。 雨が降ったとは言うものの、すでに地面は乾いていて、やはりまだハラタケ類のきのこは、ほとんど見ることができなかった。昨年4月に白ツバキから出たツバキキンカクチャワンタケを見つけたのはここだったが、今日は斑(フ)入りツバキの樹下で探してみた。そして、発見。これで、紅・白・斑入りとも撮影ができた。白と斑入りは園芸品種らしいので、どんなツバキからも生えるということなのだろう。 もう1種は典型的な姿のネンドタケモドキ。ネンドタケとはずい分印象が違うので種名に違和感を感じるが、幼菌のときは似ているのかもしれない。本種はほとんど背着していることが多く、なかなかカサを作らないようだ。 これからも月に一度くらいのペースで観察記録をすることになった。 |
 |
 |
||
| 2002年 3月2日(土) 21世紀の森 神奈川県南足柄市 |
雨とともに気温も上昇するこの時期は、自然の中のあらゆるものが動き始めるような気がして、出かけるのが楽しくなる。金太郎伝説の地、南足柄市の21世紀の森に行った。きれいな渓流沿いの道で早速「春の兆し」を見つけた。 駐車場わきの小山に登ってみると、コナラやミズナラの枝にタマキクラゲが群生していた。大きいものは互いにひしめき合っているが、融合せず1個ずつ採取することができる。中華スープなどの具に良さそうだが、デザートにもいいらしい。 相変わらずスエヒロタケが良く出ている。小さなものは毛むくじゃらで、アップで見ると防寒スタイルのようで暖かそうだ。 苔の間から出ている褐色のきのこを見つけた。根元を調べると、細い落ち枝から発生している。フウセンタケ科のケコガサタケ属のように思えるが、種名は分からない。カサの条線がハッキリしてヒダも褐色。糸くずのようなツバがある。このタイプのきのこは、どうもよく分からない。 |
 |
 |
||
 |