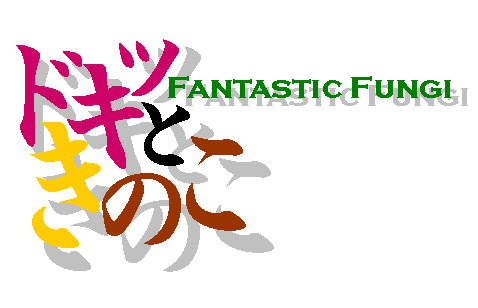 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 11月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 11月23日(土) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
俗に、「きのこ目」という1種の特殊能力があって、よくあんな遠くのきのこが見つけられるなぁとか、よくこんな小さなきのこが見えるなぁと感心する時がある。私自身はどちらかと言えば「遠目」の利くほうで、今日の定点観察でもハラタケ目のきのこは見つからないだろうという予測に反して、倒木のヒラタケを見つけることができた。 ところが私の「きのこ目」は、適度の間隔できのこを見つけてこそ精度が維持できるのであって、今日のようにその後は目ぼしいものが見つからないと、だんだん精度が落ちてきて、そのうちスイッチが切れてしまうようだ。その後はほとんど見つけることができなかった。 時どき雨がパラつく天気だったので、少しはマシになってくれることに期待しよう。 |
 |
| 2002年 11月17日(日) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
昨日の状態から尾根筋をいくら探してもムダだと分かったので、七沢森林公園の「沢のさんぽみち」を歩いてみた。狙い的中! まず、沢に倒れ掛かった木からヒラタケが群生していた。ほとんど白に近いタイプなので撮影に苦労するが、紅葉した落ち葉が季節感を演出してくれる。通りがかりのハイカーはモミジに見とれて、沢のヒラタケやそれを撮る私にも気づかない様子だ。 さらに進むと、大きなスギの根元にみごとな色をしたモエギタケが並んでいた。きのこ探しになれた目でもこの色は見逃しやすく、実はもう少しで幼菌を踏んでしまうところだった。丁寧にスギの枝や葉を払うと、きれいな姿をあらわした。いつ見ても不思議な色で、幼菌は柄まで緑色をしている。 道をはずれて沢をたどると、1本だけのコキララタケを見つけた。思い切って超アップで撮ってみた。柄の白さとカサの端の波型がとても美しい。 もう1種、個性的な形のきのこを発見。まさにさかずきの形になったクロサカズキシメジだ。高さは約3センチと小さいが、面白い被写体になってくれる。 この2日間でメインに狙っていたムラサキシメジは、結局見ることができなかったが、発生の少ない時期にしてはマズマズの写真が撮れた。もう少し適度な雨が降ってくれると嬉しいのだが。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 11月16日(土) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
少し暖かくなった日もあったりしたが、雨が降ってないのできのこは出てないだろう。ムラサキシメジかヒラタケくらいあればいいが・・・、と大和市の泉の森公園へ行ってみた。 園内を半分くらい歩いたところで、ようやく枯葉の間に小さな ※後日、ツチイチメガサだと分かった。 さらに残りの半分を歩いてやっと2カット目の写真が撮れた。きれいに並んだカイガラタケだ。カサ表面はビロードのように毛が密生し、まだ新鮮で柔らかさが残っていた。 今日はこれまでかと思ったが、まだ時間も早いので諦めずにさらに探すと、コナラらしい太い伐採材を積み上げた中に、まるで黄金のように輝いて見えるきのこを発見。そのカサの美しい鱗片はまぎれもなくヌメリスギタケモドキだ! やはり諦めないことが大切だと納得。満足して帰路についた。 |
 |
 |
||
 |
||
2002年 11月10日(日) 高麗山・七沢 神奈川県大磯町・厚木市 |
100Km以上も離れた石廊崎まで行かなくても、きのこは自分の足元にあった。まずは通いなれた高麗山の地獄沢で、毎年今ごろから12月にかけてヒラタケの出る倒木をチェック。まだ幼菌だが、例年通りかなりまとまって生えるようだ。すぐ近くの竹林の中の倒木にも少し開いたのが出ていた。 積み重なった倒木のそばでは 午後は探索地を七沢に移して、エノキタケがよく生えるポイントへ行ってみたが、チリメンタケやチャヒラタケばかりだった。小川沿いの土手にニガクリタケのきれいな群生を見つけて撮影。そばにコフキサルノコシカケの幼菌もあったのでバックに入れた。 笹薮の中に少しカサの赤いきのこを発見。今ごろ生えているのは思った通りチシオタケだった。ニガクリタケ同様、真冬になっても元気な姿が見られるのでいい被写体になってくれる。 春に「寒の戻り」があるのなら、秋にも「暖の戻り」というのがあってもいいと思うのだが・・・、このまま冬になってしまうのだろうか。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 11月 9日(土) 南伊豆・石廊崎 静岡県南伊豆町 |
仰せの通りこれはきのこではなくチョウである。種名をアサギマダラと言って、里山でも普通に見られる。 昨年の11月中旬、伊豆半島南端の石廊崎まで遠征してナラタケの群生やアイシメジ、ムレオオフウセンタケなどを見つけたので、二匹目のドジョウを狙った。ところが、どんなに目を凝らしても小型菌1本見つけられなかった。その挙句、私服の警察官に職務質問され、野鳥の密猟者と間違えられた。 そして、帰路はお定まりの渋滞。伊豆半島一周の不愉快なドライブとなってしまった。 |
 |
| 2002年 11月 4日(月・祝) 飯山観音 神奈川県厚木市 (神奈川キノコの会) |
「神奈川キノコの会」の今年最後の野外勉強会も好天に恵まれ、終わり良ければすべて・・・と言いたい所だが、残念ながらきのこの数は少なかった。 コナラの樹皮の間から赤いきのこが顔を出している。ルーペで見るとアラゲコベニチャワンタケの幼菌だった。周囲に長い毛が生えていて、どことなく動物的な雰囲気を持っているように思う。 きのこの多いシーズンならあまり目にとまらないのに、冬に近づくにつれてニガクリタケの元気な姿が目立つ。森の中がだんだん暗くなり、色彩もモノトーンになってくるので、余計にこの鮮やかな黄色が目を引くのだろう。 今日、最もきれいだったきのこはこのクヌギタケ属。ベニカノアシタケだと思うがカサの色に黄色味がなく、柄に全く色がない。かと言ってコウバイタケのカサの色とも違う。後の鑑定会ではクヌギタケ属までしか決まらなかった。きれいな色なので「Gallery」に入れることにする。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 11月 3日(日) 寺家(ジケ)ふるさと村 神奈川県横浜市 |
朝から雲ひとつない秋晴れで、日差しが暖かく過ごしやすい日だった。日ごろのきのこ仲間でアウトドアクッキングを楽しんだ。W女史お手製の餃子をメインに、きのこタップリのほうとうを作ることになった。栽培シイタケを入れたが、やはり野生きのこを入れないわけにはいかないと、探索に出かけた。 あちこちに橙褐色の小さなきのこが出ている。全体に透明感がありたいへんもろい。桜餅の匂いがハッキリ感じられた。コカブイヌシメジとのこと。今まで何度見ても覚えられなかったが、今回はよく観察して匂いも確かめたので大丈夫だろう。食菌だが小型で数も少ないので、今日のところは対象外。 T氏がいいものを見つけたと呼ぶので、行ってみて驚いた。これはホンシメジではないか!・・・と思ったが、コナラの落ち枝から生えている。ヒダを見ると強く垂生している。なんとこれはヒラタケだった。もちろん優秀な食菌なのでいただくことにした。 日がかげっても強い冷え込みはなく、風に舞う枯葉を眺めながらとても美味しい料理に舌鼓を打つ。まさに秋の味覚を満喫する贅沢な一日だった。 |
 |
 |
||
| 2002年 11月 2日(土) 茅ケ崎自然生態園 神奈川県横浜市 |
昨年10月に横浜市都筑区の「茅ケ崎自然生態園」で開催された、親子対象の「きのこ観察会」がたいへん好評だったとのことで、参加人数も大幅に増えて(約80人)今年も開催となった。 きのこ指導員は昨年の3人にもう1人が加わって4人。それでも、参加者の皆さんからの熱心な質問に答えていると、すっかり写真を撮ることなど忘れてしまった。あちこちから「きのこみ〜っけ!」の声が聞こえ、「これなんていう名前ですか?」に続いて「食べられますか?」の質問が多かった。 皆さん一様に種類や形の多様さに驚き、「食べられるきのこ」「毒のあるきのこ」「変な形のきのこ」などなど、興味が尽きない様子だった。 可食菌ではエノキタケ、スミゾメシメジ、キクラゲ、アラゲキクラゲなどがあり、1本だけカサに大理石模様のある白っぽい幼菌があって、どう見てもブナシメジにしか見えないのもあった。横浜市内のこんな平地の公園でも出るのだろうか。子供たちはエリマキツチガキやシロツチガキなどの、胞子を噴き出す様子が面白かったようでたくさん見つけていた。 少しシーズンが遅く、多くの種類を見ることはできなかったが、たいへん有意義な1日だった。 |