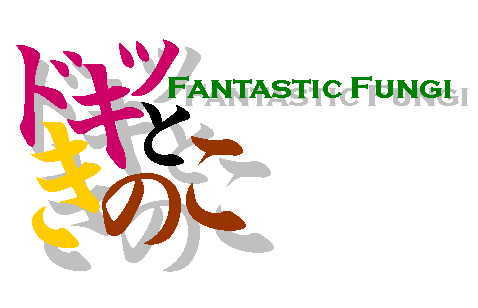 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 7月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 7月28日(日) 富士山北麓 山梨県鳴沢村ほか |
今回は富士山の北麓で27日夜からビバーク。暑さで寝苦しいこともなく、今頃がちょうどいい気候だ。鳴沢村の創造の森はカラマツが多く、秋にはいろんなきのこが出そうだが、今日はあまりいい写真が撮れなかった。 付近の「山梨県環境科学研究所」にある自然観察の遊歩道を歩いてみたら、溶岩のアカマツ林にもうタマゴタケが出ていた。カサの直径15センチを超える大きなものから、カサの色がたいへん鮮やかなものまでたくさん見ることができた。もう1種はヒダと柄のコントラストが美しいニワタケ。こげ茶色のビロードで覆われた太い柄が特徴。どの図鑑もあまり食毒に触れていないが、いかにも堅そうで食用には向かないのだろう。 なるべく裾野を何カ所も探索するつもりだったが、あまりの暑さに標高の高いところへ避難した。富士山はきのこ探し兼、避暑ができるのでイイ。 標高1,500〜1,600m付近にある、広大なモミの植林地を探索。あちこちにニオイコベニタケが群生している。苔の多い所にあると、色のコントラストが強くたいへん良く目立つ。カサの表面は粉で覆われているようで、触れると手に粉がつくような感じがする。カブトムシのにおいがするが、今日のはどれも弱いにおいだった。 どっしりしたコガネヤマドリを見つけてじっくり撮影したが、採取してみるとどれもすでに虫が入っていて、簡単に砕けてしまった。美味しいきのこは虫達との争奪戦になるが、自然のものは自然の生き物に譲るべきかも知れない。 最後にきれいなユウレイタケ(?)を見つけた。これはきのこではないが、雰囲気が近いせいかそう呼ばれている。正式名はギンリョウソウで、葉緑素を持たない植物。水晶蘭とも呼ばれる。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 7月25日(木) 不明菌の投稿 大阪府のYさんより |
いつも当ホームページを見てくれている大阪府の主婦Yさんから、イチゴの植木鉢にきのこが生えたとのメールをいただいた。デジカメで撮影して2冊の図鑑をくまなく調べたが分からなかったと、写真をメールに付けて送ってくれた。 驚いたことに、今まで見たこともないきのこで、たいへん美しい紫色のカサが印象的だ。株状に束生しているのでキシメジ科シメジ属かと思ったが、柄の上部にクモの巣状のツバが見える。すぐに胞子の色を見てくれるようお願いした所、さび褐色の胞子が出ていることを確認。 どうやらフウセンタケ科だと思うが、ビロードのような紫色の毛が密生するフウセンタケは私の図鑑には載っていない。カサの周縁部では毛がない様で、明るい黄褐色の輪郭が美しい。ぜひ詳しく調べたいと思うので、乾燥標本を送ってもらうことにした。もし、何かご存知の方は教えてください。 *大阪府のYさんにお願いして、胞子紋と乾燥標本を作って送っていただいた。城川先生に検鏡していただいたところ、驚くべき結果が出た。珍しいからではない。これがなんと、フウセンタケ科チャツムタケ属「ミドリスギタケ」だと判明した。地中の針葉樹木片から発生しているとのこと。ここまで姿を変えて発生することをはじめて知った。貴重な発見に、改めてYさんに感謝したい。慣れない標本作りをありがとうございました。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 7月21日(日) 高麗山(コマヤマ) 神奈川県大磯町 |
いよいよ夏本番で、そろそろ高麗山の「テングタケ通り(自称)」が賑やかなことだろうと思い行ってみた。気温は朝から30℃を超えて暑さが厳しいが、ここ高麗山は浜風が強く吹くことが多いのでしのぎやすい。 まずはテングタケダマシが散生しているのを見つけた。テングタケにソックリだが、小型でカサの鱗片がイガイガに尖っている。 苔の生えた地面からクロノボリリュウタケが生えていた。高さは4センチあまりで縦すじの脈になる柄が特徴。 いよいよテングタケ通りに入ると、いきなり以前から気になっていた青いテングタケが出ていた。毎年よく見かけるきのこだが、私のどの図鑑にも載ってない。どうやらまだ種名が決定していないのだろうが、アオタマゴテングタケという仮称が付いていると聞いたことがある。独特の青みがかった灰色が美しいが、暗い所に生えていることが多く今まで撮る機会がなかった。 続いては堂々とした姿のドクツルタケの仲間の幼菌。純白のテングタケ科のきのこは何種類もあって見分けが難しいが、これはかすかにピンク色がかった部分が見えるので、アケボノドクツルタケ(仮称)ではないだろうか。 斜面からはきれいな 同じ斜面にはカバイロツルタケが出ていたが、柄の半分以上が土に埋っていた。ずい分深いところのツボから柄を伸ばして、ようやくカサを広げたところだ。 ほとんどのコースを歩いて、スタートの地獄沢にもどる直前に、落ち枝から生えたきれいなキアシグロタケが見られた。サルノコシカケ科のきのこで、ハチノスタケやアミスギタケに近い種類だ。 もうまもなくテングタケ通りには、タマゴタケやウスキテングタケなどのカラフルなきのこ達が姿を現すことだろう。適度な雨が降ることをぜひ期待したい。 小さなきのこの繊細な写真も大好きだが、やはりテングタケ科などの大きくてカラフルなきのこの迫力ある写真は魅力的だ。パワーのある写真をぜひ撮りたいと思う。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 7月20日(土・祝) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
毎月初旬の定点観測の予定が、キノコの会の行事などで今日までずれ込んだ。もう梅雨は明けてしまったのだろうか。青空が広がり、風はあるものの真夏の日差しに、気温はグングン上がっていった。 ここは雨が少なかったのか、あまり多くのきのこは見られなかった。散策道に面した斜面に、なぜか数種類のイグチの仲間が集まっていて、ひとしきり種の同定と撮影を楽しんだ。そう言えばここは、去年ヤシャイグチを見つけたところだ。イグチの出やすい環境でもあるのだろうか。オリーブ色のカサと根元の黄色が特徴のミドリニガイグチや、全体が暗褐色で、カサ表面がきれいなビロード状の ※2005年7月3日に同じ場所に発生し、正しくはアイゾメクロイグチだったことが判明した。 その後は低地の方で、鮮やかなニセキンカクアカビョウタケがいくつもの小さな落ち枝に出ていた。直径5ミリほどの皿状のきのこで、似た種類がいくつもあるので正確な同定は困難なのかも知れない。同じ低地でカレバキツネタケが生えていて、私が間違って「キツネカレバタケ」と言ってしまったので、しばらく名前が混乱して分からなくなった。キツネタケ属であることをシッカリ覚えないと、また間違えそうだ。 今日一番の「ドキッと」は、実はきのこではない。なんと当ホームページをいつも見てくれている男性と、ばったり出会ったことだ。「いつも見てます」のひと言はたいへん嬉しく、これからの大きな励みになる。きっと今日も見てくれているのだろう。これからもよろしく・・・。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 7月13日(土)・14日(日) 長岡市東山・悠久山 新潟県長岡市 (キノコ会宿泊勉強会) |
今年の「神奈川キノコの会」の宿泊勉強会は、新潟県長岡市で2泊3日(私は1泊参加)で行われ、地元「長岡きのこ同好会」の前会長・宮内信之助先生(長岡技術科学大学教授)を講師として招いた。初日は「フウセンタケ科フウセンタケ属のきのこ」について講演された。 夜には台風と梅雨前線の影響で強い雨が降り始め、翌日の観察会が心配されたが、翌朝は天気が回復。青空も広がり蒸し暑い一日となった。 まずは東山ファミリーランドという自然観察林で探索。雨のおかげでいきなり美しいテングタケに出会えた。瑞々しい姿に、思わず何カットも撮影してしまう。 気温が上がったのでテングタケやイグチの仲間が一斉に顔を見せ始めた。テングタケ科ではタマゴテングタケモドキ(アカハテングタケ)が多く見られ、それの幼菌らしいものがあった。カサの周辺は白っぽく、ハッキリした条線が見られる。一方、イグチではウラグロニガイグチやニガイグチモドキが多かったが、早くもセイタカイグチを見つけることができた。関東に来てからは初めての発見だ。明るい赤褐色に大きな網目の柄が美しい。 昼食時に「長岡きのこ同好会」で作っていただいたキノコ鍋をごちそうになり、午後は宮内先生の案内で、一部のメンバーは近くの悠久山公園の方へ探索地を変更した。きのこの種類は午前と大差はなかったが、きれいなシロイボカサタケを見つけられたので撮影。 そして、最後を締めくくるように発見されたのが、なんと先生が発表されたばかりのアブラシメジの近縁種「ウスムラサキアブラシメジ」だった。前夜の講演で解説されたばかりで、しかも、これまでの発見は佐渡島のみで、本州では初めての発見とか。カサと柄に強いヌメリがあり、柄の全体が薄い紫を帯びる。カサ周辺のシワもはっきり見られた。 まるで演出されたような展開に、不思議な印象を受けて、たいへん興味深く観察することができた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 7月 7日(日) 神武寺(キノコの会) 神奈川県逗子市 |
七夕には好都合の梅雨の晴れ間となったが、きのこ探しにはちょっと暑くなり過ぎで、岩場の斜面が多い神武寺の山は、私にはまるで修行の山のように思えた。しかし、気温が上がったおかげで大きなアカヤマドリやテングタケの仲間が採集されていた。 山に入る前の桜並木に、きれいなケガワタケが出ていた。大きくなるとカサが不規則に波打つようだが、その前のとても均整の取れた美しい姿だった。青空をバックにした写真をGalleryに入れた。 昨日、激しい雨が降ったらしく、タップリ水分を含んだ枯木から粘菌がいっぱい出ていた。この前「粘菌はカテゴリー外」と言ったばかりだが、あまりの姿の良さについシャッターを切ってしまう。これは図鑑によるとシロウツボホコリというのに最も似ている。高さは5ミリ、太さは1ミリ以下。まさにミクロの世界だ。 スミゾメヤマイグチがたくさん発生していたようで、もうすでにかなり傷んでいた。その中からまだきれいな成菌と幼菌を撮った。独特の黒いオリーブ色が美しいきのこだ。 もう1種のイグチは、早々と姿を見せたヤマドリタケモドキ。虫たちにとっても旨いきのこなのだろうか、カサも柄もよくかじられているきのこだ。私の旨いきのこBEST10にも入る。管孔面がまだ白い幼菌の状態が理想的だが。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 7月 6日(土) 再度、西臼塚へ 静岡県富士宮市 |
やはり、どうしてもコガネヌメリタケをもう一度撮影したくなって、また富士山の西臼塚へ来た。・・・が、結論から先に言えば、残念ながら先週のものはすでに干からびていて、新たに発見することはできなかった。 今日は一転して、あまりきれいなきのこは見ることができなかったが、朽ちた切り株から1本だけヒロヒダタケモドキが出ていた。ヒロヒダタケによく似ているが、やや小型でヒダが柄に垂生していることで見分けられる。同じキシメジ科だがそれぞれ属は異なるので、いわゆる「他人の空似」きのこである。 いたるところでイタチタケが出ていて、地上生も材上生もあるため、カサが白っぽければイタチタケ、褐色ならムササビタケという乱暴な区別にしておいた。ムササビタケはあまり多くはなかった。 今日の中では最も華やかな写真になったのが、まるで燃え上がる炎のようなニカワホウキタケ。名前はホウキタケだが、分類的にはキクラゲに近いアカキクラゲ科になる。これも他人のナントカだろうか? |
 |
 |
||
 |