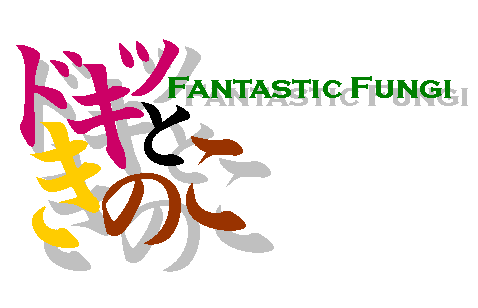 |
きのこ探して 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 5月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 5月26日(日) 高麗山地獄沢 神奈川県大磯町 |
「神奈川キノコの会・平成14年度総会」(於:平塚市博物館)に出席した後、近くの高麗山・地獄沢へ寄ってみた。大した成果はなかったが、種名のハッキリしない2種が気になったので掲載しておく。 最初の1種はクロアシボソノボリリュウタケとして一旦UPしたが、正しくはナガエノチャワンタケだろう。まるで金属探知機のように、長い柄の先に灰色の円盤がついている。こんな黒い色のナガエノチャワンタケもあるのだろうか。 針葉樹と思われる倒木の上に、小さな褐色のきのこが出ている。カサに条線があり中央がやや尖っている。ヒダの色や、柄の上部に膜質のツバがあることから、ヒメアジロガサモドキではないかと思う。 もう1種は遊歩道の土から束生していた、全体がササクレだらけのきのこ。小型のツチスギタケのようにも思えるが、ササクレが白いので違うのだろう。キツネノカラカサ属のほうに入るのだろうか。まったく分からないので標本撮影をして、検鏡してもらうことにする。 *UPしてすぐにイナタク君から、「最初のきのこはナガエノチャワンタケではないでしょうか?」とメールをもらった。確かに裏面や柄に微毛が密生しているので、ナガエノチャワンタケが正しいようだ。こんな灰色の個体もあるということだろうか・・・?イナタク君、どうもありがとう。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 5月25日(土) 表丹沢各地 神奈川県秦野市 |
丹沢山系の南縁を西から点々と移動してみた。まず「表丹沢県民の森」からスタート。スギ・ヒノキが多い中で、カシワが群生する明るい森もある。 スギ(?)の切り株にセンボンイチメガサが群生していた。ツバから下の柄がささくれている。 次の場所では、同じモエギタケ科の毒菌ニガクリタケが生えていた。きれいな黄色が特徴。幼菌の頃は微毛に覆われて、やや赤味のある色をしている。その近くではヒトヨタケが群生していた。とても小さい幼菌がいっぱいあって、種名が分からなかったが、大きく育った数本を見つけて判明。フリルのようなツバが面白い。 さらに東へ進んで、蓑毛自然観察の森に着いた時はもう夕方だったが、かなり日が長くなっているのでまだ撮影可能だ。鮮やかなヒイロベニヒダタケを見つけた。2本だけだったがカサの周囲にハッキリ明るい黄色の縁どりが見える。すぐ近くでは同じく新鮮なウラベニガサが出ていた。ヒダがきれいなサーモンピンクをしている。 *昔、私も住んだことのある京都府の長岡京市の方から、キヌガサタケの幼菌が出始めたとのメッセージをいただいた。いよいよ梅雨のシーズンが近づいてきたようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 5月18・19日(土・日) 長岡市東山自然林ほか 新潟県長岡市 |
「神奈川キノコの会」の、今年の宿泊勉強会の下見調査に同行させてもらった。18日(土)の夕刻に出発。現地では「長岡きのこ同好会」の方2人に、たいへん丁寧に案内していただいた。 まずはコレラタケが出るところがあるという「悠久山公園」へ。残念ながらコレラタケには出会えなかったが、蒼柴(アオシ)神社の境内で、きれいなアミスギタケの群生が見られた。 その後は東山自然林や森立(モッタテ)峠の方まで探索。金曜日の雨のおかげであちこちにモリノカレバタケが出ていた。独特の橙色に近いカサは、雨に濡れると美しい表情を見せてくれる。 その他はヒノキオチバタケやミイノモミウラモドキと思われるきのこが見られた。 今日19日(日)は晴れて気温が上がったり、小雨が降って肌寒くなったりと落ち着かない天気で、まだウグイスのさえずりが聞かれる一方で、もう早くもセミが鳴き始めていた。勉強会は7月に行われるので、ベニタケ科やテングタケ科などが期待できそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 5月12日(日) 金沢自然公園 神奈川県横浜市 |
いくつかの市民の森が隣接した一角に、動・植物園を含む金沢自然公園がある。中でも自然の森を散策できるエリアは、変化に富んでいて歩きやすいコースだ。 タップリの雨と初夏を思わせる気温になったが、ほとんどきのこを見つけることができなかった。まずは雨で一気に出た感じのキクラゲ。数種の木の落ち枝からたくさん出ていた。 急な斜面で落葉から生える小さなきのこを発見。キララタケだ。これを見て前から気になっていたことがハッキリした。『Gallery』コーナーの「キララタケ-2」は、どうやらコキララタケのようだ。橙色の菌糸塊(オゾニウム)を伴わない場合もあるらしい。カサ表面の鱗片がキララタケに比べて、よりシッカリ付いていて剥れにくい感じがする。『Gallery』は「コキララタケ」と改め、文章も変更した。 |
 |
 |
||
| 2002年 5月11日(土) 芝公園 東京都港区 |
デジカメを新調した。これまでのSONY-DSC-S50はたいへん扱いやすく気に入っていたのだが、Nikonから同じフリーアングルモニターの500万画素デジカメ、COOLPIX5000が発売されたので、より高画質な写真を撮れるよう変更することにした。今まで大活躍だったDSC-S50は、引き続き家族達が愛用してくれる。 仕事帰りに芝公園を覗いてみると、昨日の雨のおかげでウッドチップにツバナシフミヅキタケが群生していた。さっそくNEWデジカメの出番である。・・・が、使い慣れないため思うように撮れない。ひとまずは第1号記念ということで、記録だけになった。新鮮な状態だったが、食欲の湧くきのこではないと思った。 |
 |
| 2002年 5月 5日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
定点観測のメンバー5人に、GWを利用して遊びに来ていた我が娘も加わって、初夏を思わせる汗ばむ気温の中の探索となった。 前回見つけたクロサイワイタケ科の不明菌は、ほとんど成長しないまま枯れ始めていたので、あれで成菌だったのかも知れない。いつも数種類は発見できる低地ではほとんどきのこが無く、今日は少ないかも知れないという予感がした。 最初は竹林の中でイタチタケを発見。少し乾燥してカサや柄がささくれているが、まだヒダは明るい色だった。 同じ竹やぶで娘が興味深いものを発見した。春にナラタケが出ることには驚かなくなったが、竹の切り株から生えているのは今まで見たことがない。あらゆる木から生えることができる強い菌なのだろうと思う。 やはり多くの種類を観察することはできなかったが、イタチタケと同じヒトヨタケ科ナヨタケ属のきのこをもう2種類見ることができた。土から生えるムジナタケとコナラから群生しているムササビタケだ。 5月に入って気温はかなり上がったものの、今週は雨が少なかったので、低地や湿地でもきのこが少なかった。これからは一雨ごとに、きのこの種類が増えていくことだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |