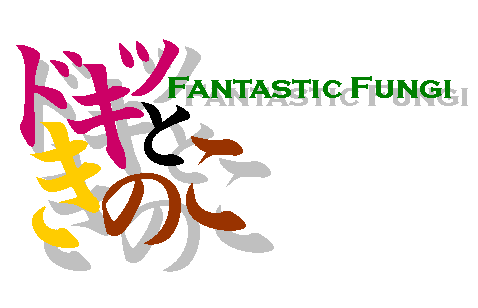 |
きのこ探して 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 4月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 4月28日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県大磯町 |
高麗山もスダジイの大木が多い所なので、カンゾウタケのチェックをするために行ってみた。いつも通りまずは地獄沢から入る。 沢沿いの倒木にベージュのカサの群生を見つけて近づいてみると、ハチノスタケがいっぱい出ている。一見するとスジウチワタケモドキにそっくりだが、カサの裏面は大きなハチの巣状の網になっている。 すぐそばの倒木にはアラゲカワキタケも出ていた。カサが反り返って面白い姿をしている。どことなく人の表情にも見える。 今日はいたるところでアミスギタケの群生を見た。今が最盛期らしく、姿も生え方のバランスも美しいので、ついシャッターを切ってしまう。フォトジェニックなきのこの一つと言えるだろう。 草むらの中にポツンと1本だけムジナタケが出ていた。いつもは周囲に数本ずつ散生するはずだが、探しても見つからなかった。カサ表面に少しつやがあってムジナタケらしくないが、ヒダがすでに胞子で黒くなっていたので間違いないだろう。 やはりカンゾウタケは早い春に左右されることなく、5月の中旬以降に出るのだろう。ここではまったく見ることができなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 4月27日(土) 真鶴半島 神奈川県真鶴町 |
梅も桜も、そしてハルシメジも例年より早かったのだから、もうカンゾウタケも出ているのではないか・・・と、真鶴半島へ行ってみた。クロマツ、クスノキ、スダジイの巨木が密生して、まるでジャングルのような雰囲気さえただよう。 なるべく大きなスダジイを中心に根回りをチェックすると、なんとナラタケの株が見つかった。すでに少し傷んでいるが、多数が密生している。 カンゾウタケはなかなか見当たらず、気温が高くても早く出ることはないのかと、諦めかけたとき、小さな赤い点を見つけた。撮影後に画面をズームアップしてみると、間違いなくカンゾウタケだ。直径3ミリ!その後は付近で2〜3センチの幼菌をいくつか見つけられた。カンゾウタケは例年通りのようだ。 マツの倒木にとても小さなきのこを発見。指先でつぶすとツンと薬品臭がする。アクニオイタケだろう。高さが20〜25ミリとたいへん小さいが、アップで撮ると均整の取れたいい形をしている。 風が強く肌寒い一日だった。カンゾウタケはやはり、GW明けくらいがピークになりそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 4月21日(日) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
天気予報では関東地方は午後から雨、とのことだったが、もう朝から降り始めて1日中止むことはなかった。久しぶりに泉の森公園へ行ったが、レインギアに傘をさしてのきのこ探しとなった。 まずは落ち枝に並んだアミスギタケ。雨粒がはねてすぐにレンズに付いてしまうので、雨の日のローアングル撮影は難しい。 サクラらしい材にスエヒロタケがいっぱい出ていた。もう今までにたくさん撮っているので、やり過ごそうかと思ったが、やはりこのきのこの新鮮なものはどうしてもシャッターを切りたくなる。特に今回は、なぜか和風の雰囲気がただよい、GALLERYに「スエヒロタケ-2」を入れることができた。 昨年の4月に高麗山で見つけて以来、1年ぶりにアミヒラタケを見ることができた。柄が太く、カサ表面の鱗片が圧着している。まだ幼菌で柔らかい状態だった。 ハラタケ類は見ることができなかった・・・と、駐車場へ戻る途中で、やっと小さな束生を見つけた。傘中央に特徴的なふくらみがあり、柄は中空で少しササクレがある。雨に濡れてカサにつやがあるので分からなかったが、後でよく観察するとどうやらアシナガイタチタケのようだ。 雨中の探索にしては、まずまずの撮影ができた。今週、さらに雨が降りそうなので、これからが楽しみだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 4月14日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
定点観測地「新治の森」の今日の参加者は5名だった。さすがに3日ほど雨が降ると、この森は面白いきのこを見せてくれる。 最初の低地ではまず、アシナガイタチタケのきれいな状態を発見。カサの表面に細かな繊維状のものが見える。すぐ横のスギの倒木からは、ケコガサタケ属と思われる全体が茶褐色の小さなきのこが束生していた。カサの中央が尖って条線がハッキリしている。 同じくスギと思われる切り株からは、奇妙な形のきのこが群生していた。以前見たマメザヤタケの幼菌に似ているが、こんなヘラ状に広がるのは種類が異なるのだろう。クロサイワイタケ科のきのことしか分からない。後日の再観察が必要だろう。 カキの果樹園で、ずい分頭部の黄色いアミガサタケが見つかった。頂部はもう黒くなっていたが、こんな色のアミガサタケはあまり見たことがない。 別のスギ林の中で、きれいなスジオチバタケを見つけた。カサに粗い溝線があり、溝の部分は濃い紫色をしている。カサの径は10ミリ前後と小さいが、よく見るとなかなか美しいきのこだ。 昨年の4月30日にこの森でミズベノニセズキンタケを見つけたが、その後、雨が少ないせいかまったく姿を消してしまった。このところの雨で再びわずかなせせらぎができて、また、その姿を見せてくれた。この場所以外では見たことがなく、再び撮影ができたことを嬉しく思う。今回はその名にふさわしく水辺で撮ることができた。小さくて特徴のないきのこだが、なぜか魅力的な子嚢菌だ。 今日は2種類のヘビ(ヤマカガシとアオダイショウ)を見かけ、ウグイスやシジュウカラ、コジュケイなど多くの野鳥の声も聞いた。すべてが一気に動き出した感じがする1日だった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 4月13日(土) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
2〜3日雨が続いたが、気温の方は平年並みに下がったので、もう花の終わってしまった「花冷え」で肌寒く感じる。しかし、山はすっかり新緑の風景になり、もう1週間もすると鮮やかな緑一色になるのだろう。 普通のタイプのアミガサタケが出始めたようだが、1本しか見つけられなかった。なかなか群生に出会えない。 小さなオキナタケ科のきのこを見つけたが、コフミヅキタケでいいのだろうか。カサの周縁に条線があるので少し疑問がある。はっきり条線のあるツバが特徴的だが・・・。※後日ツチイチメガサの可能性が高いことが分かった。 新鮮なアラゲキクラゲがたくさん見られたのは、昨日までの雨のおかげだろう。まるでチャワンタケのような生え方のもあった。 梅雨までのしばらくは、汗ばむこともない快適な季節なので、この期間にたくさんのきのこを見つけたいものだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 4月6日(土) 曽我梅林・城山公園 神奈川県小田原市・大磯町 |
今年は春が早く来て、入学シーズンの今、すでにサクラは散ってしまった。そして、あちこちからもうハルシメジが出ているとの話も聞く。昨年、湯河原でハルシメジを探したのは4月29日だった。 ためしに小田原市の東にある曽我梅林へ行ってみると、もうウメの実が色づき始めている。しばらく探すと、若いウメの木に菌輪を描いてハルシメジが出ていた。カサにつやがあり中央のとがった独特の姿で、ヒダの淡いサーモンピンクが見分けるポイント。カサの周縁が波打ったり、ややもろい点は毒菌のクサウラベニタケによく似ている。 先週の不明菌のその後が気になって城山公園に再度寄ってみたが、木が乾燥していてまったく変化がなかった。枝を一部持ち帰って、湿らせて様子をみることにした。よく雨が降ったが、まだきのこの姿は見られない。枯れた木にワヒダタケが出ていた。ヒダが同心円状に並んでいて見分けやすいきのこだ。 |
 |
 |