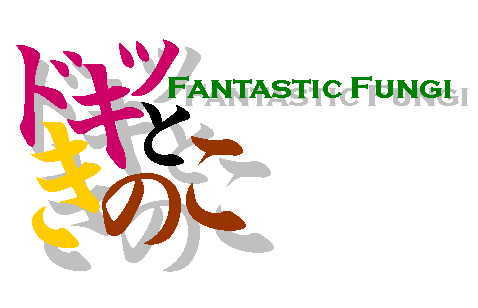 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 9月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 9月29日(日) 高麗山 神奈川県大磯町 |
彼岸を過ぎて一気に秋になり肌寒いほどの日が続いたが、今日はなぜか一転して初夏のような暑い1日だった。里山や公園を探索した人たちから「きのこがいっぱい出始めた」という情報が入っていたので、今日のとある催しの下見を兼ねた高麗山探索を楽しみにしていた。 JR大磯駅から心臓破りの坂を登って高田公園を過ぎると、道の両脇に小型のきのこが群生していた。採取してみると、ちょうどヤマノイモなどのむかごに似た黒い塊から生えている。地中に菌核を作るタマムクエタケだ。子実体に目立った特徴がないので菌核がついてない場合は同定しにくい。 薄暗い茂みの中に点々と株立ちの白いきのこが並んでいる。明らかにシメジの仲間の生え方だ。カサが明るい灰色でずんぐりスタイルのため、一見ホンシメジのような印象を受けるが、そんなはずはない。柄があまり太くなく中空なのでこれはシロノハイイロシメジだろう。多量の雨の後に出るとのこと。確かに。 またまた、ハリガネオチバタケが大量に生えていて、いいのを見つけると撮ってしまう。今回はまさに針金状の柄を写せた。 キヅタかフジの枯れたツルから、きれいなきのこが出ている。ハッキリしたツバがありツバから下がささくれている。カサの中央が高くなっているのでセンボンイチメガサのように思うが、数本だけなのでそれらしくはない。周囲には小さな幼菌が多数見えるのでこれから大きな株になるのだろうか。 地上生の大きなきのこがあって暗くてよく見えないが、カサの表面に放射状の細かなシワがあり、大きなツバに黒い胞子がいっぱい乗っている。ヤナギマツタケのようだが、地上に出ているのは変だ。撮影後掘り出してみると、地中の根から生えていた。周囲にヤナギやカエデが見当たらなかったが、種名は間違いなさそうだ。 どういう訳か付近の里山でいっぱい出ていると聞いた、カラカサタケやタマゴタケを1本も見つけられなかった。海岸に近い高麗山はかなり環境が違うと言うことなのだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月23日(月・祝) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
今日は一日中雨が降るという予報だったため、久しぶりに休息日にしようと思っていた。ところが空は明るく薄日もさしている。絶好の撮影日和ではないか! 急に思い立って七沢森林公園へ行く。いたるところでニオイドクツルタケが目に付く。他にもテングタケ科のきのこを見ることができた。 まず、ツルタケ。カサにはっきり条線が見え、ツバがない。昨日のカバイロツルタケほど柄は長くないが、それでも均整の取れた美しいきのこだ。 テングタケによく似ていて全体が赤いきのこ、ガンタケを見つけた。あまりきれいな状態を見かけないので写真が少ないが、これはいい形で並んでいた。 そしてもう1種、見事に並んでいたのがタマゴタケ。ようやくいいスタイルのタマゴタケが出始めた。今年は多く出るのだろうか。 最後に沢沿いを歩いていて、見慣れない色のきのこが朽木に出ているのを見つけた。子嚢菌だとはすぐに分かったが初めて見る色だ。小豆色とかエビ茶色が近い色だろうか。どうやらニクアツベニサラタケのようだ。外側が真っ白で厚みがあり、とても強靭だ。薄暗い中でこの色を撮影するのに一苦労したが、なんとかこの微妙な色が出せたと思う。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月22日(日) 県立四季の森公園 神奈川県横浜市 (神奈川キノコの会) |
今月3回目の「神奈川キノコの会」観察会。昨年に比べるとかなり種類も多く、大きなきのこも見ることができた。 薄暗い斜面の深い落ち葉に、なかば埋もれるようにテングタケ科のきのこが群生していた。カサがほとんど黒に近い褐色で、柄にも黒い繊維状の模様がある。ドウシンタケだと思ったが、クロタマゴテングタケと同定された。カサに条線があればドウシンタケで食菌だが、これは猛毒菌ということになる。 草に隠れた黄色いベニタケ科のきのこが見つかった。カサに薄い緑色が見えたのでアイタケかと思ったがひび割れ模様はなく、横にあった幼菌はほとんど黄色だけなのでカワリハツの方だろう。紫色にも黄色にも緑色にもなる「変わりハツ」だ。 その付近の斜面にも薄い黄色のきのこが群生していた。こちらはハラタケ科の方でウスキモリノカサだ。カサが開く頃にはヒダが黒くなってしまうが、これは紫がかった明るい灰色できれいな写真が撮れた。 テングタケ科でもう1種、カサの条線がとてもきれいなカバイロツルタケを見つけた。ツバのない細くて長い柄はまさに鶴タケがピッタリ。近くでは幼菌も見られた。ようやく、テングタケの仲間が出始めたようで、これからが大型のきのこのシーズンなのだろうか。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月21日(土) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
まずはじめに先週の訂正から。9月16日の高麗山で撮ったアカキツネガサは、気になっていた通りワタカラカサタケの方が正しいようだ。と言うのも、今日「泉の森公園」で紛れもなくアカキツネガサという、典型的なものを見つけて、柄やツバの感じがまったく違うことが判明。シッカリしたツバがあり赤い線で縁取られる。柄は白く平滑。今回でキツネノカラカサとも似ていないことも分かった。 最近めっきり秋らしくなったと思ったら、今日が彼岸の入りとか・・・。一雨ごとに新顔のきのこたちが次々に姿を見せる・・・ハズなのだが、なぜか今年もまだ少ない。 真っ白の太い幼菌がいくつもあって、採取してみると柄がポキッと折れる。ベニタケ科のようだ。かじってみてもまったく辛くない。よく探すと成菌も見つけることができた。ヒダが密なのでこれはシロハツモドキの方だ。 空気が乾燥しているせいか、カサがまるで花びらのように裂けてしまったきのこがあった。大きさ(直径3センチ)やカサの鱗片の感じからクロヒメカラカサタケだと思う。よく見るとツバに黒い縁取りがある。 斜面でようやく大き目のきのこを見つけた。ハラタケ属であることはすぐに分かるが、最近特に多くの近縁種が見つかっているようで、「仮称」や「近縁種」の文字が飛び交っている。私のレベルではこれはザラエノハラタケにしかならないが、とりあえず近縁種としておこう。 最後に朽木から黄色い小さなきのこが出ていて、ダイダイガサかと思ったら1本だけのベニヒダタケだった。カサの縁に条線があるのでヒイロベニヒダタケの黄色いタイプとは見分けられる。ローアングルで見ると中心部の透けた明かりがとても美しい。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月16日(月・休日) 高麗山 神奈川県大磯町 |
あいにく朝から雨が降り続き、時おり風も吹いて横殴りに強い雨が降る。撮影には最悪の天気となったが、とにかくキワタゲテングタケが高麗山にも出ているのかどうかだけでも確認したい。 昨年と同じようにキツネノカラカサとアカキツネガサが混生している。属は異なる2種だが外見はよく似ていて、白いタイプのアカキツネガサだと見分けがつきにくい。これはアカキツネガサで良さそうだ。日に透けたヒダがとても美しい。 斜面にシロタマゴテングタケが出ていた。柄のササクレが細かい点でドクツルタケと見分けられるようだが、あえて見分ける必要も無い・・・どちらも猛毒とのこと。 肝心のキワタゲテングタケは予想通りいくつも出ていた。雨に打たれてほとんどが倒れていたが、2年前のようなりっぱな大きさのものもある。濡れているため少しみすぼらしい姿だが、幼菌も見ることができた。今日、気づいたことだが、やや老菌で倒れて古くなったものはかなり不快臭がした。しかし、吐き気を催すという表現とはほど遠く、他のきのこでも古くなったり乾燥すると発するような臭気だと思う。 神奈川県南部では多数見ることができるのに、ネットで検索しても他府県からの報告がないのも不思議だ。新種発表は福岡市の竹林で採取とある。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2002年 9月15日(日) 葉山・山ノ上公園 神奈川県葉山町 (神奈川キノコの会) |
9月は「神奈川キノコの会」の野外勉強会が3回行われる予定だが、今日はその2回目。閑静な住宅街に隣接する里山で、よく整備されている割に自然も良く残っている。 すぐに斜面に生えるハリガネオチバタケを見つけたが、このタイプの小型菌がきれいな状態だとどうしても見逃せない。こんなものをジックリ撮ってるから、すぐに置いてきぼりになってしまう。 枯葉が降り積もった間からテングタケ科のきのこが出ていて、カサは灰色のカスリ模様、ツバがあり柄はササクレて袋状のツボがある。カサ以外は真っ白なのでコテングタケモドキになるのだろうが、なんとなく感じが違う。小型だからという理由からではなくて、カサの中央が少し窪んでいたり、ツバがシッカリ残っていて形状が違う点など、後の鑑定でも疑問が残り検鏡されることになった。 ミヤマオチバタケにそっくりだが葉や地面からではなく、必ず落ち枝から生えるヒカゲオチバタケ(仮称)のきれいな束生を見つけた。柄が濃淡のある褐色で強靭な所はミヤマオチバタケと同じだ。 ちょうど2年前の同日、高麗山で見つけた不明菌が昨年ようやくキワタゲテングタケだろうと分かった。全体が黄色の湿った微粉で覆われる背の高いテングタケ科のきのこだが、これがきれいに並んで生えているのが見つかった。しかしこのきのこについてはいくつかの疑問点もあり、城川先生が詳しく調べられることになった。 明日は久しぶりに高麗山へいくつもりだが、ひょっとするとこのきのこが見られるかもしれない。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月14日(土) 富士山須走口登山道 静岡県小山町 |
実は私は今までベニテングタケを見たことが無かった。西日本で撮影をしていたため、見る機会が無かった。関東に転勤になって2年が過ぎ、今年こそはどうしても撮影したいと機会あるごとに周囲にもらしていたところ、先日、いつも「ドキッときのこ」を見ていただいている静岡県のFさん(男性)から、富士山で出始めたとの情報をいただいた。さっそく教えていただいた場所へ・・・。 須走口五合目の駐車場は標高2,000mにある。そこから登山道を登っていくのだが、小富士へ向かう道がちょっと気になって入ってみると、いきなり立派なハナイグチを見つけることができた。周囲を探すときれいな赤茶色の幼菌がいくつも出ている。 付近ではナラタケの群生もあった。どうやら昨年夏の旱魃のダメージから立ち直ったきのことそうでないのがあるらしい。テングタケ科がまだダメージがあるように思う。 教えていただいた場所はもっと上なので、斜面を登って登山道に入り、さらに上へ向かう。途中、何種類かのフウセンタケ科のきのこを撮ったが、ほとんど種名が分からない。薄紫で太いフウセンタケ属のきのこがあって、カサに粘性があり、柄が地中長く伸びていた。他にも名前のハッキリしないものがあり、つくづくフウセンタケは難しいと思う。 寄り道が多く、雨も降ったり止んだりで、少々バテ始め、ベニテングタケは見つけられないかも知れないと、弱気になって休憩している所へ、上から降りてきた人が「きのこですか?」と声をかけてくれた。ベニテングタケのことを聞いてみると、「ついさっき見たけど・・・あれは毒だよ!」。お礼の言葉もそこそこに急いでその場所へ向かった。 初めて見るベニテングタケ。大群生とは行かなかったが、数ヶ所でまとまって見つかり、タップリ撮影させてもらった。やっぱり撮り応えのあるいい被写体だ。私にとっては記念すべき日になった。Fさん、HOTな情報をありがとうございました。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月 8日(日) 富士山・太郎坊 静岡県御殿場市 (神奈川キノコの会) |
山の天気が変わりやすいことは知っているつもりだったが、真夏の強い日差しと秋の冷たい雨とが日に何度も入れ替わると、体温調節に一苦労する。 早朝は青空が広がり、写真撮影では低く差し込む直射日光に悩まされた。倒木にきれいに群生しているきのこを見つけたが、種名が分からない。クヌギタケに近い種類なのだろう。 10時からは「キノコの会」の観察会に合流。太郎坊(五合目)の駐車場から、さらに上に広がるカラマツの多い森を探索。ほとんど道はなくて樹海の様相だが、勾配がハッキリしているので迷う心配はなさそうだ。 カサの表面に細かな鱗片がある中型のきのこを見つけて、ローアングルで撮るとヒダのピンク色が見えた。イッポンシメジ科のきのこのようだが、図鑑に見当たらない。後の鑑定会で城川先生から、まだ仮称の段階だがムジナイッポンシメジ(仮称)だと聞いた。鱗片は指で触ると簡単に剥がれ落ちる。 同行した仲間がスッポンタケの幼菌を見つけた。一番大きいのは直径7〜8センチもあり、上の部分がすでに割れていて間もなくスッポンタケが姿を現すのだろう。あの特有の匂いは感じられなかった。 次は別の一人が小さな白いきのこを発見。カサの表面に細かなササクレがありきれいに輝いて見える。ヒダが少し赤味を帯びているので、これもイッポンシメジ科のきのこキヌモミウラタケのようだ。高さは4センチほど。 さらにもう一人が倒木の苔上にきれいに並んだきのこを発見。撮影していて妙なことに気づいた。右の3本はヒダが黒くなっているが、左の1本は幼菌のためか白く、しかも他と違って垂生しているように見える。採取してみて分かったのだが、左の1本だけが種類がまったく違って、なんとアミヒラタケの幼菌だった。他の3本はムササビタケに近い種類らしく、はっきりとした種名同定はされなかった。※右3本はハゴロモイタチタケ。 ようやく「ハザカイ期」が終わっていろんなきのこが出始めたようだ。これからが楽しみなシーズンなのだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月 7日(土) 富士山・西臼塚 静岡県富士宮市 |
明日の富士山五合目での「キノコの会」観察会に合わせて、富士山の西臼塚へ今日から行っておくことにした。昨年(7月29日)に見つけた「珍菌」ナガエノニカワアナタケ(仮称)の追調査も気になっていたが、うっかり月を間違えて1ヶ月遅くなってしまった。まだ出ているだろうか。 朝、到着してすぐに探してみた。タイミング悪くドシャ降り状態で傘を片手に探したら、まばらに4本だけ見つけることができた。が、撮影は断念した。 その後、雨がやむのを待って、他のきのこ探しを始めた。小さなツボから出ている真っ白いテングタケ科のきのこがあり、てっきりシロツルタケだと思ったらツバがシッカリ付いている。後でヒダがピンク色がかっているのが確認できたので、タマゴテングタケモドキだろうと思うが、それにしても純白すぎる。 大きなブナの倒木にいろんなきのこが出ている。カサの表面の鱗片模様からアミヒラタケだと思ってローアングルで撮影すると、裏面はアミではなくヒダになっていてリング状の帯がある。なんとツキヨタケだった。そしてそのすぐ横には、正真正銘のアミヒラタケも出ていた。カサ一面に広がる鱗片が美しい。 同じ1本の倒木からはこの他、 午後遅くには駐車場から麓へ降りるコースを探索してみた。こちらはモミの木が多く、きれいなウスタケがたくさん見られた。苔の上に生えると色の対比が鮮やかで、ひときわ美しさが映えるものだ。さっきの雨でウスの中にいっぱい雨水が溜まっていた。そして、その近くで見つけた小さなきのこコチャダイゴケでは、雨で弾き飛ばされたのだろうか、中にあるはずの胞子の詰まった碁石のような粒が、きれいに無くなっていた。 昨日と今日で雨はタップリ降ったから、ぜひとも明日は雨の降らない1日であって欲しいものだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 9月 1日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
雨が少なく残暑が厳しいという、きのこにとっては嬉しくない天候で、定点観察地「新治の森」もあまり期待はできないと思っていた。案の定、地面は乾いて砂ぼこりが舞っている。それでも低地の斜面ではなかなか面白いきのこを見ることができた。 しおれたカサの黄色いテングタケ科のきのこがあって、タマゴタケモドキかキタマゴタケがハッキリしなかったが、すぐ近くに新鮮なのが数本生えていた。カサにハッキリした条線があり、ヒダとツバも黄色い。柄にも黄色の段だら模様があり、キタマゴタケと判明。よく考えてみると不思議なことに、新治の森で今までタマゴタケを見たことがない。ここは黄色しか生えないのだろうか。 そのすぐ横では、今年もヤシャイグチを見ることができた。カサの中央が擬宝珠のように尖って、柄に深い網目が見られる。あまり見られないきのこだ。 地面から生えている中型のきのこがあったが、カサ表面の状態や茶色の胞子をいっぱい被った厚い膜質のツバ、シッカリした柄の感じからヤナギマツタケのように見える。撮影後に掘ってみると木の根から生えていた。やはりヤナギマツタケで良さそうだ。 カサの表面がひどくひび割れた灰色のきのこが群生していたが、周囲の枯葉を除いてよく見ると、乾燥でカサがひび割れてしまったナカグロモリノカサだと分かった。まったく雨が降らなくてもたくさん生えていることがあるので、きっと日照りに強いきのこなのだろう。 まれな種類も見ることができるこの森は、やはり定点観察には最適な所だ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |