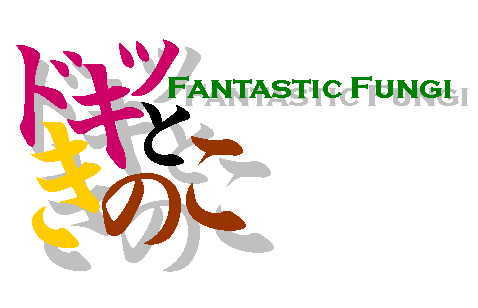 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 8月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 8月25日(日) 清里の森公園 山梨県高根町 |
前夜に出発して約4時間で清里に到着。すぐに愛車「竹ベンツ(?)」でビバーク。朝6時に起床して軽めの朝食後「清里の森公園」へ行った。ほとんどカラマツの純林に近くわずかにアカマツやシラカバ、モミなどが混じる、広々とした気持ちのいい公園だ。 まず目に飛び込んできたのがきれいなクサハツ。名前の通りくさいのできのこ狩りでは見向きもされないが、私にとっては新鮮なきのこはとてもいい被写体になる。もう1種、きのこ狩りで敬遠されるオキナクサハツも、きれいなものを見つけた。クサハツに近いがカサの表皮の裂け方が独特で、外見上で見分けやすいきのこだ。どちらも大きなきのこなので目に付きやすく、きのこハンターがガッカリして蹴飛ばすのもうなづける。 小さなきのこでは今回、ヘラタケを初めて見ることができた。相撲の軍配とか天狗の持つヤツデのようなものに似た形で、変化があって面白い。 もう1種、極小きのこで真っ白のシロコナカブリがいっぱい出ていた。大きいものでも高さが15ミリくらい。クローズアップ撮影すると、毛に覆われた長い柄がたいへん美しい。 ここでもシロニセトマヤタケを見つけた。よく考えると、これは変な名前の付け方だと気づいた。「シロトマヤタケ」に対するニセなら「ニセシロトマヤタケ」が普通だし、この名前だと「ニセトマヤタケ」の白いものだとなるが「ニセトマヤタケ」という種はない。些細なことかもしれないが、ぜひ「標準和名」を妥当性のあるものに改めて欲しいと思う種名がいくつかある。 朽ちた切り株からニカワハリタケが出ていた。全体がゼラチン質で下面は細かな針状の柔らかい突起が密生する。別名「猫の舌」という通り、まったくよく似ていて実にうまいネーミングだ。 ようやく「きのこ狩り」対象のきのこヤマイグチを見つけた。といってもランクとしてはやや低いが・・・。ドッシリとしたきのこらしいきのこ形で、幼菌のスタイルは堂々たる存在感がある。採取して乾燥保存することにした。 午後には観光バスを連ねて団体客がどっと押し寄せてきて、清里駅の付近などはまるで都内の繁華街の様相になってきた。早めに退散する方が賢明と午後3時に現地を出発したが、それでも読みが甘くどこを走っても大渋滞の連続。結局6時間以上かけて帰ってきたので、今回の遠征で10時間以上も運転していたことになる。自分の体調も心配だが、地球温暖化阻止のためにもっと考えないといけないなぁ・・・と反省。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 8月23日(金) 富士山東麓・北麓 静岡県小山町 山梨県富士吉田市 |
世間一般より1週間遅い夏休みを取って、まず初日はやはり富士山へ行くことにした。先週は台風の接近もあってまとまった雨も降り、秋のような爽やかな気候になったのでベストコンディション・・・と思ったら、朝からすでに雨が降り始め、文字通り水をさされた格好だ。 まず向かったのは「ふじあざみライン」のカラマツ林。さっそくカラマツシメジの一群を発見。図鑑によると苦味があって食用にされないとあるが、まったく苦味はなかった。無毒なのだろうがカキシメジに似た雰囲気もあって、採取は見送ることにした。付近にはクサハツモドキもたくさん散生していた。雨でカサに強いヌメリが出て、美しい光沢が見られた。他には数種のアセタケ属やツルタケなどがあったが、雨が激しく降り始め、デジカメが心配になって撮影を中止した。 午後は場所を北麓のモミ林に移して探索。ここはまだ少し早いのか、ほとんどきのこが見つからない。ようやく大きめのきのこサマツモドキを発見。2本が株立ちする、このきのこらしい生え方だ。カサと柄の全面に赤紫の粒点があり、ヒダは鮮やかな山吹色。私はこの配色からいつもサツマイモを連想し、種名もサツマモドキと思っていたことがある。 2年前にGalleryのNo.5「オオキヌハダトマヤタケ」を撮ったすぐ近くの場所で、今度は白いアセタケ属を見つけた。シロニセトマヤタケだろうと思うが、根元にふくらみが無かったので少し疑問が残る。 モミ林に多くのきのこが顔を出すのは、9月中旬以降なのだろうか。深い霧が出始めて追われるように帰途についた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 8月18日(日) 丸太の森・三国峠 神奈川県南足柄市 |
前にも書いた「夏と秋のハザカイ期」なのか、それとも単に読みが外れたのか・・・。タップリ雨が降ったはずの「足柄森林公園・丸太の森」へ行ってみた。確かにスギ・ヒノキがメインの広い公園だったこともあるが、それにしてもまったくきのこが出ていない。 やっと見つけたのは切り株に生えたウチワタケだが、表面がきれいに波打っているので、団扇というより扇子の方がピッタリだ。 ハラタケ類ではアセタケの仲間が2種見つかったが、アセタケ属は図鑑たよりの種名の判定はたいへん難しい。1つはカサに粘性があり、柄の上部が微粉に覆われているので もう1つはシラゲアセタケでいいと思うのだが、これも似たものが多く図鑑によって図版のイメージがずい分異なるので決め手に欠ける。 午後は場所を変えることにして、神奈川、山梨、静岡の3県に接する三国峠へ行ってみた。「眺望抜群」の名所も台風13号の厚い雲で何も見えず、カラマツやコナラ、ミズナラの雑木林を探索したが、新鮮なきのこはツヤウチワタケくらいのもの。 落ち枝に群生しているフサヒメホウキタケを見つけることができた。先端部分がまだ開いていない状態で、平行して垂直に伸びる姿がきれいだ。 今年もまた、きのこの少ない年にならなければいいのだが・・・。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 8月17日(土) 高尾山 東京都八王子市 (神奈川キノコの会) |
これで2週間以上も雨が降ってないから、今日の勉強会も期待はできないと思っていたら、昨日になって電車が遅れるほどの大雨が降ったようだ。とは言え、たった一晩できのこが生えるものかどうか・・・。山頂から探索しながら降りてくることにした。 土はタップリと水を含み、木々や葉は瑞々しく、深い霧まで立ち込めると、きのこが無いわけがない・・・、と思ってしまうが、いくら目を凝らしても小さなきのこ1つ見つからない。やっとドクツルタケの仲間、ニオイドクツルタケ(仮称)が見つかったが、泥はねを被っているので雨の前から出ていたものだろう。 雨後に生えたものとしては、いがぐり頭の幼菌が見つかった。このスタイルの幼菌は似た種類が多いので難しいが、もう少し成長したのも採取されていてコシロオニタケと同定された。 伐採されたモミの断面から大きなツガサルノコシカケが出ていた。鮮やかなオレンジ色の環紋は遠くからでも見つけやすい。 「ドキッときのこ」としては、いくら平凡でも形のいいきのこが嬉しいわけで、その意味では、今日一番のきのこはこのツヤウチワタケなのかもしれない。 雨後2日目になる明日の方が期待できるのだろうが、探索場所の決定には大いに迷う所だ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 8月10日(土)-11日(日) 富士山北麓 山梨県上九一色村ほか |
7月の合宿勉強会でお世話になった「長岡きのこ同好会」の方々の希望もあり、富士山でのきのこ観察会を1泊2日で行った。初日は上九一色村の精進口登山道などを探索した。 残念ながら今週は雨がほとんど降らず、猛暑が続いたのできのこの発生は少なかった。ヒロハチチタケが多く見られたが、それに混じってアオゾメツチカブリが出ていた。傷つけると白い乳液を出すところはツチカブリにたいへんよく似ているが、名前の通り時間がたつとそれが青く変色する。青と言っても幅広いが、青灰色、やや緑がかった明るい青色だ。味は本種も強烈に辛い。 今年もまた、きれいなミヤマベニイグチが見られた。幼菌のときの濃いカサの色と、成菌との微妙な紅色の違いが分かる。もっとカサが開くとひび割れて、白い地色が見えてもっと淡い色になる。 根元が大きくふくらむタマシロオニタケを見つけた。強い毒性分を含んでいるようで猛毒きのことなっている。高さは約9センチ。全体が粉状の鱗片で覆われている。 翌日は雲ひとつない好天(我々にとっては好ましいとは言えないが)。まず、低地のポイント、青木ヶ原樹海の探索コースを歩く。あちこちにオニイグチが散生していた。オニイグチモドキとの見分けがはっきりせず、コオニイグチというのもあるので断定は難しいが、カサの鱗片が尖っていること、カサ表面の地色が白いことなどから、オニイグチでいいように思う。 先端のイボが妙に長く尖っているキイボカサタケを見つけた。黄と白の中間色をしたものを、ウスキイボカサタケとして別種にするということを聞いたが、赤・黄・白とも同種で単に色の変異だとする説もあるとか。どう落ち着くのやら・・・。 昨日のタマシロオニタケとよく似たきのこがあったが、柄の表皮がちぎれていたり根元の株に縦の亀裂が何本も入っていたりで、オニテングタケにもよく似ている。もっと成長すればはっきりするのだろうが、この仲間の幼菌はどれも似た形をしていて見分けがつきにくい。 午後は1,300m辺りまで登ってみたが、かなり気温も高く乾燥していて、目立ったきのこは発見できなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 8月 4日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
カミナリ三日の後は真夏の炎天下と、相場は決まっていると思っていたら、曇天で風も涼しく過ごしやすい1日だった。ところが、期待したテングタケ科もベニタケ科もまだ盛期ではなく、手応えのある写真が撮れなかった。 スジウチワタケモドキが珍しくきれいな形を見せてくれた。落ち枝にごく普通に生える堅いきのこで、カメラを向けることが少ないが、これはアマチャヅルの葉とのバランスが良かった。 コナラが中心の少し開けた林では、樹液に4匹のカブトムシが集まっていた。その近くできれいなベニタケが見つかった。ベニタケ科の同定はたいへん難しい。ベニタケ属かチチタケ属かまでは分かりやすいのだが・・・。これも柄に赤味があるのでドクベニタケではないが、チシオハツでいいのかどうか確信がない。血赤色というより明るい色だが、いずれにしてもベニタケがこんな無傷な状態で見つかることは滅多にない。 以前から、イグチ科の中で唯一ヒダのあるキヒダタケがなぜイグチ科に入っているのか不思議に思っていた。今日、何となく納得できた。カサを上から見た時、間違いなくイグチ科のきのこだろうと思って下面を見たら、鮮やかな黄色いヒダだった。逆に、なぜ管孔に進化しなかったのかが不思議になった。 いつになったら里山に、テングタケ科のきのこがいっぱい出るようになるのだろうか。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 8月 3日(土) 富士山東麓 ふじあざみライン 静岡県小山町 |
昨日は関東地方の広い範囲で、猛烈な雷雨があった。それまでは雨がほとんど降らず、今週はやや諦め気味だったが、一転して行き先をどこにするか大いに迷う結果となった。で、やはり避暑を兼ねた富士山ということにした。 まずは麓の林の中できれいなヒロハチチタケを見つけた。チチタケに比べるとカサの色が明るく、ヒダの数が少ない。どこを触ってもすぐに白い乳を出すのは同じだ。 ふじあざみラインに入ってまず、モミやダケカンバの多い森を探索してみた。キチチタケやキアシグロタケが多く、いい被写体が見つからない。なぜか雨後にしてはきのこが少ない。やっと、いいスタイルのフクロツルタケを見つけた。成菌ではひび割れ状の鱗片があまりきれいではないが、幼菌の時はなかなかきれいな姿だ。もう1種たくさん見られたのがクサハツモドキ。杏仁豆腐に良く似た独特の甘いにおいがする。 さらに高いところへ移動して、カラマツの多い林へ入ってみる。すぐにカラマツの根際に黄色い塊を発見。遠くからでもハナビラタケだと分かった。まだ若い状態で特有の花びら状ではないが、きれいな色でひときわ目立つきのこだ。 倒木や切り株からなにやら白いきのこが生えている。やや軟質で厚みがあり、管孔がたいへん細かい。図鑑で見る限りではツガマイタケのように思える。短い柄で木につながっているらしく、簡単に片手で剥ぎ取れる。管孔が非常に短いので断面では薄い皮のように見える。図鑑では「まれ」とのことだが、はっきりした特徴がなく断定ができない。 カミナリ三日の言葉どおり今日も雷雨になったので、危険を避けて早めに切り上げることにした。 *先日(7月25日)、大阪府のYさんから質問のあった紫色の不明菌は、Yさんにお願いして胞子紋と乾燥標本を作って送ってもらい、城川先生に検鏡していただいた。そして今日、城川先生からいただいた返事は驚くべきものだった。珍しいからではない。なんと「ミドリスギタケ」だったのだ。何度写真を見直してもとてもそうは思えないが、図鑑にカサの色が紫褐色のこともあるという記述もある。植木鉢に埋もれた針葉樹の木片からの発生とのこと。意外だった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |