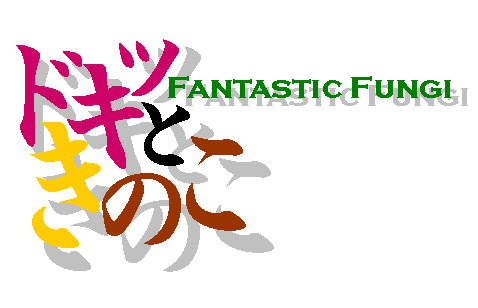 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2002年 10月 |
| 2002 | 2001年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2003年へ |
| 2002年 10月27日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
やっとデジカメが修理できて、久しぶりのMyデジカメでのきのこ撮影。横浜の新治市民の森での「10月定点観察」がキノコの会の観察会で流れたので、11月の予定を前倒しにして今日おこなった。 雨も降り、気温も下がって本格的な秋になったが、今年もきのこの多い年にはならないようだ。 スギなどの針葉樹の林でキツネノロウソクを見つけた。よく似た形態のきのこが数種類あって、見分ける特徴はなかなか覚えられないが、図鑑を片手に観察すると比較的同定はしやすいグループだ。しかし「キツネノ・・・」だけでもロウソク、タイマツ、エフデとあるので、覚えるのはたいへんだ。 落ち枝の下面からウラベニガサ属のきのこが出ていた。撮影時は分からなかったが後でよく観察すると、カサの中央部だけに濃い色のカスリ模様があった。フチドリウラベニタケなのかも知れない。 やっと少し大きなきのこを見つけることができた。フウセンタケ科はすぐに分かったがその先が難しい。カサと柄の上部に明るい藤色が見える。モリノフジイロタケのようだが、確定的なことは分からない。 昨日も雨が降ったのでやはりヒトヨタケ科のきのこが多い。畑の近くにサトイモが捨てられていて、そこからヒトヨタケ科のきれいなきのこが出ていた。これも同定が難しい。センボンクズタケにしてはカサが大きくて、ナヨタケにしてはカサの透明感が違うように思える。ヒトヨタケ科までしか分からない。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 10月20日(日) 相模原・木もれびの森 神奈川県相模原市 (神奈川キノコの会) |
デジカメを酷使したせいかUSB端子が故障してしまい、先週から修理に出しているので、ここしばらく「きのこ探索」を休んでいた。今日は会の勉強会なので同じ型のデジカメを持っている人に借りて、久しぶりの「きのこ撮影」をした。 一日中雨が降って寒いだろう・・・という予報は見事にハズレ、時おり薄日もさす穏やかな一日だった。ただ、昨夜まで強い雨だったのできのこは少ない。 さすがに成長の早いヒトヨタケの仲間はすでに出ていた。まず、その名の通り、カサ一面にキラキラした鱗片を付けたキララタケがたくさん見つかった。もう1種は朽ちた落ち枝から生えていたヒトヨタケ属で、ビロードヒトヨタケに似ているように思ったが、後の同定では属までとされた。 エゴノキにアラゲキクラゲが出ていて、まだ米粒ほどの幼菌から、もう黒くなってしまったものまで見ることができた。とても愉快な表情の幼菌が撮れたので、Galleryに入れることにする。 とても小さな白いきのこの柄の付け根に、まるでゼリーのような粘性の強い透明な液が付いている。ヌナワタケという変わった名前で面白い。ヌナワ(沼縄)とはジュンサイの別名とか・・・納得。 *10月6日に八菅山で採取された冬虫夏草はサナギタケではなく、たいへん珍しいアカイモムシタケの可能性が強いという調査結果を聞いた。貴重な写真になるのかも知れない。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 10月12日(土) 富士山南麓・水ヶ塚 静岡県裾野市 |
今週は雨が少なかった。気温も不安定で本格的な秋になりかけている時期なのか。里山ではあまり期待できそうにないので、富士山の南麓にある水ヶ塚へ行った。 笹薮が多いのであまりたくさんのきのこは見られないが、苔の生えた溶岩のガレ場ではいろいろ見つけることができた。今日最も多かったのがカベンタケ。苔の緑をバックにたいへん目立つきのこで、形も大きさもまちまちなのが面白い。大きいものは地上部だけで5センチを超えるものがあった。 もう1種、非常に多かったのがオニナラタケ。きのこの少ない年でも、この強いきのこには影響がないようだ。あちこちで大きな群生を見ることができた。ところが良く見ると、どうも違う種類が混じって生えている。カサ表面に鱗片がないので注意すれば分かるが、これはどうやらニガクリタケモドキのようだ。一見、大き目のニガクリタケに似ているが、かじってみるとまったく苦味がない。食菌らしいが、ヒダの硫黄色を見るとニガクリタケにそっくりなのでとても食べる気になれない。 苔に埋れるように、鮮やかな山吹色のきのこが生えている。カサの表面に細かなシワがあり、全体が微粉で覆われている。シワカラカサタケだ。少し触れるだけで柄の鱗片が取れてしまうので、なかなか思うように撮影ができない。目の粗いスギゴケの所でやっといい写真が撮れた。 ウラジロモミの若木が多い林で、出たばかりのきれいなチャナメツムタケを見つけた。まだ小型だが、富士山ではこれからの季節に多く発生する美味しいきのこだ。 そのすぐそばでいい色のモエギタケも出ていた。夏に多く見られたモエギタケはほとんど黄色ばかりで、名前の通り萌黄色をしたものを見るのは久しぶりだ。付近をくまなく探したが、朽ちた老菌があっただけで、1本だけの写真しか撮れなかった。 モミの林ならもうそろそろ出ているだろうと、狙いをつけて探したのがアカモミタケ。多くは見つからなかったが、鮮やかなオレンジ色がきれいなきのこだ。ただ、土や苔に埋もれていることが多く、カサ表面は白っぽく見えるので、すぐにアカモミタケとは分かりにくいが、これはこれで慣れるとピンと感じるものがある。同じチチタケ属のアカハツと非常によく似ているが、柄に楕円の紋があること、ヒダを傷つけると濃い橙色の乳を出すがアカハツのように青く変色しないことで見分けられる。 他にはフウセンタケの仲間や数種のシメジを見つけたが、どれも1本ずつで写真としては手応えがない。やはり今年もきのこ不作の年のようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 10月6日(日) 八菅山いこいの森公園 神奈川県愛川町 (神奈川キノコの会) |
なにを思ったのか、全幅の信頼を寄せていた我が竹ベンツのカーナビが、ずい分遠回りの道を選んでしまったために、同乗のK氏ともども集合時間に遅れてしまった。が、遅れても参加はできるので問題はない。 また少し汗ばむような気温になって、相変わらずきのこは少ない。木の根際に束生している大きなきのこがあって、カサや中空の柄の感じからクサウラベニタケと思ったが、撮影しながら良く見ると1個のカサに爪で押したような紋が見えた。ウラベニホテイシメジだった。「名人泣かせ」とはよく言ったもので、この日の鑑定会でも両種がたくさん採取され、分けられた後でも1本混じっていた。 草むらの中に姿のいい大型ヒトヨタケ科を見つけた。ミヤマザラミノヒトヨタケだ。カサの条線がとても美しいが、鑑定へ持ち込む頃にはもう真っ黒になっていた。 斜面に白いテングタケ科きのこを見つけた。どうせドクツルタケの仲間かと見るとカサの周囲にツボの破片が垂れ下がっている。最近、新種発表されたコトヒラシロテングタケだ。シロテングタケのようにカサに残ったツボの破片が黄色くはならない。 そのすぐ近くでシロソウメンタケ科のようなオレンジ色のきのこを発見。撮影後に採取して鑑定へ持ち込むと、なんと冬虫夏草のサナギタケだった。この仲間のきのこに興味が薄いため、うかつにも地上の子実体だけを採ってしまった。すぐに引き返して掘り出すと、菌糸に包まれた大きな虫が出てきた。図鑑によるとガ類のサナギから発生となっているが、宿主を良く見ると長さ5センチほどもある幼虫だった。サナギタケの近縁種という可能性もあるとのことだった。 ※後日、サナギタケではなく、たいへん珍しいベニイモムシタケの可能性が高いと教えていただいた。そうなら発見例が少なく貴重だとのこと。 【お知らせ】10月8日(火)の読売新聞夕刊に「IT関連」のコーナーがあり、「きのこ」の特集が組まれるらしい。当HP「ドキッときのこ」も掲載される予定なので、ぜひ、ご一読を・・・。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2002年 10月5日(土) 大志戸木の実の里 山梨県大和村 |
昨年9月にHPを通じて知り合って以来、時どききのこ探しに同行してくれて撮影のアシスタントをやってくれているR嬢と、大和村の竜門峡からさらに上にある大志戸木の実の里へ行った。昨年は台風の被害で車道が寸断されていたが、早くも復旧されて登って行くことができた。 ここでは昨年、ホンシメジ、バカマツタケ、コウタケなど、キノコ狩りの一級品が採取されたので期待して探索開始。ところが一級品どころか他の大きなきのこもほとんど見つからない。 ようやく鮮やかな色のドクベニタケを見つけた、ヒダも柄も真っ白なので種名はこれでいいと思うが、カサがやや橙色がかって見えるので少し疑問が残る。 落葉が厚く積もった斜面でホウキタケを発見。薄暗いせいで少し黄色っぽい色にも見えたが、撮影後に画像を確認すると白くて先端が赤く、まさにネズミの手のような形をしている。ホウキタケそのもので良さそうだ。 さらに登って行くと散策路の左側に、シラカバの混じる雑木林が続き、斜面にササクレフウセンタケが出ていた。カサも柄も細かいササクレに覆われて、柄の上部はササクレがなくわずかに紫色を帯びている。食菌だが旨みに欠けるようで、採取はしなかった。 斜面に取り付いて撮影をしながら、ふと下の方に目をやると、大きな赤いカサが点々と生えているのが見えた。なんとベニテングタケの群生だ。毒菌のためきのこ狩りでは見向きもされないが、私にとってはこれほど素晴らしい被写体はない。何カットもシャッターを切って、いつまでもその場を離れがたかった。本当に撮影し甲斐のある美しいきのこだ。 コウタケなどが出ていそうな雰囲気は十分にあったのだが、見つけることはできなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |