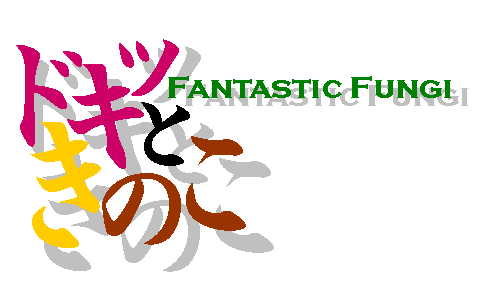 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2003年 4月 |
| 2003 | 2002年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2004年へ |
| 2003年 4月29日(火・祝) 有栖川宮記念公園 東京都港区 |
いつもホットな情報をいただいている「神奈川キノコの会」の中島氏から、いろんなタイプのアミガサタケが一つの公園内に出ていると聞き、案内していただいた。氏は近年、アミガサタケの分類に少なからず疑問を持ち、発生環境や生態的な成長過程を精力的に追跡しておられる。 この公園にはずい分大きなイチョウの木があり、早春に出るトガリアミガサタケに限らず、多くのタイプのアミガサタケがイチョウの樹下を好むらしい。まず、頭部が灰色がかったチャアミガサタケのようなタイプ。少し盛期は過ぎてしまっている。 大型の鮮やかな黄色タイプもたくさん出ていたが、驚いたのはその発生場所だ。岩や溶岩を積み上げた急斜面の岩の間から、高さ10〜15センチにもなる大きなアミガサタケが群生している。斜面にイチョウの木はないが、遊歩道を挟んだ斜面の上に大きな1本がそびえ立っている。氏の仮説では、雨水によってイチョウの成分が岩の間から染み出しているのではないかとのこと。アミガサタケのこんな写真が撮れるとは思ってもみなかった。 ウッドチップを敷き詰めた緩やかな傾斜地では、これこそ普通のアミガサタケだと思われるタイプが出ていた。 おかげで面白い写真を撮ることができた。さらにアミガサタケに興味のある方は、氏の個人サイトhttp://naknak1.hp.infoseek.co.jp/index.htmlを覗いて見ることをお勧めする。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2003年 4月27日(日) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
暑くもなく寒くもなく、風は爽やかで一年で最も過ごしやすい季節なのだろう。この公園のバーベキュー広場はまるで通勤ラッシュ並の混雑だった。 駐車場から近いスギ林の中にモリノカレバタケが群生していた。菌輪を描いているようにも見えるのだが、きれいな円になっているものは見つからなかった。栽培のエノキタケに似た歯ざわりのいい食菌らしいが、なぜかまだ食べたことがない。今日もたくさんあったのだが採取はしなかった。もう1種、多く見られたきのこはアシナガイタチタケだ。大きさはマチマチだったが、どれもクリ色のカサがとても美しい。 倒木や落枝を積み上げた付近から、赤紫色を帯びたイタチタケ型のきのこが出ていた。これはウスベニイタチタケでいいのだろうか。カサが独特の黒っぽい紅色で、今まで見た記憶がない。 開けた散策路のすぐ横に、大きなアミガサタケが10本ほどかたまって生えていた。撮影の間じゅう通りがかりの人に尋ねられる。高さはどれも10センチ以上ある大きなもので、主婦の方にミンチ詰めの料理を勧めておいた。もちろん生では中毒することも忘れずに付け加えた。今年のアミガサタケはどうやら、かなり大型の傾向のようだ。料理には好都合かも知れない。 倒木から群生している明るい褐色の硬質菌を見つけた。一見してスジウチワタケモドキかと思ったが、裏を見るとなんと網目になっている。ハチノスタケの群生だ。去年4月28日に高麗山でも同じものを見つけたが、どうしてもこれが、あの小枝に出るミカンの皮のような色のハチノスタケと同種とは信じ難い。ずい分雰囲気の違う生え方をするきのこだ。 その付近の苔むした針葉樹の倒木からは、褐色のチャワンタケが出ていた。クリイロチャワンタケの名前が浮かんだが、あれは地上から生えるので違う。材上生のこんなチャワンタケは、私の手持ちの図鑑には出てこない。苔むした倒木ということは、すでに材上とは言い切れないのかも知れない。 駐車場へ戻る途中、気になってシャクナゲ園を覗いてみたら、地上に小さなきのこを発見。なんと小型のハルシメジだ。付近を見回すと2m離れた所に、小さな梅の木が1本だけあった。納得。こんな小さいのが3本だけでは採取する気になれなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 4月26日(土) 芝公園 東京都港区 |
ずい分日が長くなったおかげで、仕事帰りに芝公園をのぞいてみても十分撮影可能な明るさだった。そして昨日から暖かい雨が降ったおかげで、ウッドチップを敷き詰めた一角には、きれいなキオキナタケが群生していた。 あまり大きくならないきのこかと思っていたが、中には直径7センチにもなるものがあった。カサの中心部に独特のシワ模様があり、特に幼菌では強い粘性がある。全体にきゃしゃな感じで、柄の表面がきれいなレモンイエローをしている。 一昨年にこの場所で見つけた時は6月22日だったから、2ヵ月も早い発生になる。今年はきのこの多い年だと期待していいのかも知れない。 |
 |
 |
||
| 2003年 4月20日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県大磯町 |
サクラの花もほとんど散って、ハルシメジも出始めた・・・というのに、今日は朝からの冷たい雨とともに冬が戻ってきた。北風も吹いて震えるほどの気温になってしまった。遠出を避けて1ヶ月ぶりの高麗山を歩いてみた。 湘南平からスタートしてすぐ、太いマツの切り株に良く目立つきれいなマツオウジの幼菌が出ていた。カサの表面にキャラメルを並べたような褐色の大きなひび割れがある。高麗山でよく見かける白いタイプのマツオウジだろうか。 自称「テングタケ通り」を歩くと、コナラの倒木にカサの直径10センチ以上あるウラベニガサが生えていた。こんなに大きくカサを開いてもまだヒダの肉色は薄く新鮮な状態だった。そのすぐ近くのサクラの落ち枝からはウスヒラタケが並んで生えていた。ヒラタケとの見分けが良く分からないが、色の薄さと言い、身の薄さと言い、雰囲気がウスヒラタケだ。 雨が一向に止みそうにないので、車で地獄沢へ回ることにして戻ると、なんと駐車場近くの生垣の下にチャアミガサタケが並んでいた。高さは4〜6センチと小ぶり。網目の窪んだ所の色が普通のアミガサタケより暗色で、コントラストがあって美しい。注意したつもりだったがレンズに雨滴がついてしまった。 地獄沢ではいつもヒトヨタケの仲間を見かける一帯で、1本だけのキララタケらしいきのこを見つけた。雨に濡れているのでカサの表面が光って、種名の判定は確かではない。ここではキララタケもコキララタケも出るので、どちらかだろうとは思うのだが。 一昨年の4月、ここの堰堤の上で私を驚かせたナラタケは、今年も元気な姿を見せてくれた。数は少なくなってきているものの、まだしばらくは春のナラタケを楽しませてもらえそうだ。 気温がこんなに下がっては、今日の雨もまだきのこの発生にはつながりそうにもない。梅雨に入るまではしばらくこんな気候が続くのだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 4月19日(土) 幕山公園 神奈川県湯河原町 |
「ハルシメジが出た!」という情報が伝わってきたので、昨年4月に撮った曽我梅林へ行ってみた。・・・が、なんとタッチの差で先客が採取の真っ最中。そうなれば、一昨年に撮った湯河原温泉近くの幕山公園へ行くしかない。 帽子どころか自分の体ごと飛ばされてしまいそうな、まるで台風でも来ているのでは・・・と思えるほどの猛烈な強風だ。しばらくは何も見つからず、ここはまだ少し時期が早いのかと思い始めた時、足元の草むらに半分干からびた1本を見つけた。こうなると俄然「きのこ目」がハルシメジモードに切り替わる。 大きな株状に生えたものや、その付近一帯に散生しているものなど、いい状態のシロを見つけることができた。 とても美味しいきのこなのだが、何度見ても毒菌のクサウラベニタケやイッポンシメジにそっくりで、春でなく梅の木の下でなかったらとても食べる気になれない姿だ。 |
 |
 |
||
| 2003年 4月13日(日) びわ青少年の森 神奈川県平塚市 |
昨日のウラベニガサとクサミノシカタケを撮影できたことから、びわの森のヒョウモンウラベニガサを思い出した。ひょっと群生でもしているのでは・・・と、予感めいたものを感じて行ってみた。 残念ながら一昨年の倒木は数個のカケラが残っているだけで、みごとに土に返ってしまった。近くの大きな倒木に菌糸が入っていれば嬉しいのだが。 春を通り過ぎて夏のような日差しになったので、昨日の雨はすっかり乾いてしまい、ほとんどきのこを見ることはできなかった。今日、唯一とも言うべき写真は大きなトガリアミガサタケ。雑木林の一部にだけ10本ほどがかたまっていて、道沿いの苔むした斜面からも15センチ以上もある大きなものが出ていた。オオトガリアミガサタケではないかとも思ったが、図鑑にも明確な相違点が記載されてないので不明。アミガサタケの仲間は分類に諸説あって、正確な同定が難しい。 |
 |
 |
||
| 2003年 4月12日(土) 寺家ふるさと村 神奈川県横浜市 |
はたして今日の天気予報は正しかったのかどうか、終わってみてもはっきり分からない。日中の雨はほとんど小ぬか雨で、傘がなくても困らない程度。夕方以降はまとまって降りだしたが、気温はかなり高めだった。 コナラの倒木にウラベニガサが生えていた。久しぶりに見るやや大きめのきのこだ。ヒダはまだ白っぽいがそれでも良く見るとピンク色が見える。 その近くには同様にコナラから1本のきのこが出ていたが、どうもウラベニガサとは違ってカサや柄にササクレがあって全体にしっかりしている。そしてムッとする妙な不快臭が確認できた。どうやらこれはクサミノシカタケのようだ。図鑑にニワトコの花のニオイとある。もしそうなら、かなり珍しい種類のようだ。 もう1種はやはりニオイで確認できるきのこは、最近よく見かけるアクニオイタケだ。均整の取れた姿で群生する様子は、いつ見てもバランスがよく絵になりやすい。 夜はかなり本降りになって気温も上がったので、明日以降はかなり期待できそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2003年 4月6日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
関東は今日が花見のピークだろうか。どこのサクラも満開で、もう散り始めている所も多い。新治もハイキングに来る人が多くなって、駐車場は満車状態だった。 どうやら今年はフクロシトネタケの当たり年なのか、先月からどこへ行っても見ることができる。ここ新治でもあちこちで見つけることができた。大きさは直径5〜6センチで子実面に凹凸がある。昨年まではこれほどの発生を見ていないので、大発生の周期があるのかも知れない。 もう1種、数ヵ所で見つけられたのは針葉樹の切り株や杭などから出ていたアクニオイタケだった。ニオイはカサを指先でつぶして確認するが、直後より1〜2分の時間をおいた方が強くなるように感じた。とても小さいがいい形をしているので、写真におさまりやすいきのこだと思う。 昨日の雨で出たのだろうか、新鮮なアシナガイタチタケがあった。柄のササクレはあまりなかったが、カサ表面の白い鱗片がはっきり見られる。 先月の観察で、ケコガサタケ属のような茶褐色のきのこを見つけて調べてもらったところ、チャムクエタケモドキだと判明したが、今日もまだ数本見ることができた。これがチャヒラタケ科というから驚きだ。毎年春に草の多い平地で、小さな落ち枝の端から発生しているのを見かけ、今までフウセンタケ科のケコガサタケ属だろうと思っていた。少し古くなって乾燥するとほとんど白っぽくなってしまい、カサの条線も消えてしまうので、なかなか同定の難しいきのこだ。 今年は何となく、きのこの発生が多いような嬉しい予感がするが、はたしてどうだろうか。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 4月5日(土) 『紺色のきのこ』続報 |
3月9日と3月21日に高麗山で見つけた「紺色のきのこ」と、3月30日に七沢森林公園で見つけた同種と思われるきのこが気になって、両方の写真と七沢で採取したものを城川会長に検鏡していただいた。 結果はなんと、コンイロイッポンシメジでもヒメコンイロイッポンシメジでもないとのこと。どちらとも胞子の大きさや形状が一致しないらしい。そして、ヒダの付き方が高麗山と七沢でも異なるようなので、これが同種という可能性も大いに疑わしいものになってきた。 取り急ぎの返事のため種名はまだ不明とのことだったが、七沢のタイプはヒダがはっきり垂生しているので、発表されている種があれば同定しやすいらしい。期待して待つことにしよう。 まだ他でも見つかるかも知れない。もっといい写真と、いい標本を入手したいきのこだ。 |
 |
 |
||
 |