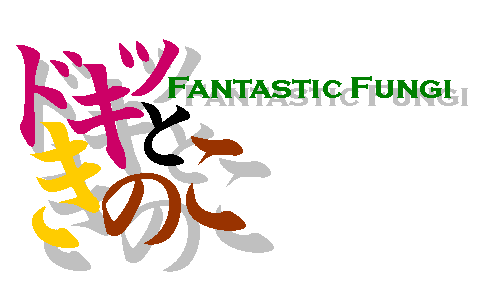 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2003年 11月 |
| 2003 | 2002年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2004年へ |
| 2003年 11月30日(日) 高麗山・湘南平 神奈川県大磯町 |
私にとって週末が悪天候になるのはたいへん困ったことなのだが、まさにこの週末はそうなってしまいそうだった。普段の季節なら少々の雨でも物ともせず撮影を敢行するところだが、この季節でドシャ降りでは出かける気にはなれない。 今日は少し雨が止むこともあるような予報だったので、最も近いフィールドの高麗山へ行ってみた。しばらく様子を伺っていると、なんと昼前には陽が差し始めた。急いで探索を始めた。 まず見つけたのはヒダが肉色をしたイッポンシメジ科のきのこ。どうやらクサウラベニタケのようだ。春のまだ寒い頃から出始めて、こんな晩秋まで生えている。 大きな木の根元にムササビタケが群生していた。これも真冬近くまで見ることができるきのこで、時どきニガクリタケと一緒に生えているのを見かける。カサの表面に細かなシワがある。 湘南平にある園芸花壇の中になにやら赤いものを見つけてよく見ると、初めて見るツノツマミタケだった。ツマミタケは何度も見ているが、図鑑にあるツノツマミタケがはたして確固とした別種なのだろうかと疑問に思っていた。やはり今まで見たツマミタケとは違うはっきりした「ツノ」を持っていることが分かった。 最後はやはりこの時期にも元気なニガクリタケのきれいな姿を見つけた。そばにあった幼菌はかなり赤味の強いカサなので、これだけを見ると同定を誤るかも知れない。もっともこんな幼菌を採取することもないだろうが・・・。 撮影断念を覚悟していただけに、思わぬいい被写体に気を良くして帰った。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月23日(日) びわ青少年の家 神奈川県平塚市 |
地元の探索ポイントとしては「高麗山」についで、期待の持てる面白い場所がここ「びわの森」だ。今までにも色いろいい写真を撮ることができている。 事務所へあいさつの後、探索を開始。すぐに落ち葉の多い斜面で、黒いカサの群生を見つけた。採取して見ると裏は明るい灰色でシワ状の脈が密に走っている。アクイロウスタケだが、昨日のものよりはるかに大きく広い範囲に群生している。図鑑によれば「ややまれ」なきのこらしいが、突発的に多く発生するのだろうか。 その同じ斜面に枯葉に埋もれた黄色いきのこを見つけた。慎重に葉を除くと3本並んでいた。傷んだ所が黒く変色しているので 苔の間からいくつもツチグリが顔を出していた。古くなって泥まみれになったのも多かったが、新鮮なときの銀色の輝きはいつ見ても美しい。 枯葉が多くなるときのこ探しは困難になるが、この色は見つけやすい。まだ幼菌だが明るい紫色が目に飛び込んできた。ムラサキシメジだ。根元が大きく膨らんでカサが強く巻き込んでいる。 最後にまた、アカヤマタケを見つけたと思って枯葉をはらいながら良く見ると、どこにも黒変しているところがない。おなじヌメリガサ科でもこれは種類が違う。カサに粘性がなく柄にも繊維状の筋が見られない。となるとベニヤマタケということになりそうだが、こんなに黄色いタイプもあっていいのだろうか。 気温が下がっていよいよ冬に突入のようだが、まだまだ面白いきのこは見られそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月22日(土) こども自然公園 神奈川県横浜市 |
今日から3連休。しかも時期的に紅葉の最盛期。・・・となればどの方面へ向かうにしても渋滞は避けられない。さらに今日は気持ちよく晴れ渡った行楽日和になったので、遠征は諦めて近くの里山を探索することにした。 さいわい雨はまとまって降ったので新鮮なきのこは見られるだろうと思った。高さ1メートルほどのアカマツの切り株に、鮮やかなオレンジ色のきのこが群生している。マツに生えるオレンジ色の群生小型菌といえばヒメカバイロタケだ。カサが開ききったものが密生しているので、良く見るとヒダの重なりが美しく、ヒダの間の細かな脈まではっきり見ることができた。 付近の倒木にはニガクリタケが出ていた。これから真冬になっても新鮮な群生を見ることができる。死亡例があるほどの猛毒きのこだが、かじってみればかなり苦いので同定は難しくない。 斜面にアクイロウスタケが生えていた。今までも何度か見かけたが、なかなか写真向きのいい状態がなかった。これもまだ成菌にはなっていない感じだが、カサ裏の色やシワの状態はよく特徴が出ている。色調がクロラッパタケとよく似ているがはっきりしたシワがあるので区別しやすい。 結局、あまり大きなきのこは見つけられなかったが、気候も良く、色づき始めたモミジも見ながらゆったり探索を楽しむことができた。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2003年 11月16日(日) 高麗山 神奈川県大磯町 |
昨夜からかなり雨が降り続いたようだったが、未明には止んでいた。きのこは雨が降ったからといってすぐに生える訳でもないが、ヒトヨタケ科のきのこぐらいは出ているかも知れないと、いつもの高麗山で湘南平から探索を開始した。 風が強く、北から突風が吹き荒れるときもあったが、どういう訳か気温が高くまったく寒くなかった。 まず見つけたのはコツブヒメヒガサヒトヨタケという長い名前のきのこ。カサの直径が2センチ位で中央がオレンジ色をしているが、ローアングルからカサ裏を見上げるように撮ると、ヒダが離生しているのでオレンジ色がリング状に透けて見えてとても美しい。 近くの朽ちた木からは褐色のカサのきのこが、きれいな状態で生えていた。イタチタケともムササビタケとも思えるきのこで、種名ははっきり分からなかった。ナヨタケ属であることは間違いないと思うのだが。 しばらく尾根筋を歩くと朽ち果てた倒木の内側に、重なって生えているきのこがあった。カサを上から見ただけでその独特の色からハイイロイタチタケだと分かった。開いたカサの下に幼菌が隠れるように生えていて、いい雰囲気の写真が撮れた。 やはり初めの予想通り、これまでみたものはすべてヒトヨタケ科だったが、「けやきの広場」へ下りてくると、苔の生えた倒木に鮮やかな山吹色のきのこが生えていた。これだけを見るとベニヒダタケのように見えるが、付近に生えているほかのきのこを調べるとすべてヒイロベニヒダタケだった。これもきっとそうなのだろう。やはりこの2種を外見だけで見分けるのは難しい。 午後からは風も止んで穏やかになったが、気温は逆に下がりだして肌寒くなった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月15日(土) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
今週に入って急に晩秋らしく、朝夕が肌寒くなってきた。これからは霜が降りることが多くなるので、しばらくは晩秋のきのこが楽しめそうだ。 あちこちからはムラサキシメジの噂が聞こえるようになってきたので、シロのある七沢森林公園へ行ってみた。 きれいな星型に開いたツチグリを見つけた。黒く朽ちてしまったものはよく見かけるが、久しぶりにひび割れ模様のきれいな写真が撮れた。内皮にはまだ穴があいていない新鮮なものだった。 沢沿いに落ちた枝にシロホウライタケのような小型のきのこが生えていたが、少し感じが違う。ヒダを見るとかなり激しく脈になってつながっている。柄の根元に色がついているのでホウライタケ属だとは思うのだが。 大きな切り株の周囲にびっしりと小さなきのこが密集している。イヌセンボンタケだ。全体を見るとやや不気味に感じるが、一部分をクローズアップすると、これはこれでなかなかきれいなきのこだと思う。 ムラサキシメジの生えるポイントへ向かっていくと、散策路のわきにオレンジ色の大きなきのこが出ている。これはどう見てもアカモミタケなのだが、この場所にモミがあっただろうかと周囲を探すと、かなり離れた所に若木が1本だけ立っていた。その付近でも老菌が2〜3本見つかった。 実はムラサキシメジの紫色の濃い幼菌か若い個体を狙ったのだが、今日ここで見つけたものは、サイズこそかなり大きいもののすべてカサの開ききった成菌だった。成菌になると色が褪せてしまい、淡褐色になってしまうものが多い。ところがなぜか1本だけ大きくカサを開きながら、みごとな紫色を見せているものがあった。さすがに中央は褐色だが、周辺やヒダはきれいな紫色をしている。 沢沿いのコースではクルミタケと思われる直径2〜3センチのきのこを見つけたが、半分に切ってみると中がほとんど空洞でシワ状の壁がない。先日の飯山観音で城川会長から説明のあったウツロイモタケという種類だろうか。付近には中央に穴のあいたものもあったが、同種かどうかはっきりしない。いずれにしても子嚢菌の仲間には間違いなさそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月 9日(日) 南高尾 東京都八王子市 |
朝から深い霧が立ち込めて、小ぬか雨が降ったりしてかなり初冬らしい気温になってきた。 初めて南高尾の尾根筋を歩いてみたがほとんどきのこを見つけられず、今日は諦めて帰ろうかと考え始めたとき、足元の赤や黄に色づいた落葉にまぎれてオレンジ色のカサが目に付いた。ひょっとしてと周囲を見回すと確かにモミの木が立っている。柄を良く見ると濃いオレンジ色のあばた模様もある。アカモミタケだ。注意深く周囲を探すとさらに1〜2本。少し歩いて別のモミの周囲にも2〜3本見つけることができた。天ぷらなどの油料理でたいへん美味しいきのこなので採取することにした。 後は沢沿いに降りてきてきれいなコキララタケを見つけることができたが、今日は良く歩いた割にはきのこの種類が少なかった。 |
 |
 |
||
| 2003年 11月 8日(土) 伊豆・一碧湖 静岡県伊東市 |
今年の5月に訪れた時は寒い雨が降っていたが、3度目の訪問となる今回はいい天候に恵まれた。ただ、どういう訳か11月も中旬になるというのに、気温は20度を超える汗ばむような日が多い。今年は夏が無かったが、この分では冬も無いのではないだろうか。 湖の周遊散策コースを歩き始めてすぐにホウキタケの仲間を見つけた。色から判断するとキホウキタケのように思えるが、この仲間は似た種類が多いらしくいまだに分類が判然としないようだ。 しばらく進むと道のわきの少し開けた所に、褐色の環紋のあるチチタケ属のきのこがいくつも生えていた。傷をつけると白い乳が出てやがて黄色っぽくなる。キチチタケかと思ったが、味を確かめると辛味は無く弱い渋味や苦味を感じる。どうやらチョウジチチタケのようだ。チョウジのニオイを正確に知らないのではっきりしないが、確かに表現の難しい独特のニオイは感じた。 ベニタケ科は夏に多いきのこなのに、まだ生えているのかと思ったら、なんとテングタケ科のきのこも生えていた。カサにツボの破片を付けて、薄い黄色のツバがしっかり付いている。コタマゴテングタケだ。異常に気温が高いせいで今ごろまで生えているのだろう。 きれいにカサが反り返ったヒトヨタケ科のきのこを見つけた。柄に細かな毛が生えているのでザラエノヒトヨタケでいいのだろう。根元には小さな幼菌も出ていていい写真が撮れた。 暦の上では今日は「立冬」とのことだが、いつになったら寒くなるのだろうか。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月 3日(月・祝) 飯山観音 神奈川県厚木市 (神奈川キノコの会) |
今年最後の野外勉強会は昨年同様、厚木市の飯山観音で開催された。実は以前から「ヤマヒル情報」が乱れ飛んで、みんな一様にヒル対策に頭を悩ませていた。おまけに今日は朝からあいにくの・・・ヒルにとっては絶好の雨。私はやられた経験がないので、取り敢えずは長靴で探索するぐらいの手しか打たなかった。探索をはじめる頃には雨も止み、薄日が差すほどになった。 人それぞれになぜか「縁の薄いきのこ」というものがあるようで、私はどういう訳か今まで満足なコガネタケを見ていなかった。今年はたくさん出ているというので期待していたら、W女史が藪の中のきれいなコガネタケを見つけた。ヒルなど恐れている場合ではない。やっとまともな写真を撮ることができた。 その後はなるべくジメジメした所を避けて、落ち枝に生えたチシオタケや、いたるところに群生していたニガクリタケなどを撮っていた。 間伐材を積んだ所から一本だけウラベニガサ科のきのこが出ていた。柄は白地に黒の繊維模様があり、カサが異常に黒く、つやのない細かな凹凸がある。気になってポケットミラーを使ってヒダを見ると、くっきりとした黒い縁取りが見えた。久しぶりに見るクロフチシカタケだ。ルーペで見ると思わず歓声を上げてしまうほどきれいな縁取りを持っている。 春にアミガサタケの撮影でお世話になった中島氏が、トリュフを見つけたので案内してくれるという。今年は各地でたくさん見つかっているようだが、私はまったくトリュフを見つける目になっていないので、「ここだよ」と指差されてもまだ見えなかった。氏が見つけて半分に切った1個も借りて撮影。ニオイはあまり強くないが、私にはややコウタケに似た醤油様の香りと思えた。標準和名はイボセイヨウショウロで、どうやら日本でもこの他数種類のトリュフが見つかっているようだ。 結局、何人かの参加者はヤマヒルにやられたようだったが、私はその姿すら見ることがなかった。大騒ぎした割には・・・と思いながら帰宅してから着替えてチェックしても無傷。何気なく腕時計を外すと、なんと、ベルトの下に血が滲んでいる。まったく気づかれることなくどこにでも潜り込む、すごい能力だと感心してしまった。 ※10月26日の高麗山でフミヅキタケとして掲載したものは誤りで、正しくは「ツチイチメガサ」だと山口氏(リンク:キノコのホームページ)に教えていただいた。特徴として、柄が細く柄の中ほどに条線のあるツバがある、とのことだった。 ご指摘ありがとうございました。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月 2日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
横浜市にも一昨日の夜に雨が降ったようで、先月に比べればかなりいい状態になっていた。少しはきのこの種類も期待できそうだと思った。 やはり駐車場のすぐ近くには、相変わらずヒトヨタケが元気にたくさん出ていたが、今日はそれに混じってきれいなムジナタケが見られた。いつもあまりいい状態を見ていないのでこのチャンスにしっかり撮っておく。 もう1種すぐそばにクリイロカラカサタケによく似たきのこが群生していたが、カサや柄のひび割れ状になった鱗片の間の地の部分に、たいへん良く目立つ独特の赤い色が見える。成菌になってもヒダの色が白いことからハラタケ科キツネノカラカサ属になるとのことだったが種名は分からない。はっきりした特徴を持っているので何とか名前を知りたいと思うきのこだ。 斜面にアカヤマタケが生えていた。一見ヒイロウラベニガサによく似ているが、地面から生えていることや、カサにも柄にもヌメリがあるので区別できる。手で触れたり老菌になると黒く変色する。カサの色は普通鮮やかな赤の場合が多いが、時どき黄色や黒いオリーブ色のタイプもある。すぐ横にその黒いタイプが出ていたが、これだけを見るときっと種名を悩んでしまうだろう。 竹やぶに入ると何カ所かでムラサキシメジを見つけることができた。いつもコムラサキシメジとの見分け方で論議を呼ぶが、結局はっきりしないままになっている。柄の根元が太くなることやヒダが極めて密であることなどで、今日のものはムラサキシメジで良さそうだ。 旭谷戸へ行くと湿地状の低地にある倒木にヌメリスギタケモドキが生えていた。かなり柄が細いので疑問が残るが、以前にも同じ場所で採取したので間違いないだろう。幼菌もいくつも出ていて昨日の富士山のスギタケモドキとした幼菌とそっくりだが、これはカサに強い粘性があるのでやはりヌメリスギタケモドキの幼菌だと思う。 畑の近くの野菜が捨てられた所にきれいなヒトヨタケ科のきのこが生えていた。カサや柄に細かな綿毛状の鱗片が付いていて、カサの中央にわずかな褐色の鱗片が見える。図鑑で見るとヒダヒトヨタケモドキにとてもよく似ている。わずかな風にもいつまでもユラユラ揺れるので、撮影にかなりの根気を要する。何とか止まってくれた1枚だ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2003年 11月 1日(土) 富士山南麓・西臼塚 静岡県富士宮市 |
今年は夏以降ほとんど富士山へ行く機会がなかった。愛車「竹ベンツ」の調子が悪かったのも理由の一つだが、あまりいいきのこが出ているというウワサが聞こえなかったのも事実だ。本来なら10月から11月にかけては「きのこのベストシーズン」なのだから、久しぶりに南麓の西臼塚近辺を探索してみることにした。 折りしも今日から3連休で秋の行楽シーズン真っ只中。渋滞が耐えられない私は、当然のことに昨日の夜に出発して「竹ベンツ・ビバーク」。そして早朝から探索して午後早めに帰路に着くプランにした。 夜中に降った激しい雨は明け方には小降りになり、次第に空が明るくなる絶好の撮影日和となった。ブナの大木が多いこの付近では、林内いたるところにウスキブナノミタケが生えている。カサの黄色にはさまざまな色の濃さがあり、きれいな山吹色からほとんど白色まで入り混じっている。なるべくいい色のものを選んで撮影。 もう一種同じようにあちこちの地面に見られたのは、スックと姿勢を正して直立しているようなアシナガタケだ。1本では絵になりにくいが群生するとどのアングルを選んでも構図を決めやすい。 ブナの大きな倒木にはビッシリと苔が取り付き、そこにムササビタケが群生する。この付近ではあちこちの倒木で見ることができた。すでに枯れたきのこも混じっているので、繰り返し群生するのだろう。 小型のきのこしか見つからず不満に思っていると、倒木の下にやや大きな白いきのこを見つけた。が、種名が分からない。採取してカサの表面をルーペで見るとかすかに、しかし紛れもなく大理石模様が見えた。ブナシメジだ。栽培されてすっかりお馴染みのきのこだが、野生のものはなかなか見られない。大きさもまずまずだったので採取することにした。 倒木に小さなきのこの群生を見ると、つい「またムササビか?」と思ってしまうが、カサが黄色いものがあった。一見してニガクリタケに見えるが、まったく苦味がない。ニガクリタケモドキだ。カサが開ききる前がやや赤味があること以外は本当にそっくりだ。 カサの表面にトゲ状の突起が密生している小さな幼菌があった。見たところヌメリがなさそうなのでスギタケモドキの幼菌のようだ。初めて見るきのこで近くにはほんの少し大きなものもあった。 枯れ葉とみごとなコントラストを見せている、きれいなカサを見つけた。ヒトヨタケ科でヒメヒガサヒトヨタケのように見えるが自信はない。雨に打たれて砕け散っているカサもこのきのこらしい姿だ。 もう昼近くになってそろそろ切り上げるつもりでいると、最後にナラタケの大きな群生にめぐり会えた。新鮮な株を選んで撮影。普通のナラタケよりかなり黄色みが強いので、これはキツブナラタケではないだろうか。状態がよかったのでこれも今日の収穫に加えることにした。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |