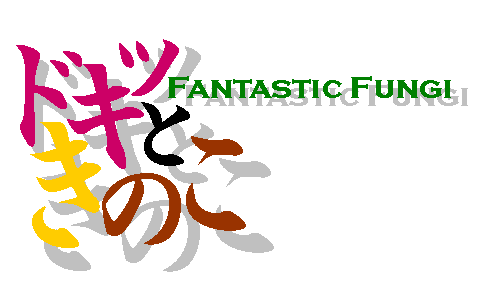 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2005年 11月 |
| 2005 | 2004年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2006年へ |
| 2005年 11月27日(日) 茅ヶ崎里山公園 神奈川県茅ヶ崎市 |
隣の茅ヶ崎市にも探索に適した自然公園がないものかとネット検索していて、今まさに造成中という里山公園を見つけた。まだ予定の半分ほどしか開園していないが、それでも池や森を散策できそうなので行ってみることにした。 せせらぎ沿いの低地を中心に3時間ほど歩いたが、もう大きなきのこはあるはずがない。開けた草地に視線を這わせて小型菌を探してみた。 するとすぐに、形のいい2本が見つかった。またあやふやな同定だが、これはツチイチメガサで良さそうだ。ツバの条線がくっきり見えて、褐色の胞子が載っている。 撮影しながら低い視線で周囲を見ると、きっと立っていては見つけられなかっただろうアシナガタケがあった。地味なカサは落葉にとけ込み、針のような細い柄は近づいてもよく見えない。撮影後にカサのニオイを確認したが薬品臭はなかった。 池の近くまで来ると、直径4センチほどのカサが3つくっついていた。地面から生えているように見えたが、よく見ると埋もれ木からのようで、付近の落ち枝にも萎れたものがいくつかあった。黒っぽいビロード状の柄をしているので、これはエノキタケだ。同じ材上生でも木のどの位置に生えるかでずいぶん形が変わるものだ。 スギ・ヒノキ林の中にコケの生えた大きな切り株があり、そこにナラタケの幼菌の株がいくつも生えていた。この時期でまだ幼菌がたくさんある。今年はずいぶん遅くまでナラタケを見る。 この公園もいい季節にまた訪れたいところだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月23日(水・祝) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
そろそろ慢性病になってしまっている風邪と決別すべく、暖かくして部屋にこもっていようかとも考えたが、これからはますますきのこの姿が見られなくなるのだから、震えるほども寒くない日はたとえ短時間でも歩きたくなる。 尾根筋を避けて「沢のさんぽみち」コースを選んだが、それでもきのこは見つからない。斜面の低いところに、やっと小さなカサを見つけた。色から判断してヒメキシメジだろう。撮影のためにしゃがみこむと、付近には小さなきのこがいくつか見つかる。ところが小型や極小という言葉も通り越して「微細」なきのこなので、撮影してもピント合わせや光のバランスがうまく行かない。 今日はEOSを使わないかも知れないと思いながら沢沿いを歩くと、落ち枝に少し傷んだハチノスタケを見つけた。もう萎れていて撮る気になれなかったが、そのオレンジ色のカサ越しにいくつもの灰色のカサが見えた。なんと、とても新鮮なヒラタケの幼菌だった。倒木や枝が絡み合ってとても撮りづらい場所で、三脚の足のやり場に苦慮していると、もう少しで三脚の足を置いてしまうところに小さなきのこが1本だけ生えていた。 ツチイチメガサか?とも思ったが何となく様子が違う。これはフミヅキタケではないだろうか。雰囲気やイメージだけでの同定だから、極めてあやふやだ。 大きなモミの樹下にたくさん群生しているきのこがあった。大きいものでカサの直径が7センチほど。オオキヌハダトマヤタケのようだ。 後は尾根筋からコナラの斜面を通ったが、まったくきのこが見つからなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月20日(日) 伊豆・一碧湖 静岡県伊東市 |
予定が昨日と逆になってしまったが今日、朝7時に出発して「伊豆の瞳」一碧湖へ行ってきた。9時に着いた頃はほとんど人がいなかったが、そろそろ紅葉も見頃を迎えているので、時間とともにどんどん人が増えてきた。 探索を始めてしばらくはわずかなニガクリタケくらいしか見つからず、いよいよ空振りになる日が多くなるのかと考えていた。 ところが散策路のすぐ脇に、カサに黒いカスリ模様がある1本を見つけて、よく見るとシモフリシメジだった。これが1本だけということはないはず・・・と、付近を注意深く探すと、その一帯に大小取り混ぜて30本ほど生えていた。 さらに斜面を登って行くと、コナラの立ち枯れた根元に今年初めて群生を見るナラタケが生えていた。やや小ぶりだがとても新鮮な状態だ。 優秀食菌が続いて見つかり、しかも群生だったことに気をよくして歩いていると、倒木をたくさん積み上げた中にエノキタケの群生もあった。大きな木が邪魔をして思うように撮影できなかったが、虫ピンほどの幼菌の塊もあってこれから盛期を迎えるようだった。 湖畔の道が工事中だったので半周で折り返したが、不思議に同じ道でも新たに見つけることが多い。優秀食菌ではなかったが、典型的なクヌギタケのきれいな状態を見つけることができた。 期待が薄かっただけに、楽しい撮影に満足して帰途についた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月19日(土) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
寒くなったので南国伊豆の一碧湖へ久しぶりに行くことに決めて、早朝目を覚ました。・・・のだが、「あと5分だけ」と目を閉じたら瞬時に2時間が過ぎてしまった。仕方なく明日に予定していた泉の森公園へ行くことにした。 一面にユキノシタが広がるところに点々と茶褐色のカサが見つかった。カサの中央が色濃く縁に向けて白っぽくなっている。柄を覗きこむと特徴のあるツバが見えた。柄の真ん中あたりにしっかりしたつばが残るツチイチメガサだ。初冬に姿を見せて、春ごろまで見ることができる冬型のきのこだ。 スギの材を積み上げた近くには、カサがじょうご型になった小さなきのこがあった。特徴に乏しい姿なのですぐには名前が分からなかったが、カヤタケ型のスタイルとカサの中央が乾いて白くなっているので、コカブイヌシメジではないかとニオイを確かめた。やはり、はっきり分かる桜餅のニオイだった。 太い倒木にオレンジ色の菌糸がべったり付いていたので、丁寧に周辺を探すとやはりコキララタケがいくつも生えていた。ちょうどカサを開き切ったいい状態のものや、萎れ始めて面白いスタイルになったものなど、いい被写体があった。 そのすぐ近くの地上からはヒダヒトヨタケモドキが群生していて、もうほとんど萎れたものばかりだった。何とかいい状態のものを見つけて撮っていると、すぐ横には頭を出したばかりの毛むくじゃらの幼菌があった。 どれも小型なりに、この季節にしてはいい状態のきのこが見られた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月13日(日) 地獄沢・高麗山 神奈川県平塚市 |
いかにきのこに最適の「雨後二日目」といえども、もうこの季節では尾根筋を歩いても被写体は見つからないだろう。そこで、いつも歩くコースとは逆に地獄沢から入って探索することにした。 それでもなかなか見つからなかったが、沢に落ちた太い木に奇妙な形のものが背着していた。今まで新鮮な状態をなかなか見ることができなかったヒダキクラゲだ。背着している姿はキクラゲ科と言われればそう思えなくもないが、これが成長してカサを作ると、まるでサルノコシカケの仲間のようになる。不思議な姿のきのこだ。 堰堤の上には太い丸太が積み上げられていて、そこにヒラタケの幼菌を見つけた。まだカサの幅が数ミリしかないが、これも冬によく見かける美味しいきのこだ。残念ながら成菌を見つけることはできなかった。 斜面の低いところに栗色のヌメリの強いきのこが生えていた。もうこの時季は地上生のきのこは珍しい。しっかりしたツバがあるのでツチナメコではないかと思うが、小さくてよく分からない。 小さいきのこばかり見つかるので今日はクローズアップレンズを付けたままでいいと思ったら、針葉樹の倒木に大きめのきのこを発見。黄色地に赤紫の粒点が広がる独特のカサはサマツモドキだ。カサ径約6センチ。付近にはきれいな幼菌も並んでいた。期待以上のいい被写体に角度を変えて何枚もシャッターを切った。 さらにもう1種、ウッドチップを敷き詰めた道に立派な姿を見つけた。すぐには種名が分からなかったが、ヒダを見ると淡いピンク色が見える。どうやらウラベニガサそのもののようだ。 コースの選択は正解だったようで、帰路の尾根筋では何も見つけることができなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月12日(土) 藤沢市少年の森 神奈川県藤沢市 |
昨日たまたま藤沢市の地図を見ていて、面白そうな公園を見つけた。あまり広くはないがキャンプ場、アスレチック、自然散策路などがある。そこで、シーズンも終わり近いので新規開拓のつもりで行ってみた。 よく整備された散策路は歩きやすく、手付かずの自然もうまく残されている。駐車場から入り口を過ぎてすぐに、杉林の横を抜けて自然散策路を歩いた。 地面はたっぷり湿っているがこれは昨夜降った雨だからきのこは期待できない。それでもすぐに、ヒトヨタケ科の中型のカサを見つけた。種名がよく分からなかったが、撮影しながらカサが光を反射するのが見えた。よく見ると表面の鱗片がキラキラ光っている。どうやらキララタケのようだが、カサの直径が3センチ以上もあって単生しているのでそれらしくない。帰る時にもう一度見ると、4時間ほどの経過でもうカサの液化が始まっていた。 落葉がフカフカに堆積したところにコノハシメジがたくさん生えていた。カサは直径3センチほどでどれも小さいが、水分の多いカサや白いヒダが独特で分かりやすい。 立ち枯れたコナラの根元に小さな白っぽいきのこが生えている。カサの中央に尖った鱗片があり、白いしっかりしたツバがある。ナラタケなのだが、それにしても小さい。今年はドキッとするような群生を見なかった。 アスレチック広場に並べられた丸太に、ヌメリのあるきのこが生えていた。いよいよシーズンが始まったエノキタケだ。いくつも出ていたが雨に打たれて泥だらけだった。来週あたりからあちこちでたくさん見られるだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月 6日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
先月の定点観察会でカヤタケ属と思われるきのこの撮影をしたときに、カメラからアングルファインダーを外してベストのポケットへ入れた。そのとき、しっかりポケットを閉じなかったので落とすかも知れないというイヤな予感がした。案の定、そのときに紛失してしまっていた。 そして今日、どうしても気になって同じコースを歩き、予感のポイントを探したが見つからない。すると、3週間前に自分が歩いた場所を少しずつ思い出した。そしてなんと、まさかと思いながら探した杉林の中にそれはあった。私にとっては今日一番の「ドキッと」な発見だった。 先月のハタケシメジのあったところに、まだ黒いタイプの幼菌がいくつか出ていた。ローアングルの撮影がこんなに楽だということを、ファインダーの発見で再認識できた。 すぐ横には頭を出したばかりのスッポンタケがあった。グレバの緑色はこういう新鮮なときしか見られない。付近には卵?がいくつかあったが大きさにずいぶん差があったので、同種かどうかが気になった。 もう何度も書いた愚痴なのだが、何年間も毎週のようにきのこ探しをしているにもかかわらず、未だかつて自分で見つけたコガネタケは去年11月の飯山観音での幼菌1本だけ。そして今日も生えている場所まで案内してもらって、群生している幼菌を撮影した。もうピークは過ぎたのかコガネタケらしくない柄の短いものが多かったが、それでも形のいい幼菌を撮ることができた。自分で発見する群生はいつのことになるやら・・・。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月 5日(土) 富士山南麓 静岡県富士宮市 |
富士山の山頂付近にいつの間にか雪が積もっている。もうそろそろきのこも終盤に差し掛かっているので、今年最後になるかも知れない富士山の南麓へ行ってきた。 もう「きのこ狩り」に来る人も減ったことだろうと思っていたら、なんと紅葉がちょうど見ごろになっていて「もみじ狩り」の車が多かった。 晩秋のきのこクリタケぐらい見つかればいいな、と思っていたら探索を始めていきなり、大きな切り株に生えていた。数は多くないが新鮮できれいな姿だった。 別の切り株には周囲を取り巻くように、センボンクズタケの株がいくつも並んでいた。小さなカサが密集して束生する独特の生え方でとても種名が分かりやすい。あまり見かけないが、出るときは大発生になる。 今日もっとも多く見かけたのはオツネンタケモドキだった。大きなブナの倒木には必ずと言っていいほど生えていた。群生していると何か別の食菌かと期待してしまうが、裏はヒダがなくて肉質も薄くて硬い。 この時期はもう枯葉が積もっているので、地上生のきのこはたいへん見つけづらい。細長いきのこが3本立っていたので、てっきりここでよく見かけるアシナガタケだと思った。ところがよく見ると柄が鮮やかなオレンジ色をしている。ヒダを覗き込んで驚いた。かねてより見たいと切望していたアカチシオタケだった。思ったよりカサの色が地味で分からなかったが、周囲を探すと赤いシミを持ったカサも見つかった。もっと鮮やかな色を見たかったが、それでも初めて見るきのこは嬉しいものだ。 前に「遊々きのこ」のフジタケさんに案内していただいた時に、ブナの倒木の下側にブナシメジが出ていたが、今日、同じ場所でたくさん並んでいるのを見つけた。よく見るとカサの中央にはっきり大理石模様が見える。栽培品に比べると遥かに大きくて白く、とても瑞々しいきのこだ。 同じように倒木の下側に毒きのこのツキヨタケが出ていた。見慣れてくるとカサの色や模様ですぐに見分けることができるが、常にこんな色という訳でもないようなので用心は必要だ。 そして、そのツキヨタケに似ているとされるムキタケも見つかった。コケの色に似た緑色の強いオリーブ色をしていた。4個しかなかったがカサが大きくて肉厚だったのでいただくことにした。 優秀な食菌も少し採ることができたので、「もみじ狩り」の帰宅ラッシュに巻き込まれないように午後早く帰途についた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 11月 3日(木・祝) 八菅山いこいの森 神奈川県愛川町 (神奈川キノコの会勉強会) |
本年最後の「神奈川キノコの会」の野外勉強会が行われた。ようやく秋深くなって汗をかくこともなく、きのこ探しと撮影にはとてもありがたい気候になってきた。 ところが、もうきのこの季節が終盤に差し掛かったのか、鑑定場所に持ち込まれた種類も量も少なくて、サイズも小型のものが多かった。 写真の被写体に良さそうなものがなかなか見つからなかったが、形が面白いのでアシボソノボリリュウタケを撮った。とてももろいきのこで、うかつに触るとすぐに壊れてしまう。 道のすぐ脇にきれいなアカモミタケが生えていた。付近一帯には太いモミが数本あり、他にもたくさん見つかっていたようだ。 採取されたものの中に興味深い種類があった。今年の3月に「遊々きのこ」に出ていたクロコバンタケという種類で、5月にここへきたときに見つけて写真を撮っていた。採取されたものは同じ木に出ていたもので、コナラの硬い樹皮を破り開いて生えている。半年を経過してやっとこの大きさだから、とても成長が遅い種類のようだ。 エノキタケの小さな幼菌が見つかったので、いよいよ冬のきのこの出番が近いと実感した。 |
 |
 |
||
 |