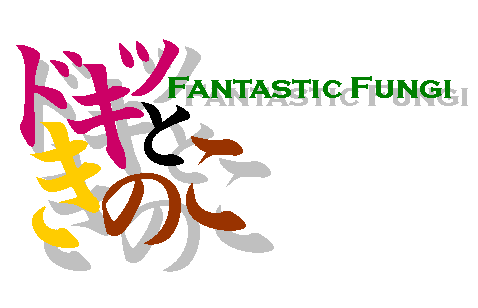 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2005年 7月 |
| 2005 | 2004年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2006年へ |
| 2005年 7月31日(日) 相模原・木もれびの森 神奈川県相模原市 寺家ふるさと村 神奈川県横浜市 |
昨日の状態から考えてより多くのきのこと出会うためには、広大で平坦な森をひたすら歩くしかないと判断して、相模原市にある中央緑地「木もれびの森」を選んだ。 やはりきのこは少ない。傷んでしまったベニタケ科の仲間が多い中、いい状態のテングタケ科を見つけた。ヒメコナカブリツルタケが2本並んでいた。カサの表面が細かな粉で覆われているので、いつもピント合わせに悩まされるきのこだ。 落ち枝に小さなダイダイガサのイガイガ頭を見つけた。しょっちゅう見るきのこだがいい状態を見つけるとやり過ごすことができない。とても絵になるきのこだ。 流れる汗に悩まされながら構図を決めていると、そこへ「寺家ふるさと村」にいる菌友から携帯電話が入った。「こっちへおいでよ、何にもないけど・・・」とのお誘いだが、こんな時は一人より複数の目の方が面白いものが見つかるに違いない。硬質菌に詳しいK氏にも会えるので、この場所で見つけた分からないきのこも見てもらうことにした。 それは散策路脇に横たえた針葉樹(スギ?)の材から生えたサルノコシカケ型のきのこで、まるでスポンジのように柔らかく裏は管孔ではなく長い針状のものが密生している。K氏いわく、同公園などで2〜3回見たことのあるオガサワラハリヒラタケとのこと。素晴らしい記憶力にただただ脱帽。 合流したときはちょうどきれいなイグチが見つかって、みんなで撮影しているところだった。紫色のビロード状がとてもきれいなブドウニガイグチだ。幼菌も揃っていていい写真が撮れた。 もう1種きれいなハラタケ科のきのこが見つかった。一見してザラエノハラタケだと思えるのだが、何となく色が明るいのと柄にも褐色の鱗片が付いている。どうやらザラエノハラタケそのもではなさそうだ。いったい図鑑に載っている以外に何種類のきのこが存在するのだろう。気が遠くなりそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月30日(土) 高麗山 神奈川県平塚市 |
きのこが多く発生する時季になってくると、1週間どころか数日できのこの種類が入れ替わってしまう場合がある。そんな訳で今月に入ってから足しげく高麗山へ行っているのだが、今日は運悪くきのこの端境期に当たってしまったようだ。 小さなきのこもほとんど見つけられない中で、驚いたことにカバイロツルタケの新鮮な2本が並んでいた。1本はまだ袋から顔を出したばかりの幼菌で、とてもきれいな色を撮ることができた。 倒木から華やかな色のきのこが出ていた。カサの条線がとても美しいベニヒダタケの群生だった。樹皮が邪魔をして得意のローアングルが狙えないので、逆にカサの美しさを真上から撮ってみた。 地面から生えた見慣れない姿のものを見つけた。見たところ冬虫夏草の仲間のようだ。あまりこの仲間に強い興味がないのだが、こんな色のものを図鑑で見た記憶がなかったので念のため記録した。掘り出すと白い膜に覆われた何かのさなぎのようなものが現れた。土を落として標本撮影したが、後で図鑑を見ても同定できなかった。 帰り間際、階段の脇に小さな真っ白いきのこを発見。カサの中央に深い穴が通っているラッパ型。その名もユキラッパタケだ。強い日差しに透けたヒダがとてもきれいだった。 曇ってはいたが気温と湿度は高く、いわゆる不快指数というヤツが高かったに違いない。きのこが少ないのだから無駄な悪あがきは諦めたが、明日はどうしたものか・・・。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月24日(日) 鎌倉中央公園 神奈川県鎌倉市 (神奈川キノコの会勉強会) |
前々から気にはなっていたのだが、「神奈川キノコの会」の野外勉強会に参加するときも、ついついいつもの調子で撮影をメインにしてしまうので採取する点数も少なくなる。せっかくの勉強会なのだから他の参加者に負けないくらいいい標本をたくさん採取して、より多くの知識を得なければいけないと思った。 そんな理由から撮影も記録程度に・・・と決めて歩くのだが、やはりきれいなきのこを見つけると好みのアングルを探してしまう。 先週は雨が少なく地面はかなり乾いた状態だったが、それでもいくつかは興味深いきのこを見つけることができた。斜面にオニイグチの仲間が1本だけ出ていて、モドキが付くのかどうかが分からなかったが、後の鑑定会でカサの鱗片が尖っていないことからオニイグチとされた。 一面にドクダミが生えた中に、1本だけきれいなヒトヨタケ科のきのこが立っていた。こういうのを見るとどうしても記録写真では気が納まらない。得意の超ローアングルで狙ってみる。これはザラエノヒトヨタケのようだ。 もう1種は時どき見かけるのだが名前が分からなかったきのこで、今日やっと高橋春樹さんによって1999年に発表されたアミガサホウライタケだと分かった。カサの中央に不規則なシワがあるのが特徴で、ヒダはオオホウライタケよりやや多い。 これからも採集と撮影の両立に悩まされそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2005年 7月23日(土) 富士山北麓 山梨県鳴沢村 |
関東の梅雨も明けて本格的な夏が始まろうとしているが、このところあまり暑くない日が続いている。雨が少なくては里山のきのこも中休みの状態だろうと、富士山まで足を延ばした。前回より少し標高を上げて、1,300m辺りのウラジロモミやカラマツの多い一帯を探索してみた。 朝から濃い霧が立ち込めて、到着した頃には大粒の雨まで降り出してしまったが、幸いにも雨は1時間ほどで止んでくれた。ところが、この辺りはまだ少し早すぎたようで、あまり多くのきのこを見ることはできなかった。 まだ雨が降る中、最初に見つけたのは高さが4センチほどの小さなハナホウキタケだった。まるで珊瑚を見るような色と形はとても写真向きだが、種の同定は極めて難しいらしい。 真っ白なヒラタケ型のきのこがいくつも見えて、てっきり昨年の有毒騒ぎの主スギヒラタケだと思い込んで撮影していた。ところが広葉樹に生えていたり、カサの表面が灰色になったものもあり、やっとウスヒラタケであることに気づいた。外見ではちょっと見分けにくい場合があることを改めて知った。 きっとたくさんのタマゴタケに出会えると思っていたが、朽ちたのを数えても数本しか見つからなかった。それに小型のものばかりで、最もきれいだった写真の1本も高さは8センチほどだった。 道の脇にまるで動物のフンのような灰色の変な塊を見つけて、よく見てみるとクロノボリリュウタケの頭部だった。何とも奇妙な形をしているのでとてもきのこだとは思えないが、低いアングルで見ると見覚えのある姿が分かってくる。 例によって渋滞を避けて早めに帰途に着いたが、今日はそれがとても幸運だった。帰り着いてすぐに大きな地震があった。東京で震度5強。高速道路の通行止めを免れることができた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月18日(月・祝) 高麗山・子供の森 神奈川県平塚市 |
朝から晴れて気温がグングン上がっていく。きのこ探索は朝の涼しい間に・・・などと悠長なことを考えていたら、午前7時の時点ですでに30度を超えていた。蚊が大嫌いなので真夏でも長袖を着ているが、今日は短時間だけと決めてポロシャツに虫除けスプレーをたっぷり吹き付けて探索開始。 入り口ですぐに灰色の小さなきのこを見つけた。カサの表面に粉がいっぱい付いている。形こそ小型だがテングタケ科のヒメコナカブリツルタケだ。柄は真っ白でツバはなく、根元にカサと同色の膨らみがある。 昨日同様、ドクツルタケの仲間が多いのだが、この広い斜面にはベニタケ科の種類がたくさん出るようだ。 とてもきれいな黄色のウコンハツが1本だけ出ていた。カサの中央はやや赤味が強くなり、柄も下へ向かって同じように赤くなる。ヒダは真っ白できれいなコントラストを見せる。 同じベニタケ属でカサの模様が面白いオキナクサハツが、広い範囲に群生していた。有毒で不快臭もあり極めて辛いという「きのこ狩り」の嫌われ者だが、カサの表皮の裂け方が独特で、群生しているとなかなかきれいなパターンになる。 撮影を終了して駐車場へ戻ると、斜面にきれいなきのこが生えていた。カサが明るい橙黄色でヒダと柄が鮮やかなレモン色。ヒダに傷をつけると見る見る白い乳液を出す。これが「神奈川キノコの会」で仮称がつけられているレモンチチタケに違いない。付近には幼菌から大きなものまで10個ほどが群生していた。ヒロハチチタケともチリメンチチタケとも違う特徴で、名前も覚えやすい。 今日見つけた中で名前の分からない2種を掲載しておく。特徴がはっきりしているのに図鑑で見当たらない。 1種目は高さが2センチほどの小さなもので、キツネノカラカサ属だと思うのだが、こんなしっかりした鈎針状のトゲを密生しているのは初めて見た。 もう1種は階段の材木から生えていて、これも見覚えがない姿だ。同じ材からクロサカズキシメジも出ていたが、これは色も大きさも全く異なる。 今日、関東は梅雨が明けたらしいが、いま里山はきのこが多く観察も撮影もたっぷり楽しませてくれる。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月17日(日) 高麗山・湘南平 神奈川県平塚市 |
3連休はどこか遠くへ・・・と、行きたいところだったが、初日の昨日は出勤日。そして、連休の後半にはお決まりの交通渋滞と考えると、今日から遠征というのも気が進まない。「やめておけ!」と持病の腰痛も訴えている。 となれば、このところまともに歩いてない高麗山の「テングタケ通り」あたりがちょうどいい。きっと、テングタケの仲間で賑わっているに違いない。 そんなことを考えながら湘南平へ向かって運転していると、右目の隅にチラッと白いきのこが2個並んでいるのが見えた。急いで停車して戻ると真っ白なテングタケ科のきのこだった。いわゆるドクツルタケの仲間だ。結局今日はこの種類が最も多く見られた。と言うよりこの色だから最も目立ったということか。 遊具のある斜面ではカバイロツルタケが出ていた。ツルタケと区別できないようなタイプもあるが、ここに出るものは根元のツボまでほとんど同じ明るい褐色をしているので分かりやすい。 この季節になると、カビに侵されたイグチやベニタケをたくさん見かけるので、これもまた黄色いカビにやられたきのこかと思ったら、ずいぶん立派なキイロイグチだった。普段小さなものしか見かけないが、これはカサの直径が5センチ近くあった。 テングタケ通り(自称)へ差し掛かるとやはり目立つのはドクツルタケの仲間だが、それに混じって見かけないきのこを見つけた。イグチなのだがカサがシワだらけで柄が真っ白。ヤマイグチ属の特徴なので図鑑を調べると、どうやらシロヤマイグチらしい。初めて見るきのこだ。幼菌の時だけカサが褐色で次第に白くなるらしい。 やはり「テングタケ通り」の主役タマゴタケは出ていた。それもカサの直径が15センチを超える堂々たる姿。付近にはいくつか生えていたがあまり多いとは言えない。 明日はこの山の「こどもの森」を探索してみよう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月10日(日) びわ・地獄沢 神奈川県平塚市 |
昨日の夕方から降り出した雨は、深夜にはまるで台風でも来ているのかと思うほどの嵐になっていた。朝にはもう止んでいたが、これではどんなきれいなきのこも泥跳ねまみれになっているだろう。 そこで、最近気になっていた2ヵ所へ、目的を絞って確認に行ってきた。 まず、リンクHP「貴美子・水彩画・きのこ」のKimikoさんから、横浜の寺家ふるさと村でコガネハナガサを見つけたとの情報をいただいたので、以前見つけた「びわ青少年の家」付近の場所をチェックした。 残念ながらコガネハナガサは発見できなかったが、きれいなクリイロイグチがたくさん出ていた。まさに栗色のカサと柄の間に、真っ白な管孔がとてもきれいで印象的だ。 さらに付近の竹薮では数本のキヌガサタケも見つけることができた。残念ながら昨日生えたものらしく、雨に打たれてすっかり白くなってしまっていた。グレバのあった頭部は網目になった残骸となっていたが、独特の悪臭だけはしっかり漂っていた。 もう一つの気がかりは、高麗山の地獄沢で見られるヤグラタケだ。あちこちでクロハツが終りかけているのでそろそろ出ているに違いない。 読みは的中した。地獄沢から登る道の一本は「クロハツ坂」とでも名付けたいほど、点々と大きなクロハツが束生している。目的のヤグラタケはすぐに見つかった。何しろ真っ黒に朽ちたクロハツに真っ白のきのこだから、極めて見つけやすい。 同じ場所にスミゾメヤマイグチも出ていた。この柄は雨による泥跳ねもほとんど影響なし。元から泥跳ねを被っているような柄だ。 午後は晴れて気温も一気に上昇。滝のような雨の後は滝のような汗だ。健康のためきのこの見過ぎにも注意しよう。(例えが古いか・・・。) |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月 9日(土) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
神奈川キノコの会では今日から静岡県の椹島で宿泊勉強会が行われているのだが、今年は残念ながら都合により参加できなかった。そこで、多分きのこがたくさん出ていると予想されるこの場所で、ひたすらマイペースできのこ撮影を楽しむことにした。 目当ては去年、大群生していて斜面が赤く染まった(?)というタマゴタケだ。もうそろそろ出始める頃だろう。 最初に目に付いたのはとても細長いきゃしゃなきのこだった。キツネノハナガサが一本だけ立っていた。幸い今日は全くの無風状態だから、揺れに悩まされることはない。カサが開き切って反り返ったとても新鮮な状態で、レモンイエローの条線が鮮やかに見える。 すぐ近くには同じキツネのつくキツネノカラカサが、これもとてもきれいな状態で生えていた。柄にいくつも水滴をつけている。しっかりしたツバに黒い縁取りが付いている。 夏になるとテングタケの仲間がたくさん出始めるが、真っ白でとても目を引くのがドクツルタケの仲間だ。近い種類が数種あって見分けが難しい。あやふやな同定をするよりドクツルタケの仲間としておく方がよさそうだ。どの道、猛毒には違いない。 カサの直径が10センチ以上もある大きなきのこを見つけたが、覗き込んでも柄が見つからない。よく見ると倒れ掛かっていて後ろに細い柄が見つかった。これは時どき勉強会でも採取される特大のツエタケだ。普段見るツエタケと比べるととても同種とは思えない。形態的な分類で考えるとオオツエタケと名付けて別種とすべきだろうと思う。当然、柄も長くて全体では高さが25センチほどになる。カラカサタケと肩を並べる大きさだ。 次も立派な大きさのきのこが立っていた。膜質の大きなツバが垂れ下がる姿はテングタケの仲間だろう。全体に赤っぽく見えるのでこれはガンタケだろう。なかなかきれいな姿に出会えないでいたが、ようやく傷んでいないガンタケを撮ることができた。 午後になって雲が厚くなり始め、森の中はピント合わせが困難になるほど暗くなってきた。そんな時になって色のきれいなきのこが見つかるのは皮肉だが、何とか長時間露光で自然な色を出すようにした。 まず、カサや柄にオレンジ色の粉をまぶしたようなカバイロコナテングタケ。まだカサの開いてない幼菌だが、このままの色で大きくなるきれいなテングタケの仲間だ。 斜面の下のほうにかすかに赤いカサが見えた。今日の第一目標だったタマゴタケをようやく見つけた。まだ、群生とはいかないが今年も一面のタマゴタケが見られるかも知れない。きれいな幼菌も見つけることができた。 もうほとんど撮影困難なほど暗くなって、今にも雨粒が落ちて来そうになってから、石垣の間にきれいなイグチを見つけた。カサに細かなひび割れがあり地色が赤い。これがキッコウアワタケかと思ったが、あまりにカサの紅色が鮮やか過ぎる。管孔を爪でこすって変化を見たが、5分経っても全く変色しない。どうやらこれはミヤマベニイグチのようだ。これも今まで富士山の樹海でしか見たことがないので、こんな里山に生えるきのこだとは思っていなかった。 ついに大粒の雨が落ちてきた。一目散に車に戻って、本日の撮影は終了。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月 3日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
今日の定点観察会もきっとたくさんのきのこが見られるに違いない。参加したメンバー6人とも同じ思いだっただろう。 確かに多くの種類を見ることができたが、名前の分からないものもいくつも見つかるのでなかなか前へ進まない。みんなで採取したものを同定すれば時間は節約できるが、生えている状態や生態写真を撮ることができなくなる。やはり時間がかかってもその場で見ることが大切なポイントだと思う。 今日、見られた中で印象に残るものをピックアップしてみると、まず、この森で初めて見るヒロヒダタケモドキだ。今まで富士山でしか見たことがなかったので、高山性のきのこだと思い込んでいた。 いつもイグチの仲間が何種も見られる場所に行ってみると、全体が青紫色の柄の太いきのこが出ていた。一昨年にここで見られたフウセンタケ科のアイカシワギタケだ。まれなきのこなのだろうか、図鑑などで写真を見たことがない。一昨年の成菌での検鏡で同定されたきのこだ。これもデジカメで正確な色が出にくいタイプで、独特の深い青紫はどうやっても撮ることができなかった。 同じ斜面で見慣れないイグチが見つかった。「ニガイグチモドキだ」いや「ウツロイイグチでは?」と意見が飛び交ったが、傷ついた部分がゆっくり青変することが分かり、アイゾメクロイグチに落ち着いた。味は全く苦味がなく、むしろ弱い甘味を感じた。 夕方近くになり駐車場へ戻ってから、きれいなテングタケ科のきのこが見つかった。テングタケにしてはカサの色が薄すぎる。ウスキテングタケに似ているが細かな点で疑問が残る。 いろいろ同定で悩むのが面白く楽しいことであるのは認めるが、はっきりしないのがいくつも現れると不満がつのることも事実だ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2005年 7月 2日(土) 富士山北麓・創造の森 山梨県富士吉田市 |
長い間、乾燥状態の続いていた富士山北麓にもようやくタップリの雨が降った。不満をつのらせていたきのこ達が一気に爆発している・・・・・・に違いない。そう思いながら富士山へ向かった。 東富士五湖道路の富士吉田I.C.を出ると、いつも必ずチェックするポイントがある。料金所を出てすぐ左側にウッドチップを敷き詰めた一角があり、特に雨の後はかなり面白い探索場所なのだ。そこですぐに見つけたのは、か細いヒトヨタケ科のきのこ。ヒメヒガサヒトヨタケだろうと思うが、コツブヒメヒガサヒトヨタケとは見分けが付かない。きれいな状態だったので超ローアングルも撮った。 もう1種、茶褐色の背の高いきのこが出ていたが、ツバを見ればすぐに種名が分かる。以前にも何度か見ているサケツバタケだ。もう盛期を過ぎたせいか前よりかなり小さくなっていた。 場所を「創造の森」へ移して、アカマツとカラマツの混じる森を探索した。散策路脇の木にいくつもマツオウジが生えていたが、よく見るとはっきりツバがある。カラマツなどに時どき、しっかりしたツバのあるマツオウジが生えるようで、別種としてツバマツオウジと名付けられていると聞いたことがある。 この森にはずいぶん大きなヒロヒダタケが生える。2002年6月末に霧をバックに撮った1点をGalleryに入れている。今日もあちこちで大きなカサを見ることができた。 とても小さな真っ白のカサを見つけて、しゃがみこんでよく見ると柄に細かな粉が付いているように見える。名前もそのままのシロコナカブリだ。ピントを取るのが難しいが、きれいに撮れるきのこなので気に入っている。 小さなシロコナカブリを撮り終えて痛む背筋を伸ばしたとき、ドキッとするきのこが目に飛び込んできた。そう言えば5年ほど前、この場所でサッカーボール大のハナビラタケを見たが、あれは確か9月だった。こんな早い時期にも生えるとは知らなかった。強い雨に打たれたようで少し傷んでいたが、まだまだ被写体に十分な姿を保っていた。 さらに道を挟んだ北側のカラマツ林を歩いてみたが、いかにもきのこがありそうな雰囲気にもかかわらず、ほとんど出ていなかった。 やっと見つけたのはアセタケ属の新鮮なきのこで、カサの細かなササクレの様子からオオキヌハダトマヤタケだろうと思う。柄が白くてしっかりしたきれいなきのこなのだが、これをはじめこのグループは有毒の種が多いのが残念だ。 ここは何もないから諦めて車に戻ろうとしたとき、朽ちた切り株に冬虫夏草のアリタケを見つけた。雨に洗われたのだろうか、全くゴミの付いてない状態でそのまま丁寧に標本撮影することができた。アリの脚も触覚も欠けることなくきれいに揃った状態だった。 久しぶりに変化に富んだ撮影内容になり、いささか疲れたので早めに切り上げて退散した。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |