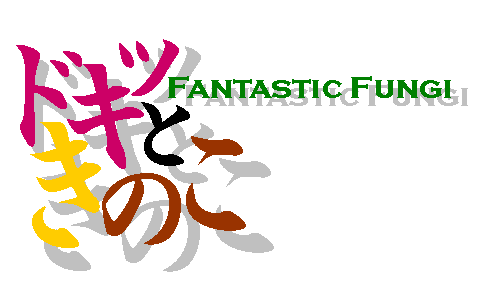 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2006年 2月 |
| 2006 | 2005年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2007年へ |
| 2006年 2月26日(日) 平塚市上吉沢 神奈川県平塚市 |
このところ寒暖の差がとても激しくて、体調を維持するのに一苦労といった感がある。立体マスクを付けている人がとても多いが、まだ花粉が多くなっていないので、やはり風邪引きかその予防なのだろう。 今にも雨が降りそうだったので、最も近い探索地の一つ「びわ青少年の家」へ向かった。途中の農道にあった大きな倒木に、きのこらしきものを見つけて急停車。近づいてみるとスエヒロタケの群生だった。キクラゲ同様、雨が降るととても元気になるきのこだ。 撮影の途中から冷たい雨が降り始め、数カット撮ったところでかなり本降りになってしまった。これでは「びわ」へ行っても撮影が困難だと判断し、以前から取り上げようと考えていたある話題を掲載することにした。 特にきのこグッズを集めている訳ではないが、ネクタイを選ぶ時にはつい「きのこ柄」を探してしまう。実は駅前の千円ネクタイでたいへん興味深いものを見つけた。なんとモグラが巣穴から顔を出している傍らに、柄の長いきのこが生えているではないか。これはきのこ通ならすぐに分かる「ナガエノスギタケ」だ。 ネクタイのデザイナーが知っていたかどうかは不明だが、何かの写真をモチーフにデザインしたのかも知れない。一度は見たいと思っているきのこをこんなところで見るとは思わなかった。 |
 |
 |
||
| 2006年 2月19日(日) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
この一週間はずいぶん気温が高くなり暖かい雨も降った。にもかかわらず金曜になってまた冬に逆戻りをしてしまったようだ。まだ2月の中旬だから寒いのが普通なのかも知れない。 極小菌でもいいから「きのこ型」に期待して、七沢森林公園を探索してみた。枝や倒木を積み上げたところはかなり湿り気があったので、丹念に探してみたが何ひとつ「きのこ型」を見つけられなかった。 やっと新鮮な状態を見つけたのはヒメキクラゲだった。真っ黒いぶよぶよした塊が枝を覆っていた。 もう1種、同じ仲間のタマキクラゲも元気だった。こちらは褐色の半透明で1個ずつ独立したものが並んでいた。キクラゲの仲間は季節に関係なく、雨さえ降ればたくさん生えるようだ。 朽ちた木の塊に小さな円盤が密生していた。かなり色が薄いが黄色っぽく見える。最大限にクローズアップして撮影してみると、円盤は皿型から茶碗型になっていて外側が粉状に見える。柄はまったくないのでハイイロクズチャワンタケが近いのだろうか。直径は大きいものでも2ミリほどだった。 昨日テレビで「春の足音が聞こえる」と言っていたが、私は耳が遠くなってしまったのだろうか・・・? |
 |
 |
||
 |
||
| 2006年 2月12日(日) こども自然公園 神奈川県横浜市 |
免許証の書き換え期間が誕生日の前後2ヶ月間に延びたのはいいが、のんびりしているとかえって忘れそうになるため今日済ませてきた。「優良ドライバー(?)」のおかげで手続き時間が短くてありがたいのだが、逆に待ち時間の方が長かったのは何とかならないものだろうか。 E5000だけを持って来たので午後は近くの公園を散歩してみたが、多少でも湿り気のあるような場所でもきのこは見つからず、名所の梅園はまだまだつぼみが固いので本当の散歩になってしまった。 腰掛け用に置かれた太い丸太にエノキタケを見つけたが、すっかり干からびて撮る気になれなかった。むしろすぐ横の大きなカワラタケの方が新鮮で、表面の密毛が日差しを受けて輝いていた。 折れた長い枝にかなり赤いカサの硬質菌が生えていた。環紋が色鮮やかなエゴノキタケだった。裏面のヒダはまるで迷路のような模様で、カサよりはるかに大きな面積になっていた。 園内にはたくさんのツバキもあったのだが、今日はなるべく樹下を避けて歩いた。 |
 |
 |
||
| 2006年 2月11日(土・祝) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
日中の日差しが暖かく日ごとに春の気配を感じるが、本格的な春の訪れまでにはまだ数回の寒波が襲ってくるに違いない。もうそろそろ「冬きのこ」以外の小さなものでも見つかるだろうと、地獄沢から丹念に探し始めた。 枯木に出ているヒラタケのようなきのこはなんだろう・・・と、近づいてよく観察するのだが、1個だけしかなくてよく分からない。カサの柄に近いところが独特の三角になっているのでどうやらヒラタケそのもので良さそうだ。 「けやきの広場」まで来ると、ヤブツバキの樹下に枯葉を払い除けた跡があった。だれかツバキキンカクチャワンタケを探したのだろうか。その付近にはなかったが、別の木の下でいくつかを見つけることができた。 スギの切り株にはヒメカバイロタケモドキが群生していた。中にはカサの直径が1センチ近い大きなものまであって、元気な群生だった。 今日、最もたくさん見かけたのはやはり「冬きのこ」の代表、エノキタケだった。今まで高麗山にはあまり出ないと思っていたが、去年あたりからずいぶん立派な株を見かけるようになった。 今、「写真資料館」の各種のページに過去の「きのこ探して」の写真をリンクさせる作業を進めているが、種類が限られている冬の時期にエノキタケが極端に多いことが分かった。他に無いのだから当然かも知れないが、それにしても圧倒的に登場回数が多い。通年撮影をしている結果だろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 2月 5日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
今日は晴れるという予報だったので昨日以上に乾燥が進むだろうと思ったら、なんと朝は2〜3センチの雪が積もっていた。気温もかなり低いままなので、うまくいけばいい写真が撮れそうだ。・・・きのこがあればの話だが。 いくつもの切り株にはエノキタケが生えていたが、どれも厚く積もった枯葉に埋もれていて被写体にはイマイチというのが多かった。 倒れたコナラにたくさんのカサが見えて雪を被っている。種名は分からないがとりあえずそのままを撮影。後で調べたらヤケイロタケだった。硬質菌の雪のシーンも種類によってはいいかも知れない。 そろそろあちこちでツバキキンカクチャワンタケが出始めているので、当然いつも姿を見せるヤブツバキの下にもあるはずだ、と探したがなかなか見つからない。ここはちょっと遅いのかと諦めかけたとき、足元に直径2ミリほどの小さな円が見えた。「あったぞ!」・・・きのこは極小でも声は大きい。 昼食を摂る「いけぶち広場」では太い丸太に大き目のエノキタケが生えていて、うっすらと雪を被っていた。地面の雪がレフ版の代わりをしてくれるので撮影が楽でいい。 それにしても「冬きのこ」は、たとえ凍ってしまってもまた溶けて成長するのだから、驚くべき生命力を感じる。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2006年 2月 4日(土) 飯山観音 神奈川県厚木市 |
昨日の夕方から探索場所をいろいろと考えてみるのだが、どこの風景を思い浮かべてみてもきのこが浮かんで来ない。今朝になってもまだ、行き先を決めかねていた。沢があってなるべく倒木の多い所・・・ふと飯山観音を思い出して、「そうだ、この時期なら苦手のヤマヒルがいない!」 3日前に降った雨は焼け石に水だったのか、もうすでに地表は乾いていてカサカサと枯葉を踏んで歩く。ここでは今までにたくさんのツバキキンカクチャワンタケを見ている。まだ小さいものしか出ていないが、確信を持って探すからすぐに見つけられる。脇役の花はまだほとんどが固いつぼみで、落ちているきれいな花を探すのはツバキンよりたいへんだった。 斜面の上の朽ちた切り株に黄色いものが付いていたので、気になって払い落としてみると、網目状に広がる粘菌(変形菌)の1種ヘビヌカホコリだった。もうツヤがなくなって胞子が成熟しているようだ。 新鮮なきのこが何も見つけられず車に戻ろうとしていたとき、積み上げられた倒木のすき間にヒラタケを見つけた。三脚どころかカメラを据えるスペースもほとんどない。それでもなんとか、すき間にカメラを置いて鏡でレフをして撮影。後で触ってみるとコチコチに凍っていた。 やはり気になって時どき足元をチェックしながらの探索だったが、狙ったとおりヤマヒルを見ることはなかった。 |
 |
 |
||
 |