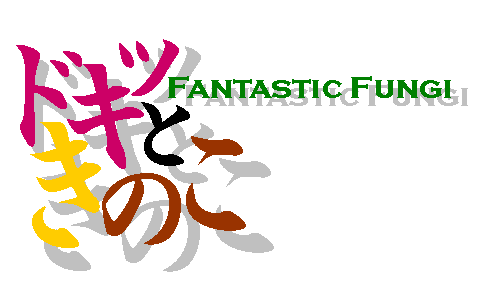 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2006年 3月 |
| 2006 | 2005年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2007年へ |
| 2006年 3月26日(日) 七沢森林公園 神奈川県厚木市 |
サクラが咲いた。暖かい雨も降った。もうそろそろ地上から生えるきのこを見つけたいものだ・・・。と、七沢森林公園のいつも歩かないコースを探索してみた。結果、尾根伝いはいくら探しても硬質菌ばかりで、仕方なくいつもの「沢のさんぽみち」へ回ってみた。 あちこちでトガリアミガサタケが出ているようなので、毎年出るイチョウの樹下を探してみた。やっと地面から頭を出したばかりの数ミリの幼菌を見つけたが、枯葉を取り払うとそのすぐ横にもっと大きなものがあった。さらに探すと、頭部がオリーブ色になった成菌が1本だけ見つかった。 スギの落葉の間から柄の細いきのこが2本生えていた。褐色の弱々しいカサには条線が見える。柄には細かな白い鱗片が付いている。種名に自信がないがコガサタケのように見える。地面から生えていた。 もう少し柄の太い地上生のきのこも出ていたが、これは以前にも何度か見ている。ツバが柄に残らずに落ちてしまうようなので、幼菌と成菌では印象が異なる。以前に見てアシナガイタチタケやフミヅキタケなどと思ったことがある。カサの感じはツチイチメガサに似ていてそれが正解にも思えるが、ツバのない成菌を見るとまた自信がなくなる。 苔の生えた材からは小さなアクニオイタケが出ていた。ちょうどバックにこの公園のシンボル「森のかけはし」があったので背景に入れてみた。 やっと種名に自信の持てる種を見つけたと思ったら、次はまったく分からないものを見つけてしまった。斜面の土から生えた柄の太いきのこで、カサの直径は1.5センチの小さなもの。カサの表面は繊維状の細かな鱗片があり、ヒダは白くて厚みがある。柄にも褐色の鱗片がある。まったく見覚えがないので標本撮影をしておいた。※アカチャイヌシメジだと思われる。 もうそろそろ出ているだろうと期待した種類を見つけた。カサの色が肉眼では黒に見えるがデジカメで撮ると紺色になる、ヒメコンイロイッポンシメジのようなきのこだ。暗い場所だったので思うように撮影できなかったが、それにしても神秘的な色合いのきのこで、ヒダは初め白いが開くとピンク色を帯びる。 やっと地面に生える「きのこ型」の種類が見られるようになってきたが、小型で種名の分からないものが多くて気分がスッキリしない。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 3月21日(火・祝) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
昨夜からあちこちの探索地をイメージしてみたが、どこの映像にもきのこが浮かんでこなかった。そこで仕方なく、マイフィールドの高麗山で普段歩かないコースで探してみることにした。 幸先よく群生を見つけたのはニガクリタケだった。カサの直径が4センチにもなる大型や幼菌も含めてたくさん生えていた。今年は発生の多い年なのかも知れない。 落ち枝にずいぶん形の乱れたハチノスタケが出ていた。カサの上にもササクレ状のものが多数あり、下の面に至っては網目が乱れて歯牙〜針状になっている。別種かとも考えたがやはりどう見てもハチノスタケだ。別の場所では乱れないものも見つけた。 埋もれ木から生える奇妙なきのこを見つけた。これは今までにも何度か見つけているが名前が分からない。クロサイワイタケ科だと思うのだが図鑑やネットで見つけられないでいる。幼菌か成菌かも不明だが、スギの材上で見た記憶がある。※カノツノタケと思われる。 高麗山にはタブの老木が多いのでマユハキタケをたくさん見ることができる。ほとんど朽ちてしまった切り株にも、長さ1.5センチの立派なマユハキタケが出ていた。穂先の部分がきれいな紫色をしているが、そこから出る胞子の色は鮮やかな黄色だ。 だんだん小さなものに目が慣れていくと、ついに自分でもビックリの極小菌を見つけた。地面から出ている部分は7ミリほどで全体に黒いから、よく目に止まったものだと我ながら感心した。図鑑で見るとハナヤスリタケであることは分かったが、掘り返してもツチダンゴは見つけられなかった。細い菌糸でつながっているらしいので、少し深い場所だと掘り出すのは難しいようだ。 ※後日、検鏡していただいた結果「テングノメシガイ属」だと判明した。 またフクロシトネタケの元気な姿を見つけた。スギの切り株に苔が生えて、それをバックにいい写真が撮れた。 梅雨になって多くのきのこが出始めるまでは、こうして一風変わった小型のきのこを探すのも面白い。珍菌でもないのに初めて見る種類もけっこう多くて興味が尽きない。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 3月19日(日) びわ青少年の家 神奈川県平塚市 |
雨は今朝まで残った。ゆっくり出発して「びわ青少年の家」へ向かった。あまり広いフィールドではないが、いつも何か面白い種類を見せてくれるところだ。 いきなり広場の中央付近にたくさんのチャワンを見つけた。ツバキかヤマグワかと付近を探したが頭上高くにイヌシデの枝が広がるだけで、どちらも付近には見当たらない。もう一度地上をよく見ると、すぐ横に枯葉を燃やした跡があった。どうやら掃き集められた落ち葉などに混じっていたらしい。ヤマグワの実に生えるキツネノワンはまだ早すぎる。掘ってみるとやはりツバキのガクらしい木質の小片から生えていた。他でも白いツバキの樹下で苔の間に生えたものが、いい被写体になってくれた。 散策路の坂道に大きなカサを見つけた。直径7センチあまりで周囲は少し反り返り、ササクレ状の鱗片や深い亀裂が中央に見える。周縁部にはわずかに赤みがかった部分も見える。よく見るとステップ材のコナラから生えている。可能性としてはシイタケだろうか・・・と、撮影後に裏返すと白いヒダに赤いシミがあり、太短い頑丈な柄を付けていた。やはりシイタケだった。 同じようにステップ材に使われたスギからは、フクロシトネタケが数個見つかった。大きいもので直径4センチ。このくらい広がれば子嚢胞子にくちばし状の突起が確認できるに違いない。 午後にまた雨が降り出して、今度はカミナリも鳴り出した。このまま気温が高めなら明後日の祝日はちょっと面白いかも知れない。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2006年 3月18日(土) 伊豆一碧湖 静岡県伊東市 |
横殴りの強い雨が降ったり、抜けるような青空が広がったりと、まるで猫の目のようにクルクルと天気が変わるようになってきた。こうして春になっていくのだろうが、日本の気候はもう少し穏やかだったように思う。 まだ気温が低いので心情的になるべく南へ行きたがる。そこで、2ヵ月ぶりに一碧湖へ行ってきた。 まだ地上生のきのこは期待できないので、倒木や積み上げた枝を丹念に探す。新鮮なアラゲカワラタケを見つけた。独特の淡い色調の環紋がある写真がなかったので撮影。カサの「アラゲ」もアップで撮っておいた。 先週はアクニオイタケを間違えたが、今回はマツの倒木にたくさん見つけた。かなり柄が長いのもあるので、採取してしまうと見分けられないだろう。両方を同時に観察できたらニオイの微妙な違いなどがあるのかも知れない。 コナラの立ち枯れた根元をよく見ると、苔の間から小さなカサがぶら下がっていた。直径は5〜6ミリしかなくて下の面は管孔になっている。確か図鑑で見覚えがあった・・・と、探してみるとヒメカイメンタケだった。いい状態は1個しかなかったが初めて見る種類だ。 以前、湖畔の道沿いにトガリアミガサタケを見つけた場所で目を皿のようにして探してみたが、まだ幼菌すら見つけられなかった。ここは少し遅く生えるタイプらしい。そのかわりシイタケの幼菌が3つ並んでいるのを見つけた。 渋滞を避けるために午後早く出発したが、雨が降り出したためいつもより酷い渋滞に巻き込まれてしまった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 3月12日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
並みの台風でもこんなには吹かないと言うくらい、海からの温かい風が吹き荒れた。そのせいで地面はすっかり乾いてしまい、高麗山を歩いてもほとんどきのこが見つけられなかった。 寒いのは苦手で体が動かないが、急に汗ばむような陽気になってもバテやすくて困る。何のことはない、単なる軟弱者だ。 以前からツヤウチワタケとツヤウチワタケモドキの違いが釈然としなかったのだが、今日、新鮮なものを見つけてツヤウチワタケモドキがはっきり分かった。 1ヶ月前にエノキタケの大きな株を見つけたポイントをチェックすると、すでに朽ちてしまった下から新たな幼菌が出ていた。まるで、朽ちてなお幼菌を守っているかのようなシーンだが・・・。 車へと引き返す道で、早くもヘビの姿を見た。1mほどのジムグリだった。苦手な人はクリックしないように。 帰ってみると、洗濯物のバンダナが一つ、行き先も告げずに放浪の旅に出かけてしまったらしい。 |
 |
 |
||
| 2006年 3月11日(土) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
「三寒四温」にはまだ届いてなくて「寒」の方が多い日が続いている。しかし、一雨ごとに着実に春めいてきたことは確かなようだ。 何か目新しいきのこが見たいと、久しぶりにこの公園へ来てみた。朝はまだ寒かったが気温はどんどん上がり、陽気に誘われて散策する人が多くなってきた。 ムクの大木のウロに小さなきのこを見つけた。柄を見ると黒いビロード状なのですぐにエノキタケと分かったが、いよいよ最盛期が終るのだろうか心なしか弱々しく見えた。真冬よりむしろ、エノキタケの消える今ごろの方が被写体が少ないのかも知れない。 スギの倒木にいくつも見つかったのはフクロシトネタケだ。まだ小型のものばかりで、確かな同定はもっと成長した胞子を見る必要があるのだろうが、この時季に見るこのスタイルは間違いないだろう。 すぐ横に同じスギの木からキクラゲも生えていた。以前、高麗山でも見つけたことがあるが、キクラゲもまれに針葉樹から生えるようだ。どの図鑑をみても広葉樹となっていて、保育社の新菌類図鑑には「日本では広葉樹に生える」という意味あり気な表現がしてある。味が違うかどうかは試してないので分からない。 朽ちた落ち枝にクロサイワイタケ科のきのこが群生していたが、姿を見るとブナノホソツクシタケによく似ている。樹種が何かは分からないがブナの実ではないことは確かだ。マメザヤタケ属までしか分からない。 ※リンクHP「東京山案内人」の広尾山荘主人こと中島さんから、昨年7月の勉強会でも採取された「フデタケ」だろうとメールをいただいた。城川会長の解説を聞いてなかったようで大いに反省!さらに、「サイワイタケ」は漢方の「霊芝」、つまりマンネンタケの別名で、黒い硬質菌の仲間を「クロサイワイタケ」と名付けたのだろうと教えていただいた。中島さん、ありがとうございます。勉強になりました。 極小菌でもいいから何としても「きのこ型」を見つけようと、視線と意識を集中させて丁寧に探したところ、やっといい被写体を見つけた。カサのニオイをチェックしてアクニオイタケだろうと思い、撮影開始。イヤに柄が長いことが気になってよく確かめてみると、なんと地面から生えていた。同じように薬品臭がするニオイアシナガタケの方だった。 気を良くして探索を終えようとしていたとき、ふと、白い看板が目に入った。「気持ちは分からなくはないが、ウソを書くのは良くないなぁ」・・・と、つい文句が口をついて出た。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 3月 5日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
3月になってすぐに、本当に久しぶりにまとまった雨が降った。今日の定点観察にいい条件が揃ったと期待してはいたが、その後も気温が低いままだったので思ったほどの菌果はなかった。 針葉樹の柵木に黄色いカサが並んでいた。幼菌のカサはやや赤く見えるのだが、ヒダを見れば独特の硫黄色ですぐに種名がわかる。このところあまり元気な姿を見かけなかったニガクリタケだ。まだあまり胞子が落ちていないのか、特徴的な黒い糸くず状のツバは見えなかった。 昼食場所にしている「池ぶち広場」には、毎年この時季に決まって生えるきのこがある。小さくて写真栄えのするきのこではないが、「もうすぐ春」を実感させてくれる種類として印象深いものがある。チャムクエタケモドキだ。とても吸水性の強いきのこらしくて、乾いてしまうとまったく別種のように色が変わってしまう。 すっかり朽ちてしまった広葉樹の切り株に、センボンクヌギタケが群生していた。小型ながらもこれだけの数が群生していると、写真に迫力が出てくる。 ウメの花がかなり開いてだんだん春らしくなってきた。一雨ごとに景色が一変していくのだろう。 |
 |
 |
||
 |