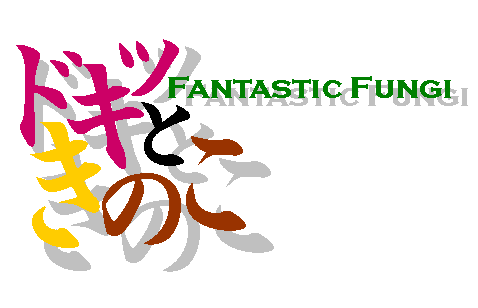 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2006年 8月 |
| 2006 | 2005年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2007年へ |
| 2006年 8月28日(月) 第5回きのこセミナー 東京都KKRホテル東京 |
2004年8月にスタートした「KKRきのこセミナー」は早くも第5回目を迎え、今回は110名以上の参加者で賑わった。今回のメイン講師は料理研究家の堀江ひろ子さんで、ご自身やご家族の食生活や工夫されたレシピの紹介など、面白いエピソードも織り込んだ内容だった。 続いて私の「きのこ撮影テクニック」の講演。誰にでも簡単に実践できる撮影ポイントに絞って、きのこフィギュアを使って実演しながら紹介した。 その後はきのこや山菜をふんだんに使った、多彩なメニューのブッフェ料理をバイキング形式で楽しんだ。 また今回、100種以上のきのこ写真を提供した本「名人が教えるきのこの採り方食べ方」(瀬畑雄三監修・家の光協会)を、9月1日の発売に先駆けて会場で販売させていただいた。 生まれて初めての「サイン本」に緊張しながら、たくさんの方に購入していただくことができた。 ※今回ご参加いただいたたくさんの方々、そして、出版に当たって小HPを採択してくださった関係者の皆さまに、心より深く感謝いたします。ありがとうございました。 |
 |
 |
||
| 2006年 8月27日(日) 高尾山 東京都八王子市 (神奈川キノコの会勉強会) |
今までに「神奈川キノコの会」の勉強会も含めて何度か高尾山へ行っているが、きのこがたくさんあったという記憶がないしいい写真も撮れてない。明日の「第5回KKRきのこセミナー」に備えての準備もあるので休もうかとも思ったが、このところの秋めいた気候に誘われて行くことにした。 ケーブルで登って散策路を下るコースを取ったが、散策路脇にはけっこういろんなきのこが出ていた。 少し道をそれて斜面を登ってみるときれいなボタンイボタケがあった。鮮やかなオレンジ色は遠目にも目立ち、まるで周囲に砂糖をまぶして化粧を施したような色合いが面白い。 落ち枝に生えたきれいな薄紫のきのこが見つかった。しっかりした柄にヒラタケ型〜じょうご型にカサを広げ、ヒダは長く垂生している。形から判断してカワキタケだろうと思ったが、こんなに淡い紫色の場合もあるのかと不思議だった。しかし、図鑑を読むと「色はしばしば大きく変化」とある。 砂に埋もれて丸山型のカサだけが地上に出ているのを見つけて、近づいてよく見ると白い地色に黒いかさぶた状の鱗片が付いている。気になって慎重に掘り起こしてみるとしっかりしたツバがあり、柄の根元が株状に膨らんで黒い鱗片が同心円に並んでいる。かなり白っぽいがヘビキノコモドキだ。 もう1種、きれいなテングタケ科のきのこがあった。カサの表面に黒っぽいまだら模様が放射状に広がっている。クロタマゴテングタケだ。柄の段だら模様もきれいに見えて、標準的ないい姿だった。 あまり普段見かけない種類にも出会えて、これからも探索したい場所の一つになった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 8月26日(土) 泉の森公園 神奈川県大和市 |
このところ天候が不安定で局地的な大雨が降ったりしている。そして昨日あたりから急に真夏の日差しが少し弱くなり、まるでもう秋になってしまうような過ごしやすさだ。きっと、まだまだ厳しい残暑が続くことは間違いないと思うが、いくらかでも探索が楽なのはありがたい。 久しぶりに「泉の森公園」へ行ってみた。ここも明け方ごろまで雨が降ったようだ。しばらく何も見つけられないまま、池のそばの森に入ってようやくいくつかを撮影した。 赤いカサのイグチがいくつも生えていて、成菌はどれも雨に打たれて傷んでいたが、幼菌はしっかりしていて被写体になってくれた。 すぐ近くにはツルタケもたくさん生えていたが、中にカサの色が灰色ではなくやや褐色のものがあった。覗き込むと柄にはしっかりツバが付いている。これはアカハテングタケの方だった。 もう1種、少し盛り上がった地面に見慣れないきのこが出ていた。カサ一面にトゲ状の鱗片が付いている。見たところアセタケ属のようなのだが名前は分からない。ヒダが濁った色で縁が鋸歯状になっていた。 コースも終わり頃、シラカシの根際に全体が粉だらけのきのこが3本立っていた。初めて見るコナカブリテングタケだ。手を触れるのを躊躇してしまうほどの粉まみれ状態で、きのこの多様性に改めて驚いてしまう。 午後はまた暗くなり、雲行きが怪しくなってきたので早めに引き上げた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 8月20日(日) 四季の森公園 神奈川県横浜市 新治市民の森 神奈川県横浜市 (定点観察会) |
今年も来月から、定点観察会のメンバーで「四季の森きのこ写真展」を行うので、まず被写体探しに「四季の森公園」へ向かった。 園内はやや乾燥気味だったが、中型から小型菌を中心にみんなで作品作りに励んだ。 枯葉の積もった一帯にキツネノカラカサ属と思われるきのこがいい形で束生していたので撮影。ところが、種名がはっきり分からない。ヒメオニタケやクリイロカラカサタケによく似た感じなのだが、細かく見ていくとどちらとも断定できない。結局、属までしか分からなかった。 被写体として絵になる色彩の華やかなきのこを探したが、なかなか見つけることができない。ところがごく平凡な種類の意外な美しさを見つけることができた。いたるところで落ち枝に群生している小さな子嚢菌、ニセキンカクアカビョウタケが朱色の幼菌から黄色の成菌へときれいなグラデーションになっていた。 最後はいつもの定点観察地へ移動したが、すでにかなり体力を消耗していたので探索も撮影もやや手抜き気味。初めて見るシロツルタケを見つけて喜んだが、これも純白ではなくてやや疑問が残った。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2006年 8月19日(土) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
富士山の北麓と伊豆の一碧湖のどっちにしようか迷っているうちに、出発が遅くなってしまった。遠くへ行くほど気温はどんどん上がってしまう。そこで、考えていた候補地をすべて振り払って、マイフィールドの高麗山を歩くことにした。 まず「地獄沢」から入ってみたが、大きな葉の雑草が生い茂ってとても探しづらい。堰堤の上でやっと、落ち枝に小さなきのこを見つけた。2004年6月にここで見つけてアシナガイタチタケだろうと同定したものと同種のようだ。イタチタケ近縁種としておく。カサの鱗片がよく揃っていてきれいだ。 倒木にロクショウグサレキンの幼菌が出ていた。直径が1〜2ミリしかないが、独特の色がよく出ている。レフ板の光を当てると子嚢盤が光っているように白く見えるので、ひょっとすると「ヒメ」が付く方かも知れない。 少し沢を登っていくと、先月23日に見つけて城川先生に検鏡していただいた白いニクアツベニサラタケがまた生えていた。前回とは場所が離れているがやはり上面はほとんど真っ白なので、極端に色素の少ない品種レベルということになるようだ。「ニクアツシロサラタケ」と仮称して記録しておく。 きのこの「特異ポイント」と言うべき場所がある。かなり狭い範囲に種々のきのこが次々と姿を見せるのだが、よほどきのこにとって好ましい環境だということだろう。この堰堤の入り口斜面はまさにそんなポイントで、今までにエノキタケやツチナメコなどを見つけたが、今日はなんとヒョウモンウラベニガサが生えていた。 地面から生えているように見えたので目を疑ったが、かなり腐朽した埋もれ木から3本生えていて、カサの表面には紛れもなく豹紋がある。まさか本種を見つけるとは思っていなかったので、今朝の行き先の迷いはこのきのこが呼んだのかとさえ思えた。 その後はなかなかいい被写体に出会えなかったが、倒木に並んだエゴノキタケが面白いパターンを描いていた。 汗が噴きだしてきて撮影意欲も萎えてしまったので、昼までの探索にして早々に冷房の効いた部屋に逃げ込んだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 8月13日(日) 道志みち 山梨県道志村 |
今まで春先の「道志みち」しか知らなかったので、この時季はどんな様子かと行ってみた。なんと朝の8時で「道の駅どうし」の駐車場はすでに満車状態。キャンプ場や川遊びなどができることもあって、ここを目的地にしている車が多いようだ。 道志川のつり橋を渡って散策路をたどってみるが、きのこはまたまた「端境期」に入ってしまったのかほとんど見つからない。スギの根際にやっと明るい褐色のイグチを見つけた。いつも思うが、イグチの仲間はなぜかカサの様子だけでイグチだと分かることが多い。これは管孔面だけが真っ白で柄とカサが同じ褐色のクリイロイグチだ。カサ表面は細かな鱗片のビロード状だった。 いかにも「きのこがあるぞ!」という風通しのいい斜面を丹念に探すのだが、見つかるのは真っ白の毒きのこドクツルタケの仲間だけだった。それでもいいバランスで立ってくれていると、アングルを決めるにも熱が入る。 針葉樹林の方も歩いてみたが、目を引くのは真っ赤なアケボノオシロイタケだけだった。小さなものがいくつも生えていたので、苔をバックに形のいいものを撮った。 散策コースを歩き終えて川沿いの農道を戻っていると、道の脇に漏斗状のカサが見えた。近づいてみると明るい褐色のササクレが放射状に付いている。裏はヒダではなく細かな管孔だから、どうやらタマチョレイタケだ。今まで材上生しか見たことがなかったので、やっと菌核を見られると期待したが、残念ながらこれも直径5センチほどの落ち枝から生えていた。 昼にはますます家族連れの車が増えてきて、国道沿いに長蛇の列ができている。これ以上付近を探しても変わりばえしないだろうと帰途についた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 8月 6日(日) 高麗山・子供の森 霧降の滝 神奈川県平塚市 |
新聞によると今日6日は東京では、屋外で運動をしてはいけないことになっている。8月に入って「熱中症」で倒れる人が増え始めたため、気象協会が出した予防情報だ。 そこで午前中だけ近い場所を歩くことにして、7時に外へ出るともう息が詰まる暑さだった。なるべく木々の多い場所と考えて高麗山の子供の森へ向かった。 ようやく夏きのこの代表(?)ドクツルタケがたくさん出始めた。幼菌から老菌まであちこちに生えているが、よく見るとツバの形にずいぶん差がある。すべてが同種かどうかは検鏡しないと分からないが、ツバの出来方にはバリエーションがあるように思う。 大きなタマゴタケも数本見つけたが、これはカサを開き切った成菌ばかりだった。所どころ裂けた赤いカサにくっきりと条線が並ぶ。華やかさと言うより濃厚な美しさを持っているように感じる。 もう1箇所、霧降の滝の道も歩いてみたが、ここもすぐに見つかるのはドクツルタケとタマゴタケだった。引き返そうとした時、鮮やかな黄色いカサを見つけた。 枝が邪魔をして曲がりくねって生えていたが、カサにははっきり条線が見える。キタマゴタケかと思ったが中央に突き出た小山がない。それに表面に黄色い粉を付けている。ツバは膜質で上下両面とも濃い黄色、柄には段だら模様がない。そして、ヒダが真っ白だ。いろいろ考えたが結局分からない。外見的特長が当てはまる種類は図鑑にも見当たらなかった。 午後は「Gallery」のページを作ることにした。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2006年 8月 5日(土) 富士山北麓・精進湖 山梨県上九一色村 |
リンクHP「兵庫きのこ研究会」の会員8名の方々が富士山に来るというので、案内を兼ねて同行させていただいた。「青木が原樹海」をご希望だったがよく知らない私の案内では危険が大きすぎるので、以前に2度「宿泊勉強会」で行った精進湖周辺を歩くことにした。 9時半に待ち合わせてあいさつもそこそこに探索を始める。・・・が、長かった梅雨の反動か真夏のカラカラ天気となって、溶岩樹海の中も乾き切っていた。 「きのこゼロ」かと心配したが散策路に沿ってポツポツとタマゴタケが見つかる。どれも傷んだものが多かったが、やっとカメラを向ける気になるいい状態が見つかった。 しばらく歩くと高さが7センチほどの黄色いカサのきのこがあった。よく見るとテングタケ科のきのこでどうやらタマゴタケモドキのようだが、かなり弱々しい雰囲気でしばらく分からなかった。ずいぶん昔に広島で見て以来、久しぶりに見た。 昼食後は精進登山道の方へ少し入ってみた。こちらもきのこは少ないものの、それでも幾分ましで数種のイグチが見つかった。その中に初めて見る種類があった。カサは平滑で灰色、中央が濃い色になっている。柄のほぼ全体に黒い網目模様がある。どうやらクロアワタケのようだ。 同じような黒っぽいカサのものが見つかったので同種かと思ったら、柄が繊維状で白い。カサの周縁にはふけ状の白い鱗片が見える。幼菌ではそれがカサ全体にあるので白っぽく見える。ヒダは粗く灰色で大きな鋸歯状になっている。図鑑を調べても分からず印象はクロゲシメジに似ているが、カサの表面にほとんど鱗片がないので別種だろう。 残念ながら肝心のきのこが少なかったが、初対面とは思えないほどザックバランな方々の心地よい関西弁に囲まれながら、楽しい探索をすることができた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |