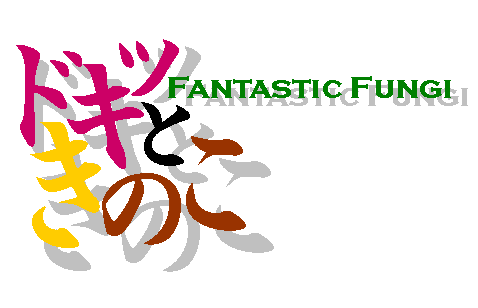 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2006年 10月 |
| 2006 | 2005年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2007年へ |
| 2006年 10月29日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
今月最後の探索は天気の予報も良くなかったので、マイフィールド高麗山の最近あまり歩いてないコースをじっくり回ることにした。地獄沢からスタートしたがエノキタケのポイントにはまだまったく気配もなく、堰堤の上まで行ってやっと小さなヒラタケを見つけた。一番大きいカサでも3センチあまり。これからに期待しよう。 すぐ近くに誰かが採って捨てたきのこがあった。ところがカサの表面を見てビックリ。この大理石模様はブナシメジではないのか。小さくてハッキリしないがやはり外見ではブナシメジの雰囲気だ。ここに生えていたのだろうか? 「けやきの広場」へ向かう坂道では、階段の杭にいくつもの 広場を出るとき小型のヘビを見つけて、今まで見た記憶がないので撮っておいた。帰ってから調べるとタカチホヘビだと判明。珍しくはないがあまり姿を見せないらしい。50センチほどのとてもおとなしいヘビだった。 サクラの倒木にたくさんのチャカイガラタケが並んでいたが、木の上に生えているものはカサが円形になってきれいな環紋が見えた。褐色の明暗や赤紫色の環に混じって真っ白の細いラインも走っている。よくみるとかなり凝った色使いが見られるのが面白い。 今日はコースのあちこちでニオイアシナガタケを見かけた。細くて小さなきのこが1本ずつ生えていてはなかなかカメラを向ける気にならない。それでも次々に現れるので、最も撮りやすいものを選んでじっくり構えてみた。淡い色合いを写すのも難しく、きのこ全体にピントを合わせるのも困難だ。かと言って絞り込んだらバックに紛れて見えなくなる。せめて2・3本並んでいれば絵になりやすいのだが・・・。 最後に地獄沢へ戻ってきたが、なんと今日3回目に通る道でツチナメコを見つけた。「きっと、朝通ってから生えたんだ・・・」などとブツブツ言いながら撮影。ツチイチメガサかな、とも思ったが撮影後に確かめるとカサに強いヌメリがあった。 結局、雨は早朝に止んで、時おり日差しも出て暖かくなった。「冬きのこ」の盛期はまだひと月ほど先にしてもらって、もう少し面白い種類を楽しみたいものだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月22日(日) びわ青少年の家 霧降の滝散策路 神奈川県平塚市 |
日光の紅葉が始まり、渋滞のいろは坂は20分の道のりを2時間かけて登るらしい。車に一人で乗って歩くより遅い速度で走っていては「自然を愛する」精神からひどく逸脱していると思うので、単にイライラするという「イラチな関西人」だけが理由ではなく渋滞が嫌いだ。 で、今日は平塚市内の2箇所を歩いてきた。久々の「びわ青少年の家」と、沢沿いのコースに期待して「霧降の滝」だ。 地面は乾き切って砂埃が舞うほどだから、探索の目は自然に倒木へと向かう。すると大きなクヌギの倒木に生える形のいいきのこが飛び込んできた。そろそろこれが出始めたかと、シーズンの名残惜しさを感じるエノキタケだった。こんなに乾いた空気でも瑞々しさを保っているのは凄い力だと思う。 階段の木の下側に面白いきのこを見つけた。今まで立ち木に生える姿しか見たことがないハナビラニカワタケだ。こんな所に生えたおかげで、胞子の色が白いのだと改めて確認できた。 枯葉に埋もれるようにして黒いカスリ模様の小型菌を見つけた。時どき見かける ※後日、ウラベニガサ属のクロスジウラベニガサ(青木氏仮称)らしいことが分かった。 午後は霧降の滝へ移動。ここは沢沿いの散策路だから何かいいものが見つかるだろう。しばらく歩くとスギの間伐材を積み上げた所に白いカサを見つけた。こういう場所で最も気を付けなければいけないのはマムシだ。注意深く邪魔な木を動かしていると、迷惑そうに顔を見せたのはヒキガエルだった。きのこはきれいなスギエダタケで、じっくり腰を据えて撮影した。 散策路沿いにはほとんどきのこが見つからなかったが、また、新顔のホコリタケを見つけた。全体に褐色の粉を被り大小の鱗片が並んでいる。何となく見覚えのある顔に、柄を覗きこんで納得した。何と条線のあるツバが見える。これはキショウゲンジだ。紛らわしい姿をしているものだ。 帰り際に朽ちた切り株にヒメロクショウグサレキンを見つけた。とても小さいので撮影は苦労するが、それでも得られる写真はとても神秘的で美しい。 帰り道で「おしめり」にもならない霧雨が降ってきた。明日からは雨が降るとか・・・。期待しよう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月21日(土) 伊豆・一碧湖 静岡県伊東市 |
久しぶりに伊豆の一碧湖へ行ってきた。このところまったく雨が降らないので、どこのフィールドを思い浮かべてもきのこがありそうに思えない。どうしても湖の傍か沢沿いのコースを選びたくなる。 この時季は紅葉狩りなどで人が多いため、一碧湖の東側にある湖の周囲を探索した。さっそく草むらに群生するキララタケを見つけた。絡まった草やつるを慎重に取り除く。カサの表面にある「キララ」を落とさないように、息を止めての苦しい作業だ。ローアングルで何カットも撮影した。 散策路に踏み潰されたベニタケの仲間が1本あって、何だろうと思いながら歩くとすぐ前にもう1本しっかり生えていた。この独特の紫がかった灰褐色はチギレハツタケだろう。ヒダがとても密なため「脈連絡」があると言われても観察が難しい。何とか撮影できないかと挑戦してかろうじて写すことができた。 最近ホコリタケの多様さにちょっと興味を持っている。今日も数種見ることができたがいい状態のものは少なかった。真っ白いヒメホコリタケのすぐ傍に、鱗片の様子が少し違う黄色っぽい幼菌があった。この仲間は成長とともに色や外見をかなり変えるようなので、正確な分類には経過観察が不可欠だろう。 落ち枝に1本、小型で形のいいきのこが生えていた。カサは黄色みの強い褐色で細かな放射状のひび割れ模様が見える。きっとウラベニガサ科だろうとヒダを覗くと、ヒダも柄もきれいなピンク色をしていた。「北陸のきのこ図鑑」にあるアカエノベニヒダタケ(仮)に酷似している。 広い芝生の公園で大きなコナラの周囲に丸いカサのきのこがたくさん生えていた。今年ずいぶんあちこちで見たワタゲナラタケのようだ。ナラタケの仲間だが地上に生えることが多い。 ずっと曇り空で気温も湿度も低く、探索するには快適な一日だった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月15日(日) 四季の森公園 神奈川県横浜市 |
約1ヵ月間にわたり展示していた「四季の森公園きのこ写真展」が最終日を迎えたので、作品の搬出に行った。設置したメッセージノートにはたくさんの感想に混じって、すっかり子供たちの落書き帳になっていた。それでも楽しい遊び場を提供できたことは嬉しいことだ。 搬出の後は集まった仲間ときのこ探索。乾燥気味なのできのこは少ないが、清々しい秋の空気を感じながらの散策は気持ちがいい。 切り株に見つけたきのこは今までなら撮る気も起こらなかったコフキサルノコシカケなのだが、これが今ちょっと興味深いことになっている。どうやら関東周辺で普通に観察されるものはコフキサルノコシカケではなく、胞子サイズがかなり大きい別種で、その名もオオミノコフキタケというらしい。外見的な違いはないので検鏡しないと区別はつかないが、ごく普通に見られるのは後者だそうだ。 草に埋もれるように1本だけヤマイグチが生えていた。もうイグチの仲間は見られないと思っていたが、この仲間は遅くまで生えるようだ。 かなり腐朽の進んだスギの材からきれいな赤褐色のきのこが生えていたが、姿はどう見てもキツネノカラカサ属に見える。しかし、材上に生えているのは変だからひょっとするとモエギタケ科のヒメスギタケ属になるのだろうか。 ホコリタケがたくさん並んでいた。よく見るとちょうど頂部に穴を開けるところで、1個だけ開いているという面白い瞬間だった。付近には同じ形の黄色いタイプもあって、同種にしては色が違うのでこちらも興味深い。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月14日(土) 大志戸・木の実の里 山梨県甲州市 |
きのこシーズンも終盤に差しかかったようなので、ぜひもう一度見ておきたいポイントへ向かった。ひょっとすればコウタケを見つけるかもしれないし、何かの間違いでホンシメジに出会うかもしれない。そんなことを考えているとクマに遭遇するかも知れないので、チリチリと鈴を響かせながら歩く。 前回の逆周りをしようと駐車場から道を少し戻っていると、斜面の上の方の大木に何やら白い塊が見えた。根元の周囲を取り囲んで見えたので気になってよじ登ってみると、ナラタケの大きな群生だった。ちょっと密集しすぎてきれいな群生ではなかったが、幹の上の方にも塊のあるみごとなものだった。 ついでだからとそのまま「けもの道」をたどって登っていくと、あちこちにヌメリササタケが見つかった。雨が降ってないのでやや乾燥気味だが、それでも強い粘性があり手に付いて離れないほどだ。 コウタケのポイントまで行くまでに数人の「狩人」が降りてきたので聞いてみると、すでに数日前に何人も入っていて何もないという。ちょうどきれいなクリタケを見つけて撮っている所だったので、そこで引き返すことにした。クリタケが姿を見せると「きのこシーズン」もそろそろ終わりに近づく。 今日はあちこちで大きなベニテングタケを見たが、どれもすでに傷みがひどく被写体にならない。2002年に見たような素晴らしい群生は見られなくなった。何とか色と姿のいいものを選んで撮影。やはりベニテングタケはきのこの代表とも言える、とても絵になる姿をしている。 早くもムラサキシメジが顔を出していた。付近を探してもこの1本しかなかったが、これも終盤を告げる種類だ。やや色の薄いタイプだったがヒダの紫はとてもいい色だった。そして、もう1種、晩秋に出るきのこも出始めていた。そろそろ「霜」の降る季節になるのだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月12日(木) 農水省・消費者の部屋 東京都千代田区 |
10日(火)から明日13日(金)まで、霞ヶ関の農林水産省1階にある「消費者の部屋」で〜森の芸術・きのこの世界〜と題した特別展が開催され、当HPの写真も展示されたので行ってきた。 シイタケをはじめ多種の栽培きのこや、その他にも木炭や漆などの特用林産物が展示されていた。その一角に「自然界のきのこ」という感じで写真が展示され、食毒の別や外見のユニークさ、名前の面白さなどでまとめられていた。 エノキタケの栽培品との大きな違いや、色、形の面白さなどが訪問された方に興味を持ってもらえているようだった。 展示は明日13日の午後1時までで、14日(土)・15日(日)に江東区の「イーストプラザ21」で開かれる「特用林産物フェア」でも展示される予定だ。 |
 |
 |
||
| 2006年 10月 9日(月・祝) 富士山北麓 山梨県鳴沢村 |
そろそろ富士山初冠雪のニュースも聞かれる時季になり、ここでの「きのこ狩り」も終盤を迎えている。たっぷり雨が降った後のこの3連休は言ってみればラストチャンスだから、最終日におっとり出かけて行っても空振りに終るのは覚悟していた。それでも、「狩り」の対象外でいいから富士山らしい写真が撮りたい。 ところが歩き始めてすぐに、キシメジが数本並んでいるのを見つけた。ひょっとして人が入ってないのか?と期待したが、その後は「食菌」がほとんどなくて単なる見落としだと分かった。 巨大化したカキシメジ(毒)の老菌はあちこちに残されていたが、それに混じってチャナメツムタケの幼菌が生えていた。成菌は見つからないから、さすが「狩人」は一見よく似たカキシメジとの見分けがちゃんとできているのだと感心した。 苔の間に生えた灰色のカサを見つけてシモフリシメジかと思ったが、中央の黒い部分が尖っているのでネズミシメジだと分かった。 溶岩樹海を歩くととても足が疲れるので、途中からは平坦なカラマツ林に移動した。こちらもめぼしいきのこが少なかったが、あちこちで ホテイシメジを撮影中に少し離れた所の切り株に目をやると、何かの幼菌が形よく生えていた。近づくにつれてカサの様子からナラタケの仲間だと分かった。さらに種を同定できないかとよく見ると、ツバになると思われるところに黒い鱗片が残っていて、柄にも段だらに鱗片が付いている。・・・となると、これはきっとオニナラタケの幼菌だ。いずれ別のコーナーに登場することになるだろう。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月 8日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
3連休の計画では昨夜に富士山へ向けて出発しているはずだった。昨日の観察会でかなり歩き疲れたこともあって、夕刻には迷い始めていた。そして、HPの更新に手こずって夜には完全にメゲていた。そこで今日は疲れを癒す意味から最も近い高麗山を歩いた。 結果的にはいろんな種類が観察できたのだが、気象の展開の割りに大きなきのこが少なかった。今日はあちこちでワタゲナラタケを見かけたが、なぜかどれも地面から生えている。ナラタケらしい根際の群生を探したが、やっと見つけたのは斜面に束生しているものだった。 この場所で秋に期待するのはルリハツタケだ。富士山の北麓以外ではここしか見たことがない珍しい種類だ。とてもきのことは思えない不思議なブルーは、さすがにインパクトがある。 散策路の脇にいくつかのホコリタケを見つけたが、色や表面のトゲの様子がいろいろですべて同じ種類でいいのか疑問を感じた。成長過程の違いにしては混在していることがなかったので、いくつかのタイプがあるのではないだろうか。 通称テングタケ通りでは何一つ見つけられなかったので、頼みの綱の地獄沢へ向かった。沢に落ちた朽木に黄色いきのこが1本だけ出ていた。よく見るとしっかりしたツバがあり、カサの中央にはこげ茶色のトゲ状鱗片が付いている。どうやらキツブナラタケ(※)のようだが、これがたった1本では絵にならない。仕方なく超ローアングルで撮ったら前に同じ場所で撮ったヒメベニヒダタケとそっくりの構図になった。 (※)後日、ツバに黒い鱗片があり小型で単生している等の特徴から、「コマヤマナラタケ」と仮称されている別種の可能性が高いことが分かった。 今年、この場所で白いニクアツベニサラタケを見つけて、普通のタイプは見たことがないと書いたが、なんと普通のエンジ色のものが見つかった。やはり発生時期で色が変化するのかと思ったら、すぐ近くに真っ白なタイプも生えていた。 最後は「高麗山にもついにマイタケ!」と、一瞬だけビックリしたきれいなカワラタケ。残念。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月 7日(土) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
昨日、東日本を中心に記録的な大雨となった。ニュースでは2ヵ月分の雨量が一日で降ったようなことを言っていた。この時季にまとまった雨は嬉しいのだが、その直後の今日は泥跳ねを被ったきのこが多くなるので撮影には痛し痒しだ。 朝から青空が高く広がり、絶好の散策日和のもと観察を開始。すぐに種々のきのこが見つかるが、やはり雨で傷んでいるものが多い。スギ林の地上に強いヌメリのきのこがあった。しばらく名前が分からなかったが菌糸の塊に包まれた根元をほぐすと細長く伸びているのが確認できた。どうやらアシナガヌメリだろう。動物の死骸でも埋もれているのかと思うとちょっと不気味だ。 今日、あちこちの斜面でもっともたくさん見かけたのは、チチタケ属で橙黄色の大きなカサを広げるアイバカラハツモドキ(青木氏仮称)だ。カラハツタケやキチチタケに似た姿だが、大きくじょうご型に開き半透明の乳液を出す。やや渋味がある程度で辛くない。 毎年、ハタケシメジが群生するポイントへ向かったが、この道は何度もマムシが目撃されていて要注意だと思っていたら、やはり今日も50センチほどのものがいた。そしてその先にはみごとに群生したハタケシメジがあった。ヘビ嫌いのメンバーもハタケシメジの魅力には抗しきれず、遠巻きに通り過ぎて行く。 薄暗い散策路にクロノボリリュウタケを見つけた。この場所では以前にも見ているが、被写体としていい表情を感じるのでついカメラを向けたくなる。少し逆光気味に撮ると柄が日に透けて見えた。 今日一番の「ドキッと」は探索開始間もなく見つかったマイタケだ。今年は平地でもコナラの根際に出ているようだが、まさかこの公園でこんなみごとな株が見つかるとは思っていなかった。山深く分け入って、シロは家族にも教えないなどと言われているが、今年はかなり広い範囲で多く発生しているようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2006年 10月 1日(日) 茅ヶ崎自然生態園 「きのこ観察会」 神奈川県横浜市 |
毎年楽しみにしているイベント、横浜の「茅ヶ崎自然生態園」での「きのこ観察会」が、今年も空模様に気をもみながら開催された。時どき小雨がパラつくことはあったが、何とか解散までは傘のいらない天候を保ってくれた。 34名の参加者は2班に別れて探索を開始。早くもあちこちから「きのこ見っけ!」の歓声が上がっていた。去年大きな菌輪を描いていたウラムラサキシメジが、今年はいたるところに群生していて、今日もっともたくさん見られたきのこだった。あまり美味しくなくて、おまけに人によって中毒することがあるので、ちょっとガッカリという様子だった。 そしてもう1種たくさん採れたのは、これも残念ながら毒きのこのニガクリタケ。「どうして毒があるの?」という不満混じりの質問も出て、返答に窮してしまった。 やっと食菌が見つかったが、これはむしろ観賞用にしたいほど美しいキタマゴタケだった。去年までの観察会では見られなかったが、今年は神奈川県の各地でキタマゴタケの遅い発生が観察されているようだ。 みんなが採取したきのこの鑑定会場では、形と手触りの面白さからかスッポンタケの幼菌が関心を集めていた。 最後は恒例のシイタケバーベキュー。今年もホダ木から自分でちぎって焼いて食べる。毎年のように「シイタケは嫌いだったが美味しく食べられた」という声を聞く。 昼に解散したが、まるで待っていてくれたかのように午後は本降りの雨となった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |