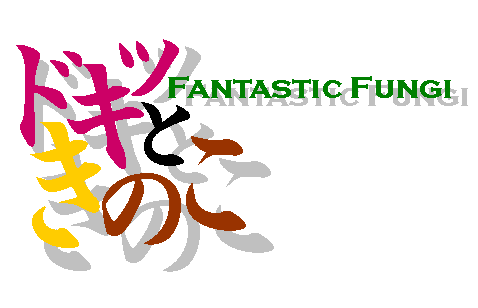 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2008年 6月 |
| 2008 | 2007年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2009年へ |
| 2008年 6月30日(月) 土屋の里 神奈川県平塚市 |
所要で休みを取っていたら少しだけ時間が空いたので、この季節に一番撮っておきたいキヌガサタケを探してみた。最初、高麗山のポイントではすでに大きな2本が倒れていて、他に幼菌は見つからなかった。 そして、次のポイントではなんと、ちょうどこれからレースを広げるという理想的な瞬間を見つけた。急いでカメラをセット。1時間経過して地面に着くまでの間をほぼ5分刻みで撮った。 時間待ちの合間に付近を探してみると、きれいなカサを広げて束生しているきのこがあった。ヒダを見るとクッキリと黒い縁取りがある。イッポンシメジ属の仲間の雰囲気だが種名は分からない。ローアングルで撮影に集中していると、ついキヌガサタケの5分を忘れそうになる。 いよいよ梅雨らしい梅雨になってきた。そして明日から7月、夏本番に突入するのはいつ頃だろう。 |
 |
 |
||
| 2008年 6月22日(日) 木もれびの森 神奈川県相模原市 (神奈川キノコの会) |
「神奈川キノコの会」の本年最初の野外勉強会は、相模原市の中央緑地「木もれびの森」で行なわれた。不思議なことに私がここを訪れる日は雨になることが多いのだが、今回もまた本降りの雨になってしまった。 しかし、集合時間の9時半から鑑定開始の11時半までは、幸いなことに雨が降らなかったので、何とか採取と撮影をすることはできた。 枯葉に埋もれて小さな白いカサが見えた。いつもここでよく見かけるヌナワタケだ。今年は雨が多いので柄のジェル状のヌメリがよく見える。 リンクHP『ちょっと道草〜きのこ道』のUさんご一家はいつも目ざとくきのこを見つけるので、ちゃっかりいい被写体だけを撮らせていただくことが多いが、以下の3種もそんな楽チン撮影だった。 広葉樹の老木の根元に大きなツエタケの仲間が生えていた。簡単に仮称種のオオツエタケだろうと思ったが、城川先生の解説ではカサに強いヌメリがあることから大型のサトヤマツエタケ(仮称)とされた。 太い落ち枝から明るいクリーム色の大きなカサが生えていた。カサの周囲は強く波打っている。よく見ると表面にササクレ状の毛があり、幅の狭いヒダが密に並び柄に垂生している。これはケガワタケだ。カサの表面が濡れていたりすると一見ウスヒラタケにそっくりだが、肉質が水っぽくなく硬い点で区別できる。 コナラの材上にはとてもいい状態のゴムタケが生えていた。あまり見かけない種類なので幼菌から老菌まで揃った生え方は嬉しかった。 鑑定会は本降りの雨の中、ブルーシートをテントのように張って標本はその下に並べられ、参加者は傘やレインウェアで熱心に解説を聞いている。「たかがキノコ、されど・・・」と、熱い情熱のようなものが漂っていた。 ※都合により次週は探索ができないので、次回の更新は月末の「月間MVP」の予定です。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
2008年 6月17日(火) 謎の物体が判明 神奈川県・高麗山 |
先月、高麗山の地獄沢付近で不思議なものを見つけた。何かきのこの幼菌のようにも見えるのだが、石の隙間から生える1センチ足らずの姿から、成長した姿は浮かんでこなかった。その後、観察を続けたのだが結局大きくならず、黒く萎縮してしまった。(5月6日・10日参照) そして先日(6月15日)の高麗山で同じものを見つけた。やはり石の隙間や表面から褐色の繊維質の物体が生えている。これも大きさは1センチ足らずで、付近にはもっと小さなものもある。 さらに注意深く探しながら歩くとだんだん長く伸びたものが見つかり、ついにその正体を突き止めることができた。きのこによくある現象だが、無数にできた小さな幼菌がすべて大きくなる訳ではなく、一部だけが成長したり時にはすべて萎れてしまうこともある。何はともあれ謎が解明できてスッキリした。 |
 |
 |
||
| 2008年 6月15日(日) 高麗山・湘南平 神奈川県平塚市 |
高麗山で撮影をしていると、植物観察や昆虫観察などの人たちと言葉を交わすことが多い。みなさん一様に「毒キノコ」への恐怖と警戒心をお持ちだが、多くの方が「タマゴタケ」に興味があることも分かる。やはり出会った時のインパクトの強さが、他の人へと語り伝えられるのだろう。 遊具のあった(老朽化して取り壊された)斜面に、今年もイロガワリが生えていた。まだイグチの仲間は見かけないが、いつもこの場所は一足早く出るようだ。 そのすぐ傍に冬虫夏草を見つけた。この姿はオサムシタケだが本体の虫が見えない。オサムシタケは幼虫から生える場合もあるらしいので、注意深く掘り出してみた。やはり、幼虫から生えていた。念のためオサムシの幼虫をネットで確認したが、こんなことで幼虫の姿を初めて知ったのは奇妙な話だ。 極小菌を見つけて撮影を迷っていたら、後ろから来た二人のご婦人の会話が耳に入り、「神奈川キノコの会」と聞こえた。伺うとご主人が古くからの会員とのことだった。そしてなんと、すぐ傍の大きなカサのきのこを教えていただいた。反対側の斜面しか見てなかったので見落としていた。お礼を言ってすぐに撮影を始めた。 砂地の急斜面で撮影困難だったが、勢いのあるみごとな株立ちでカサの表面には著しいシワがあり、大きなツバには暗褐色の胞子がタップリ載っている。フミヅキタケ属の特徴だから無理やり同定するとヤナギマツタケになるが、それにしても強すぎるカサのシワと厚みのあるツバは違いすぎる。 そしてやはり極小菌も撮ることにした。と言うのも久々のヒメコンイロイッポンシメジだったからだ。カサの直径7ミリ、高さ12ミリほどのきのこに何枚シャッターを切ったことか。ピントを撮るだけで一苦労だった。 しばらく歩くと枯葉に隠れたカサを見つけた。このカレー粉のような色はキショウゲンジだ。ちょうどツバが離れた幼菌はいい被写体だ。 そしてさらに進むと棒を立てた先にティッシュの目印が・・・。見るときれいなきのこを保護するように枝が刺してあった。数人と言葉を交わしたので特定できないが、とてもやさしい心遣いに感謝して撮影させていただいた。 これはクサウラベニタケの近縁種アズキクサウラ(仮称)だ。独特のカサの色がとても新鮮な状態で撮影が楽しかった。 目印を残してくださった方、ありがとうございました。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 6月14日(土) 富士山北麓 山梨県富士吉田市ほか |
まだ雨の日に気温が下がり過ぎる傾向にあるが、それでも日中の気温はかなり高くなってきたので、富士山北麓の数ヵ所を急ぎ足で探索してきた。 まず草むらの中に大きなハラタケを見つけた。よく見るとカサの表面に広がる褐色の模様がある。となるとハラタケモドキか?ところが幼菌のカサを見るとまたそれとも様子が違って見える。結局ハラタケ属ということしか分からない。 散策路の階段の脇で大きなズキンタケを見つけたが、これもズキンタケそのものとは様子が違う。オオズキンタケになるのだろうか?ホテイタケという種類かとも思ったが、柄の下部が膨らんでないので違うだろう。 なかなかベニタケを見ないと思っていたら、やっと小さなドクベニタケに出会った。念のため味を確認して後悔した。強烈に辛い。 最後の場所ではヌメリガサ科の3種類がいい状態で見つかった。最初は目にも鮮やかかなレモン色のアキヤマタケ。名前の通り秋によく見られるがこんな季節にも出るようだ。ヒダが白っぽいのでちょうどタモギタケに似た配色だが、こちらは水分が多く透明感がある。 次は初めて見る種類だ。カサの直径1〜2センチで中央が窪んでいる。ヒダは枚数が少なくやや垂生気味で、柄の上端はオリーブ色を帯びている。名前が分からなかったが標本撮影のために採取して驚いた。柄もカサも極めて強い粘性がある。特に柄の方は粘着性と言った方がいい。指にくっついて離れないほどだ。それで同定ができた。ナナイロヌメリタケ・・・なんともいい名前だ。色はかなり変異があるらしい。 最後は今日あちこちで目に留まったベニヤマタケだ。薄暗い森の中でもこの色は遠くから見つけられる。 やはりまだ小型のきのこが多いが、かなりカラフルになってきたのでページを華やかにしてくれる。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 6月 8日(日) 伊豆・一碧湖 静岡県伊東市 |
ちょうど1年前、一碧湖で見つけた「ハラタケ属」と思ったきのこが、見たこともないテングタケ属だと分かり、どうしてももう一度見たいと雨を押して出かけた。結果は残念ながら、そう約束どおりという訳にはいかない。「約束した覚えはないぞ」といったところか・・・。雨はほとんど止んだのだが、枝から落ちるしずくがやっかいモノで傘が手放せない。 ヒメシャラの木の根元に白い幼菌が1本だけ出ていた。カサがわずかに灰色に見えるのでよく見ると、全体に細かな黒い粒点が広がっている。どうやらナカグロモリノカサのようだ。 すぐ近くにはイタチタケが2本並んでいた。幼菌のカサの周囲には被膜の白い破片が付いている。雨粒でも当たったのか成菌の柄が折れたようになっている。 探しているテングタケか?と、一瞬喜んだきのこがあった。カサ全体にササクレが広がり、やや赤く変色している。ヒダを覗き込んでみると、もうほとんど黒に見える紫褐色になっていた。これはハラタケ属の方だ。柄に綿毛がほとんどないのでザラエノハラタケではないが、それに近い仲間のようだ。 コナラの太い立ち枯れた幹に小さなカサを見つけた。よく見るとカサの中央に見覚えのあるシワがある。シワベニヒダタケ(青木氏仮称)だ。ヒダを見るととてもきれいなピンク色になっていたので、いろんなアングルから撮ってみた。 道のすぐ脇に直径6センチほどの明るい褐色のカサが開いていた。中央が突出して高くなっている。条線のあるツバが見えた。フミヅキタケのようだ。まだほとんど胞子が落ちてない新鮮な状態だったので、ローアングルでズームを変えながら撮影を楽しんだ。 脇道へ入ってもう引き返そうとした時、大きなカサが目に飛び込んできた。やや赤みのあるカサだったので、また雨で変色したハラタケ属かと思った。ところがカサの表面に鱗片が付いている。枯葉を取り除くと赤みがかった太い柄が現れた。ガンタケだ。 目的のテングタケ属は見つからなかったが、今年最初のテングタケの仲間は大きなガンタケだった。季節は初夏へ移ったようだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 6月 7日(土) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
午後からは都内へ出る用事があったので、朝の短時間だけ地獄沢を歩いてきた。関東が梅雨に入ったがまだ雨の日の気温が低く、梅雨特有のジメジメムシムシにはなってない。とても過ごしやすいのだがきのこは少ない。 いつもニガクリタケしか生えないのでてっきり針葉樹だと思っていた切り株に、今日はちょうど撮り頃のナラタケが生えていた。カサがすっかりかじられて、ほとんど柄だけになっていた数本を取り除いてローアングルで撮った。 この季節になるとあちこちの倒木でイヌセンボンタケを見かける。いつもこれを見るたびに「人海戦術きのこ」だと思う。一つのカサを極力小さくして無駄なエネルギーを省き、胞子を大量に飛散させるという目的に徹した姿なのだろう。幼菌は真っ白で逆光で撮ると美しい。 足元にさらに小さなきのこを見つけた。枯葉から生えているシロコナカブリだ。ヒダの枚数が極めて少ないので近い別種かも知れない。目一杯近づくとピントが浅くなるので、全体にピントを取るのが難しい。 スギの枝を積み上げた所に黄色っぽいホウキタケの仲間が生えていた。とても新鮮なヒメホウキタケだ。よく見ると直径1.5メートルほどの菌輪を描いていた。一部は積んだ枝の下になって見えないが、俯瞰撮影をするときれいなカーブが見える。しかし、よく考えるとそれはヘンだ。 午後は気温が上がって暑くなった。そろそろ迫力のあるシーンが期待できそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 6月 4日(水) 不明2種の続報 |
気がかりだった2種について、城川先生からとても興味深いご回答をいただいた。先月の富士山南麓で見つけたミミナミハタケ属の1種と、6月の定点観察で見つけた白いカサの不明菌だ。 まず、ミミナミハタケ属は採取した翌日に新鮮な状態でお渡しすることができた。後日いただいた同定結果はキツネナミハタケだった。日本新菌類図鑑の検索表で「北海道でのみ(1959年)」とあるが、富士山・丹沢山塊などの高地では生えているようだ。イタチナミハタケをよく見かけるが、そこへ「キツネ」が加わるのは愉快だ。 もう1種の細い枯れ枝に生えていた白いカサは、青木氏仮称のシロキクザタケとのこと。キシメジ科ケカゴタケ属に分類されている。柄はなくカサの中央で背着しているが、カサ内側の中心部に丸い乳首状の突起があるものが多いのが特徴。特筆するほどの珍種ではないらしいが発生は少ないようだ。新鮮な状態を撮影できたのは収穫だった。 城川先生ありがとうございました。 |
 |
 |
||
| 2008年 6月 1日(日) 新治市民の森公園 神奈川県横浜市 |
6月の定点観察会・・・ということはもう今年の半分が過ぎることになる。何という速さで月日が過ぎ去っていくことか。3日続けて雨が降った後に気温が上がるといういい条件だったが、たった一日では大きなきのこは期待できないだろうと思った。 ところが、駐車場のすぐ近くの草の間に、大きなヒトヨタケが出ていた。高さは7〜8センチの新鮮なもので、一夜で萎れるというより一夜で生えるという意味の名前かも知れない。 さらに次はもっと大きなきのこを見つけた。カサの直径が7センチほどあるナカグロモリノカサだ。ちょうど大きな内被膜が外れて、ツバができたばかりのいい状態だった。 昼食の「池ぶち広場」では、ウッドチップから小さなカサがたくさん生えていた。ヒトヨタケ属だと思うが種名は分からなかった。幼菌の時はカサが褐色だが、成長するとほとんど灰色になってしまうようだ。柄の全体に細かなササクレ状の鱗片が付いているのも特徴的だ。 メンバーが腐朽の進んだ木片に白い小さなきのこが生えていると持ってきたが、同じ木に変形菌のような白い点が並んでいるのを見つけた。ルーペで見て思わず「パイプタケだ!」と叫んだが、見たいと思っていたパイプタケはコウヤクタケ科の極小菌だが形は球形で、これは円筒形なのでフウリンタケ科のシロヒメツツタケであることが分かった。あまりの小ささにピントを合わせるだけで一苦労で、拡大してやっと見えるというカメラ撮影の限界に近いものだった。 古畳の上に柄の長いきのこが数本生えていた。ハタケキノコのようだ。あまり絵になる情景ではないが、これはこれで本種らしい面白い写真だと思った。 細い落ち枝から白いカサがたくさん生えているのを見つけたが、これは初めて見る種類で名前が分からない。印象としてはシジミタケを真っ白にした感じだが、チャヒラタケ科の仲間になるのかも知れない。 毎回10人ほどの仲間が毎月1回同じ公園を観察し、それをもう7年以上も続けてきてもまだ初めて見る種類がたくさんある。本当に興味の尽きない奥深さを感じる。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |