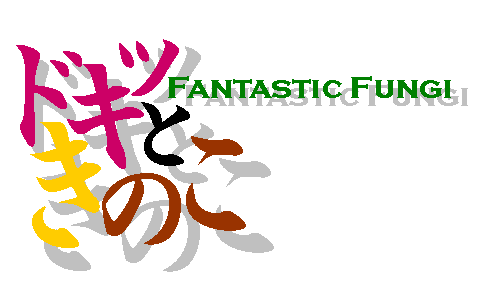 |
 今日はどこまで行ったやら・・・ |
2008年 12月 |
| 2008 | 2007年へ | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 2009年へ |
| 2008年 12月28日(日) 七沢自然保護センター 飯山観音 神奈川県厚木市 |
寒いのが苦手でなおかつきのこが無いとなれば、冬は何もいいことがない季節なのだが、あの憎きヤマビルが姿を消すというのは嬉しいことだ。たかがヤマビルごとき相手に「恒温動物」であることの優越感を覚えるのはヘンだろうか。 という訳で勇んで「七沢自然保護センター」へ行ったら、なんと今日から1月4日まで休館で観察路に入れなかった。仕方なく駐車場付近を歩いてみたら外国産のマツを植えた林に、とても新鮮なヒトヨタケが生えていた。積もった長い松葉を押し上げるような元気な姿だ。 そこでもう1ヵ所のヤマビル封印の解けた場所、飯山観音へ向かった。ここは初めてツバキキンカクチャワンタケを見た想い出のポイントだ。駐車場の近くですぐにそれは見つかった。 尾根筋はカラカラに乾いているので沢沿いのコースを取ったが、沢登りは冷気が流れ降りてくるので手がかじかむほど寒い。それでもしばらく進むと、色のいいムラサキゴムタケを見つけた。 この沢にはニガクリタケがたくさんあるはずなのだが、やっと見つけたのは古くなった一群だけだった。他に朽ちたものも見つからないので、本当に今年は発生が少ない。 ふと、朽ちた木の隙間にある黄色いものが目に留まった。よく見ると幼虫の頭が見える。冬虫夏草のようだが、まだ虫の姿が分かる初期のものだ。色から判断するとコガネムシタンポタケではないかと思うが、この段階ではまだ何とも言えない。 丹念に探したつもりだがエノキタケもヒラタケも、気配すらなかった。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 12月23日(火・祝) 木もれびの森公園 神奈川県相模原市 |
汗ばむほどの暖かさの後でいきなり震えるような寒さになった。たとえて言えば、饅頭を食べた直後にレモンをかじったような気分だ。 柔らかいきのこは探しても徒労に終わると思ったので、硬質菌が豊富な公園へ行ってきた。広い緑地のいたるところに倒木や間伐材を積んであるので、丁寧に探せばそれなりに面白い。 今日たくさん見られた一つにエゴノキタケがある。エゴノキだけにしか生えないきのこだが、ここにはそれだけたくさんのエゴノキがあるということだ。カサの表面はチャカイガラタケとそっくりだが、ヒダが粗いことと樹種から見分けられる。もしチャカイガラタケがエゴノキに生えるとややこしいことになりそうだが、それはないらしい。 逆にエゴノキによく生えているのはアラゲキクラゲだ。かなり干からびたものが多かったが、比較的新しいものとたくさんの幼菌を見つけた。 コナラの倒木にオレンジ色のカサがたくさん並んでいた。ニクウスバタケだと思ったがほとんど背着している部分がない。しかし、裏面は細い針のような薄刃になっているので、やはりニクウスバタケで良さそうだ。 諦めていた柔らかいきのこを1種だけ見つけた。倒木の下の部分で落葉に隠れるように生えていたエノキタケの幼菌だ。日陰で湿度が保たれたので、カサの周囲に水滴を付けた瑞々しいものだった。 ちょっと風が吹くだけで体感温度がグッと下がる。早々に切り上げて逃げ帰ってきた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 12月21日(日) 高麗山・地獄沢 神奈川県平塚市 |
今日が冬至で最も昼間が短いということだが、季節はこれからが本格的に冬になる。今日の高麗山は南風が強くとても暖かい。何か目新しいものに期待して尾根筋を歩いてみたが、上着を脱いでも汗が出るだけで何一つ見つけられなかった。こうなるとやはり残る手段は「地獄の徘徊」しかない。 ところが今日は頼みの地獄沢でさえ「不況」の真っ只中で、極小菌のスケールでも被写体は見つからない。撮影できたのは、ようやく顔を見せ始めたニガクリタケだった。それならいっそのこと・・・と、ニガクリタケを積極的に撮ってみた。 「たかがニガクリ、されどニガクリ」・・・最初は切り株の根元でユリワサビをバックに。次は倒木に生えた柄の長い幼菌。そして、その近くにあったさらに小さな幼菌。 もう当分ニガクリタケを撮りたくなくなった。何でもいいから他のきのこが見たいものだ。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2008年 12月20日(土) 谷戸山公園 神奈川県座間市 |
もう何年もこの公園へ行ってなかった。と言うのも、今までにここでいい写真が撮れた記憶がないからで、今日行く気になったのは「どこへ行っても・・・」という開き直りの気持ちだった。2〜3日前に雨が降り、また少し気温も上がったのでいくつかいい状態のきのこを見ることができた。 降り積もったたくさんの落葉の間に、ポツリポツリと小さなカサが開いている。極端に柄が長いのですぐにアシナガタケだと分かるが、今回撮ったものはかすかにニオイがした。しかし、ニオイアシナガタケとするには弱すぎる。ハッキリしないのはとても困る。 湿地に立つ枯れた木にエノキタケがいいバランスで開いていた。やや萎れかけてはいるがいい被写体になる。少し離れた場所にも一株見つけたが、まだエノキタケの少ない状態が続いている。 斜面の苔の上に一本だけ小さなきのこが生えていた。高さは2.5センチ。一見してムササビタケだろうと思ったが、一本だけではそれらしくない。いい状態だったので思い切りクローズアップしてみたが、種名には自信はない。 ボロボロに朽ちた針葉樹にニガクリタケの一群を見つけた。冬になればとても目立つきのこのはずだが、今年はこれもかなり少ない。秋に雨が少なかったことで菌糸がエネルギー不足になっているのだろうか。 最後はとても小さなきのこ。朽ちた針葉樹に生えたヒナコガサだ。カサの直径は5ミリほどで中央が尖っている。図鑑を見て学名の「nana」が気になった。どうやら「小さい」とか「可愛い」の意味があるらしい。本種にぴったりのいい学名だと思う。 午後2時を過ぎるともう日は傾き、夕日のように赤みが強くなる。冬は撮影に適した時間がとても短いが、焦るほどきのこも多くないのでちょうどいいのかも知れない。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 12月14日(日) 新治市民の森 神奈川県横浜市 |
朝から冷たい雨が強く降っていた。こんな日でも定点観察は8人の参加者で行なわれた。もう酔狂や変人などという域を超えてしまった集団としか思えないが、そんな中で率先してきのこ探しをしている自分も、少しも違和感は感じなかった。 駐車場でいきなり被写体きのこ発見の声がする。ここで何度か見ているナヨタケ属のきのこが束生していた。傘を持ってもらっての撮影になったが、コンパクトデジカメでの手持ち撮影は寒さで手が震えてブレるほどだった。大げさかと思った極寒仕様の厚手のダウンジャケットがちょうど良かった。 同じ駐車場の別の場所では、きれいなウスベニイタチタケが生えていた。近くに幼菌もあったが、残念ながらフレームに収まる近さではなかった。春先のまだ肌寒い頃によく見る種類なので、近頃の寒暖の変化にちょっと勘違いでもしたのだろうか。 その後はしばらく硬質菌の観察が続き、天気のせいもあってほとんど撮影しなかった。そんな中で今日最もイキイキしているように見えたきのこは、外皮を広げ始めたツチグリだった。 午後は雨も止んで青空も見えたが気温は上がらないままだった。解散のあいさつが「良いお年を」になって、急に気ぜわしい気分になった。 |
 |
 |
||
 |
||
| 2008年 12月13日(土) 伊豆・一碧湖 静岡県伊東市 |
冬になると出会うきのこの顔ぶれも決まってくるので、何か目新しい種類を見つけたいと思い一碧湖まで足を伸ばした。 最初に目に留まったのはマツカサから生える1本だけのきのこ。 ※後日、ニセマツカサシメジだと分かった。 その近くの倒木を積み上げた所には、ちょうどシイタケがカサを広げ始めているところだった。木の反対側にももう1個出ていたので、食べ頃の2個をいただいた。 朽ちて黒くなった竹の表面に小さな白いカサがたくさん並んでいた。ルーペで見ると網目状になった管孔がある。スズメタケ属のきのこだが、恐らくこれは発光性がないヤミスズメタケになるのだろう。採取して発光を確かめることにした。 もう1種も小さくて名前の分からないものだった。地面から生える直径5〜6ミリのチャワン型のきのこで、短い柄の上に黄色い厚みのあるチャワンを広げている。子嚢菌の仲間だと思うが何科になるのか分からない。柄の部分は白く外側は微粒状で、縁の部分はやや赤みを帯びた粒が並んでいる。※アレウリナ・イマイイ(和名なし)の幼菌らしい(2012/6追記) 時おり陽が差す穏やかな天気だったので、きのこが少なくてもいい散歩ができた。 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
| 2008年 12月 6日(土) 高麗山・ケヤキの広場 神奈川県平塚市 |
今年もとうとう師走になり新年へのカウントダウンが始まる。このところ寒暖の変化が激しくて、今日は朝から冷たい北風が吹いていた。冬になってエノキタケもニガクリタケも少ないようでは、いったいどんな被写体があるというのだろう。 地獄沢から入ってケヤキの広場までを往復したが、やはりきのこはほとんどない。やっとスギ林の中でアシナガタケを見つけた。撮りながら「ニオイアシナガ」だろうと思っていたが、後でチェックすると全くニオイがなかった。 ケヤキの広場の倒木にも何も見つけられず、ヤブツバキの樹下を探すと1個だけツバキキンカクチャワンタケが見つかった。冬から春にかけて長い期間に生えているが、よく探せばひょっとして年中無休のきのこかも知れない。 朽ちたスギの間伐材にはたくさんのヒメカバイロタケモドキが生えていた。カサの上から見ただけではとても地味でおよそ写真向きではないが、ローアングルではヒダがきれいなラインを描いてなかなかいい表情をしている。 最後は極小きのこ。カサの幅が3〜4ミリしかなくて斜面の細い落ち枝から生えている。肉眼ではカサの厚みが薄く見えたのでホウライタケの仲間も疑ったが、写真をよく見るとやはりクヌギタケ属のようだ。 これからしばらくは中型サイズ以上のきのこを見つけることは困難になるが、今年は例年以上に難しそうだ。きのこ目をミクロモードにして、地を這うような探索を強いられそうだ。 |
 |
 |
||
 |
||
 |